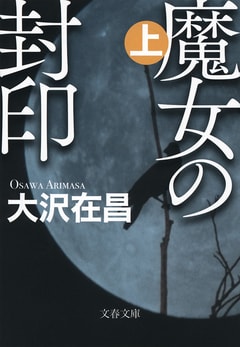本作『極悪専用』は、マンションの管理人とその助手を主人公に、その敷地内だけでの事件を描くという大沢(『やぶへび』・講談社文庫の解説でも触れましたが、大沢のマネージメント・オフィスに在籍していた私としては、さん等の敬称をつけるとやはり心持ちが悪いので敬称は略させていただきます)には珍しい設定の連作短編集です。
この設定が生まれたのは、飲み屋での「マンションの管理人を主人公にしたら面白いよね」という何気ない一言だったようです。一口にマンションといっても、都心のタワーマンションから、郊外のファミリーマンション、単身者が多く住むワンルームマンションなど形態は様々です。年齢、職業、国籍などが異なる多様な人間が共棲するマンションは、魅力的な事件現場に映ったのでしょう。
その時にどのようなマンション像があったのかは知るすべもありませんが、「オール讀物」での連載をスタートさせるにあたり出してきた答えが、世界中の極悪人がセーフハウス的に利用しているという特殊なマンションでした。
入居者のプライバシーは何があっても守り、武器、弾薬、毒物などの持ち込みは暗黙の了解で何でもありのトンデモマンション。その建物が多摩川沿いに建つのは、多摩川を越えると警視庁ではなく神奈川県警の管轄になるからというリアルさ。絶妙ですね。
しかしいざ書き始めてみると、後悔したと大沢は言います。なぜならマンション内とその敷地だけという限られた空間で物語を展開させる縛りを課したため、登場人物たちを動かすのに苦労したようです。それでも、魅力的な女殺し屋や、対戦車砲という大技をくりだし、一級のエンターテインメントに仕上がっています。
本作の主人公は裏社会の大物の孫であることを笠に着て、ヤンチャがすぎたためにこの最悪な環境に管理人助手として送り込まれた望月拓馬クンなのはいうまでもありませんが、もう一人、強烈な存在感の管理人・白旗がまた異彩を放っていて、ダブル主役といった趣があります。
ゴリラのような体つきに毛むくじゃらの太い腕。両頰には横一文字に切り裂かれた傷跡。そのために言語不明瞭。まるでフランケンシュタイン博士の作り出した怪物のような描写ですが、その白旗の切ない過去が物語の展開とリンクしていて、個人的には白旗が主人公だと思って読了しました。
作家が作品内において創造したキャラクターはいうまでもなく、実在の人物ではありません。キャラを練り上げていく過程で、実在の人物、あるタレントやアスリートなどを念頭におくことがあるかもしれませんが、その場合でも具体的な名をだすことはまずありません。
ただ白旗に関しては、実はモデルとなった人物がいるのです。姓をそのまま(漢字表記は変えています)使っていますが、有名人ではないので、読者には誰? という疑問しかないでしょう。作家と編集者の間のお遊びみたいなものだと思います。ゴリラかどうかはともかくいかつい体格はそのままですが、もちろん傷などありませんし言語不明瞭でもありません。
本作の場合は本人の了解もありますので問題は起こりませんが、作家の想像上の人物であるはずなのに、時として誤解によるトラブルが生ずることがあります。たまたま姓名が同じだった、容姿や性格の描写が自分そっくりだということで、勝手にオレを、私をモデルに使ったという思い込みによるトラブルです。信じられないでしょうがそういった抗議が稀にあります。実際、私もそういう電話を受けたことがあります。
そのため多くの書籍には「実在の人物、事件とは関係ない」という断り書きがあるのですが、思い込んでしまった人には通用しませんよね。
フィクションのジャンルとして、実際に起きた事件や、事象をあつかうことがあります。社会派や経済小説などが相当するかと思います。実際の事件をあつかうとフィクションとはいえ、実在の関係者のプライバシーに踏み込むこともあります。そこには常に「表現の自由とプライバシー」の問題が起きえます。三島由紀夫の『宴のあと』はその「表現の自由とプライバシー」が裁判にもちこまれ、初めてプライバシーの権利が認められた作品です。
さて話を本作にもどしましょう。
初めて本作のタイトルを聞いたとき、真っ先に頭に浮かんだのが、大沢が師と仰ぐ生島治郎氏の『悪人専用』でした。この作品は私が出版社在籍中、担当として文庫化したので記憶に残っていたのです。当然大沢の頭の中にもあったでしょうから、生島氏へのオマージュという思いがあったのではないでしょうか。タイトル繫がりでいうなら『ブラックチェンバー』(角川文庫)もまた、生島氏原作のテレビドラマシリーズのタイトルです。
このように生島氏の背中を追いかけて、本格ハードボイルドの担い手としてデビューしたわけですが、同時代は北方謙三、船戸与一、逢坂剛、志水辰夫各氏などの錚々たる顔ぶれが実力を遺憾なく発揮していました。よく軽妙洒脱な作品とか文章などといいますが、洒脱な文章を書かれる方はいらっしゃっても、軽妙なとなるとあまりいなかったように思います。
そのなかで、本作や『アルバイト探偵』シリーズ(角川、講談社文庫)、『らんぼう』(角川、新潮文庫)、『いやいやクリス』シリーズ(集英社文庫)などの軽妙路線(異論はあるでしょうが)を手掛けたのは、本人の志向もさることながら、ハードボイルドの可能性について模索していたからではないでしょうか。
ハードボイルドの定義には百人百様の考え方があります。大沢はよく「惻隠の情」という表現を用いますが、生き方であるということは共通していると感じます。
余談ですが、このようなとき「生き様」がよく使われますが、もともと「死に様」から派生した言葉であり、個人的にはあまり使いたくない言葉です。まあ日本語は生き物であり、日々変化していますので、こんなことに抵抗しても仕方ないとは思いますが。
本人が自身の分身であるという佐久間公の「探偵は職業ではない。生き方だ」という言葉がすべてを表しているとおもいます。本作にあてはめるなら「管理人は職業ではない。生き方だ」となるのでしょう。白旗はまさにそれを実践している人物ではないかと。
だからこそ、白旗の生き方が拓馬に影響をあたえ管理人の仕事に責任がもてる大人に成長したのでしょう。
渋谷あたりによくいる世間を舐めきったような若者も、気弱で心優しいサラリーマン(『坂田勇吉』シリーズ・講談社文庫)もハードボイルドの主人公になりえると証明しているのです。
同時に大沢は『天使の牙』(角川文庫)、『相続人TOMOKO』(講談社文庫)、本作と同じ文春文庫からは『魔女』シリーズなどの女性を主人公にした作品も数多く発表していますし、『流れ星の冬』(双葉文庫)では老人を、といっても六十五歳ですが、主人公にすえています。大沢の手にかかれば、ハードボイルドの主人公に年齢、性別など関係ないということでしょう。そのうちに子供が主人公の作品が世にでるかもしれませんね。
大人も子供もタフでないと、生きづらい今、だから。