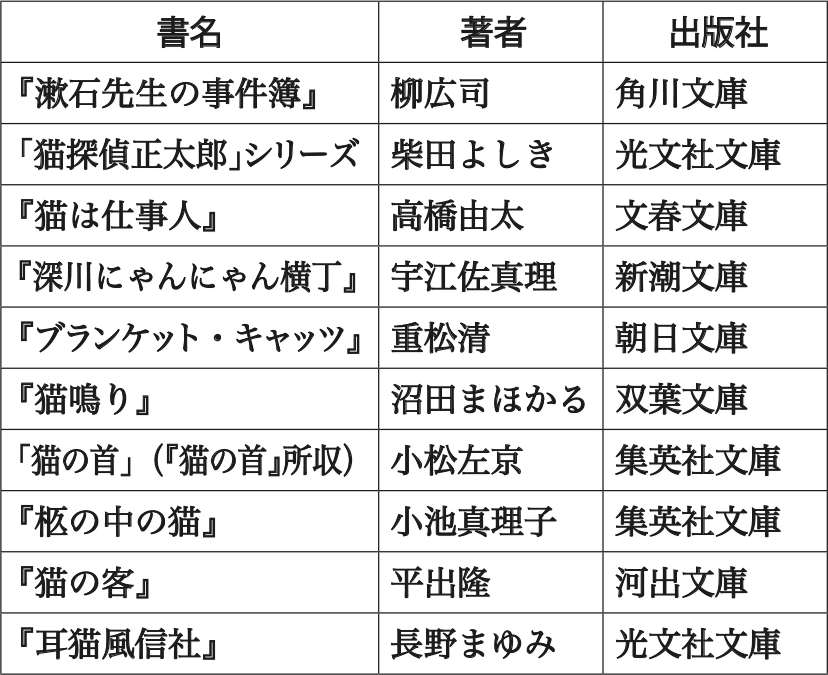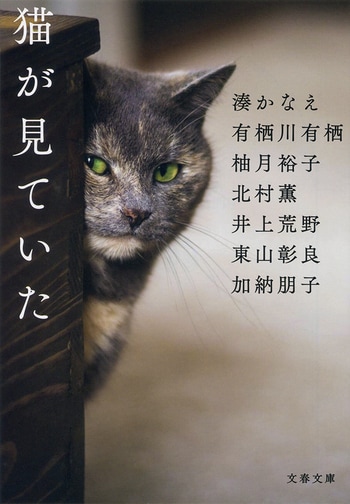自らの体験に基づいて意見を述べれば、猫とは実に恐ろしい生き物だ。私はここで、自信を持って断言する。
大学生の頃まで、私は自他ともに認める犬好きだった。自宅には間抜けな柴犬が一匹いたし、ご近所に飼われている犬たちとも大の仲良し。猫といえば、愛想のない巨大な野良猫たちが、犬と遊ぶ私を遠巻きにしているばかりだった。
そんな生活が一変したのは、二十代半ば。稽古事の師匠が突如、猫を飼い始め、ご自宅にうかがうたび、嫌でもこいつと顔を合わせるようになったのだ。
遠くからじーっとこちらを見ている癖に、急に近づこうものなら、脱の勢いで逃げて行く猫。柔らかい毛をわずかに触らせてくれたかと思った次の瞬間、笥の上に駆け上がって、毛づくろいを始める猫。
なかなか胸襟を開かぬそんな猫を見ているうち、私はこいつをどうにか懐かせてやろうと思うようになった。猫好きになったわけではない。ただ本当にふとした気まぐれで、よし、こいつを手なずけてやれ、と考えてしまったのだ。
そう、もうお分かりだろう。これが私の転落人生の始まりだった。
男性は、自分にすげなくする女性をついつい追いかけてしまうという。私はまさにこの思考パターンにはまった挙句、猫に対して疑似恋愛をしかけ、結果、本物の恋に落ちてしまったのだ。
あれから早十五年。今や私はすっかり、猫がいなくては生きていけぬ人間と化している。ふわふわでしなやかで、それでいてちょっとドジな愛すべき猫たち。気高く、孤高を愛し、しかし人の寂しさにふと寄り添ってくれる彼ら。一度虜になったら二度と離れられない彼らほど恐ろしい生き物が、果たしてこの世にいるだろうか。
今回、編集者さんから「猫小説をご紹介いただけませんか」とのお声がけを受けて、私はつくづく、自分の本棚を眺め――そしてため息をついた。
なんということだろう。その時々の興味の赴くまま本を買っているにもかかわらず、いつの間にか私の本棚には、明らかな「猫本」コーナーが出来ていたのだ。小説はもちろんのこと、猫写真集、猫マンガ、猫エッセイ。スポーツには微塵の興味もなく、セ・リーグとパ・リーグの区別すらつかない癖に、そにしけんじさんの『猫ピッチャー』が全巻揃っている事実には、正真正銘、目まいがした。
しかし、それもしかたがない。猫が登場する本の中には、私同様、猫を愛し、猫に振り回されることを喜びとする人々が、必ず登場する。いわば「猫本」に出て来る人物は、もう一人の自分自身。そして書物の中の「私」がどんな猫に出会うかを楽しみに、私はきっと明日もまた新たな「猫本」を買い求めるのである。