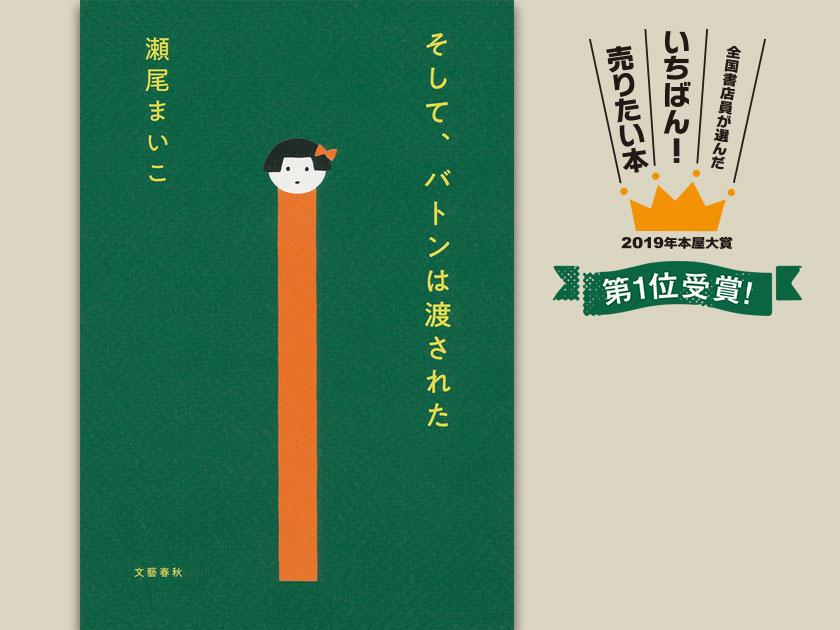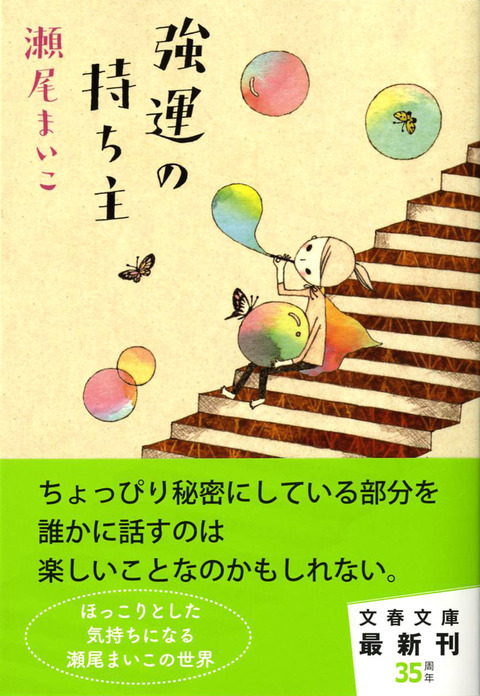──新作の『傑作はまだ』(2019年エムオン・エンタテインメント刊)は逆に、血の繋がりだけがある親子の話です。引きこもりの作家・加賀野のもとに、存在は知っていたけれども会ったことのなかった25歳の息子・智が訪ねてきて、しばらく一緒に住むことになる。これは最初WEBメディアに連載されたものですよね。
瀬尾 もともと違う出版社のものとして途中まで書いていたら担当編集者の方が転職されたので、そちらの媒体に掲載することになり、続きを書きました。その方がすごく愉快な人なので、面白い話、笑える話を書きたいと思いました。
──加賀野の世間知らずっぷりに笑いました。一方の智は社交的で、近所の自治会の人たちともすぐ馴染む。
瀬尾 智のように、屈託のない、垣根のない人は私も好きですね。書いていた頃、私も自治会の会計をしていたんです。自治会ではお年寄りたちが活躍していて面白いと思ったので、地域のそうした話を書こうと思いました。
最後は加賀野があることに気づくシーンで終わりにしていたんですが、担当編集者の方に「この先のシーンを書いてください」って言われて、最後は増やしました。

──そのように担当編集者から何か指摘された時、「いや、それは違う」って思うことはありますか。
瀬尾 いえ。小説に書かないことも自分はこの先こうなる、と分かっていますが、他の人は分からないじゃないですか。だから「読者は分からないですよ」と言われたら「もっともだな」と思います。
──ところで、もともと作家を目指していたのではなかったのだとか。
瀬尾 20代半ばの頃、丹後の中学校で国語講師をしながら正教員の採用試験を受けていたんですが、落ちまくっていたんです。2次試験までは通るようになっていたから、もっと自己PRができればいいなと思って。国語教員を目指していたし、ちょうどその頃一人暮らしを始めていたし、それで小説を書いて応募してみようと思ったんです。
──突然書き始めて、すらすらと書けたのでしょうか。
瀬尾 最初に書いた「卵の緒」は短いものでしたから。鉛筆で、手書きでしたね。それで坊っちゃん文学賞をいただきましたが、その後も正教員の採用試験には2回滑ったので自己PRポイントにはならなかったかも(笑)。数冊本が出てから、ようやく採用されました。