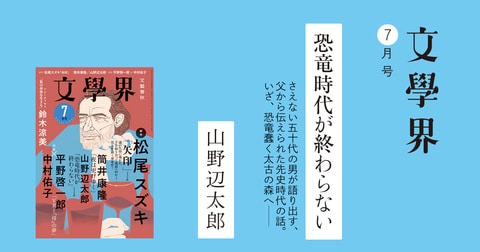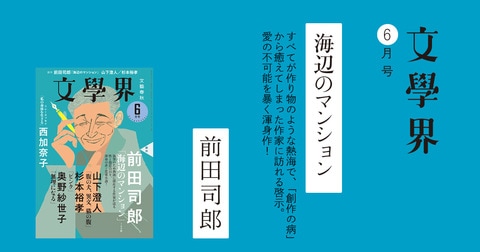1
午前四時過ぎ。リビングの床で、喋っていたかと思ったら突然眠りについた半裸のスミレは、さっきまでの剣幕を思えば、
「可愛らしくてしかたないじゃないか」
ともいえる衣擦れのようないびきをかいている。それをぼんやり聞きながら、俺は、今宵お互いがさんざんやりあった醜いやりとりを「二人が正気に戻ったときに少しでも自分が有利な立場になれますように」という卑しい願いでもって、頭の中で整理しようとしていた。夫婦でけたたましく罵り合いながら四〇本はタバコを吸ったと思う。今、目を閉じたスミレの姿は靄がかかっていて、その周辺だけ切りとれば八〇年代に流行った幻想的な広告写真みたいな雰囲気にも見えるが、タバコの煙の残り香は目に染み、鼻の奥はツンと苦く、ムードなどない。一切ない。
頭の中で再生されるのは、家の裏手に住むジジイの、我が家から出たちょっとした騒音に対するいつものクレームに、スミレが「ジジイを家の中に招き入れて話をしよう」と提案し「いや、今我が家を見せれば、もっと不幸な結果になる」と俺が抵抗したのをきっかけに展開された、お互いの「世間体の正体とはなにか」あるいは「ジジイとはどういう生き物か」という、世界の捉え方に関する本質的な議論と、そこから派生する相手の言葉の揚げ足をただとりあった小賢しいマウントの奪い合い。それらを聖と俗といったように引き離して考えようとするのだが、その二つは、格が違うふうに見えてもしょせん同じ人間から出たもので、根は一つであり、赤と黒、二つの粘土をこね合わせて作ったいびつな風体のトルソーを、元の赤と黒の粘土に分け戻すのは限りなく難しいように、分別不可能なのであるということに気づき、俺は考え続けるのをあっさり放棄したのだった。
そもそも問題はジジイにはない。ジジイはただ死ぬまでの余白の多さに困惑し、俺達ともつれている時間をカジュアルに楽しみたかっただけ。本人は死んだババアの遺影の横でとうに眠って忘れてもう起きる頃だ。その話がなぜ、こちら側の負の遺産として夜明けまで持ち越され、ジジイ不在の揉め事になる? その不毛に大きな問題がある。
いやいつもそうだ。そうじゃないか。細部じゃない、全体をとらえろ。
本当はもっともっと口にしたくないような、恐ろしい問題がある。スミレの思い描く身の破滅を招きかねない劇画チックな野望にけりをつけなければ。
俺は、両手で頭をもみ、椅子の上にさらに浅くだらしなく座って、もう息をするだけでもタバコを吸っているのと同じくらいリビングのニコチン濃度は高いというのに、さらにマイルドセブンに火をつけ、ゆっくり吸って、もっとゆっくり吐き、放電するように静かにしてみた。今の生活において、静けさというものには一〇分で二万円ぐらい払いたいほどの値打ちがある。おかげで脳と頭蓋骨の間に少しだけ隙間が現れ、そこから浮かび上がってきた事実のしっぽをかろうじてつかむことができた。
言い争いは「いつものように」繰り返されているように見えても、その頻度は週三から週五ぐらいの割合で増えていて、互いの傷は癒える前に絶えず新しい傷で更新され、かさぶたの下にすえた臭いのする膿がたまり始めている。つまり、二人の姿は順調に、結婚した三年前に思い描いた未来とはほど遠い、ひどい有り様になって来ているということだ。
スミレよ、もう、引き返すことはできないかな!
でも、それは間違いないのだ。俺は指が焦げそうなほどタバコを吸ってから、二人の吸い殻がうず高く積まれたバケツ型の灰皿の中にねじ込んで、おのれに対してせせら笑った。これでは、自分たちのたたずまいの醜さの重みに自分たちが耐えられなくなって崩れ落ちるのは時間の問題だった。早ければ年内中に別れなくては、致命的な暴力沙汰になるだろう。大怪我をするのはどちらだ? 可能性は五分五分。いや、もう、暴力はとうの昔に芽吹いている。昨日も俺が投げたワイングラス(彼女が飲んでいたものだが)はスミレの鼻先をかすめてキッチン方面の壁で砕け、破片が床やシンクにまで散らばり、中に入っていた赤ワインは、ぶつかった箇所を起点として斜め上方に飛び散り、大気圏に突入し轟々と燃え尽きんとする流れ星のような染みを壁紙に描き、その飛沫は、一メートルほど上にピンで止めてあった南国の海辺を描いたわたせせいぞうの絵葉書にまで及んでいた。なんで自分はわたせせいぞうの絵など居間に飾っているのだろう。それは今どうでもいい。見ようによって、この染みは事件。視覚的には、暴力の思い出。と言われてもしょうがない。後悔はなかった。それに値する人間性の薄汚さをスミレに感じてやった行為だったからだし、それでもまだ言える、愛していると。
この続きは、「文學界」7月号に全文掲載されています。