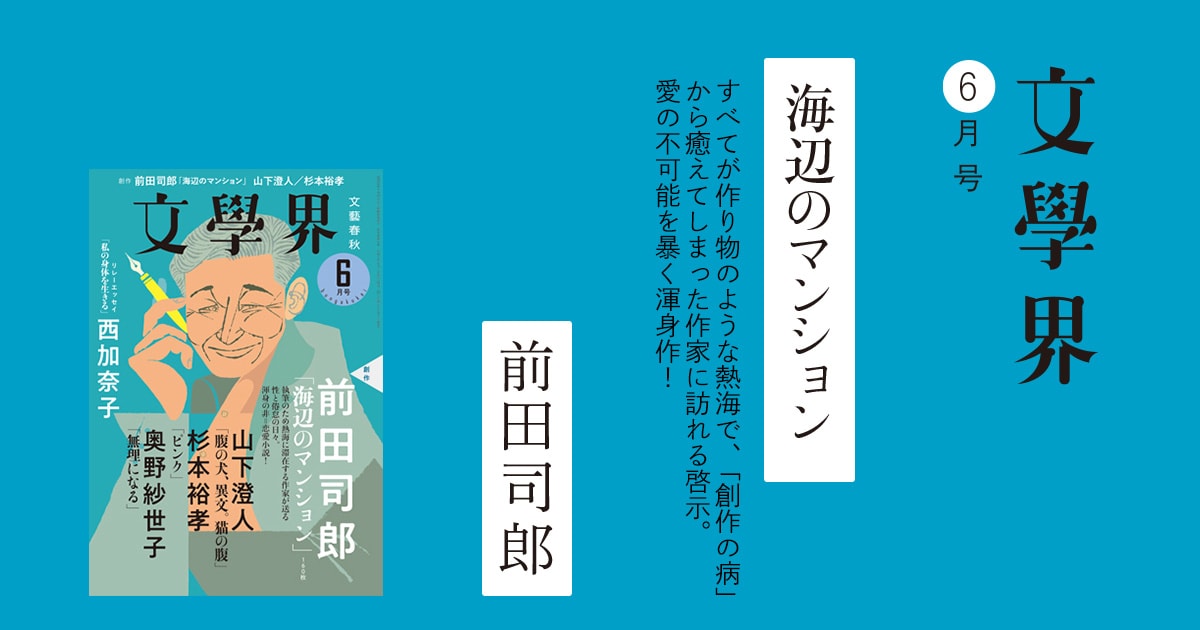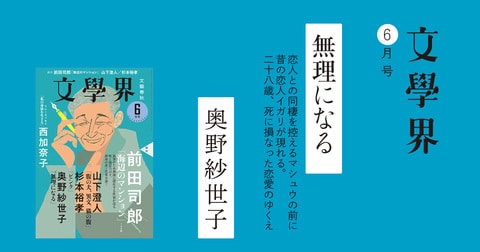今は波の音だけが聞こえる。静寂より静かに感じるのは、静寂もまた音だからだろうか。
互いにほとんど喋らなかった。
頭の中ではきっと誰よりも饒舌に、雑多でどうでも良い事を考えていた。声にすると何か根本の価値が下がるとでも思っているのか、黙っていた。
小森は合板を曲げて造られた三本脚の低い椅子に胡坐をかいて文庫本を開いている。その椅子を気に入っていた。物が好きだった。物は人よりも永遠に近いように思えた。
永遠であり得ない恋人は、暗い、ベランダに向かう窓に背を向け、簡素な木の椅子に座り、楢材の小さな机に向かってときどき教本を確認しながら、たどたどしく鉤針を動かし、今はマフラーを編んでいるらしかった。五月も終りだというのに。
「だって次の冬には使えるでしょ」
「半年しまっておくってこと?」
「ちょうど冬くらいに編み終わる予定なの」
結子は語尾に少し力を込め、小森を追い払うように言った。
「ああ」
少しだけ自分も編んでみたいと思った。でもそろそろ目が駄目だ。近いものが見え辛く感じる。結子は六歳若いから、後六年は大丈夫だろう。
小森は眼鏡を外し、瞼の上から眼球を揉むと、再び本に目を落とす。
妻も子もない。結子も明日には東京に帰ってしまう。
小森はもう随分帰っていない。東京の古い家で父が死に、新しい家で母と猫が死んだ。
「ずれた」
結子が呟く。背もたれに腕をかけ、顎を肩にあて、小森の方を、その奥の、黒い海に向かって大きく切り取られた窓を見ている。編み目でもずれたのだろうと黙っていると「ずれたよね?」ともう少し大きな声で言った。
「え?」
聞き返しながら、結子が何のことを言っているのか判った。
あの歌だ。
波音の向こうから老いた女の声が微かに、インクの切れ掛かったボールペンの文字のように弱弱しく、かすれかすれに漂っている。古めかしい歌詞は、何度生まれ変わってもあなたを愛し続けると誓う。そんなの信じない。
ここでは時々、風のない日に歌が、部屋まで入りこんで来る。
結子は唇をつきだし、少し上を見るようにして耳を澄ませている。
「ベランダに出て歌ってるのかな」
「そうだよ」
「誰が歌ってるか知ってるの?」
「うん」
「お婆さん?」
「ここには老人しかいないから」
結子はしばらく黙って、
「海が歌ってるみたい」
いつの間にか目をつぶって、言った。
「そうかな」
「なんか、船乗りをさ、歌で海に誘い込む魔物いなかったっけ?」
「魔物?」
「知らないけど、幽霊か何か」
「ああ。居たかもね」
「あれみたい」
歌と波音は重なりあって最初から一つだったもののように聴こえた。
・ ・ ・
熱海の街から南に下ると幾つかの岬があって、その一つの岸辺に薄汚れた白い外壁のマンションが建っている。上から見るとLの字が少し馬鹿になったような形をして、遠くから眺めれば海を行く船のように見えなくもない。
この建物はずっと昔、ホテルだった。
部屋数は四百に近く、そのほとんどが十二畳のワンルームで、小森の部屋は十一階にあった。道路に面したロビーは九階。建物に一階と二階はなく、三階からはじまる。故に十三階建てのマンションは実質十一階建てで、十一階の小森の部屋は実際には九階の位置にある。
崖に引っかかるように立っているからだろうか。それにしても一から数えはじめればいいのにと、ここを買う時、不動産屋に聞いてみたが「当時のリゾートホテルやマンションにはそういうのが多かったんですよね」と、答にならなかった。
「四」が「死」に通じるから一階をロビー階と称し、二階を五階と呼称する風習は聞いたことがあった。ここには死の四階が普通にあるわけで、なぜ一階を三階と呼んだのか、住人に尋ねてみても誰も知らない。この地域に土着の死生観とでも繋がった風習や慣例が過去には息づいていたのだろうか。
この続きは、「文學界」6月号に全文掲載されています。