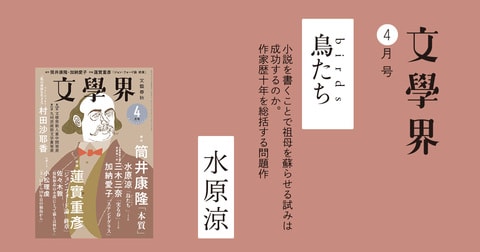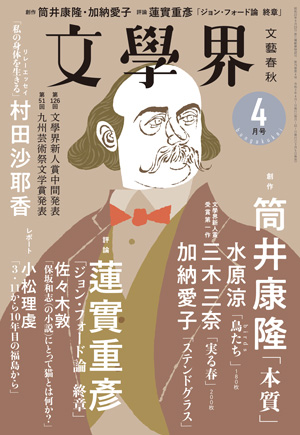
オカンのステンドグラスは深いというよりは鈍い緑色で、テレビに映るヨーロッパの教会を彩っているそれらとは、まるで受ける印象が違った。祈りに導かれているかのようなやわらかい日光が、ステンドグラスを通して教会内にいる観光客に惜しみなく降り注いでいる。ステンドグラスに描かれた体にわずかな布を巻いた二人の女性の、歴史的に重要な意味をもつあたしたち、とでも言いたげなすました顔。しかし見ようによっては、ウチ、なんか忘れたけど何を忘れたか忘れた、ほな黙っとき、といった不毛なやり取りをしているように見えなくもなく、彼女らに端を発して信仰心が立ち上がりそうもない。
それでも、美しさは美しさとしてのみ私の心を奪った。初めて見た荘厳な空間に、ため息に似た力のない声が漏れる。まるで自分がそこにいて、私はちっぽけな存在だと知るという経験をしたかのように。手の届かないその色彩は、透き通るようなターコイズブルーであったし、神秘のエメラルドグリーンであったし、またマリア様の下ろした髪の金色だった。一方オカンのステンドグラスは、沿道で雨に濡れる椿の葉みたいだった。
小学三年生になる頃には、オカンの左の首元にステンドグラスの破片が刺さっていた。破片は全体の三分の一ほどが首に埋まっているように見え、ギターのピックほどの大きさが外に突き出し、肩に対してほぼ平行に、頸動脈の少し後ろにあった。その頃はまだステンドグラスの存在を知らず、なにか色のついたガラスとだけ思っていた。今考えれば、破片という不慮の出来事で生まれることの多い、およそ存在意義をもたないとされる物体がそこにあり続けていることを、未知で理解のおよばない「大人」を捉えるのと無理やり一緒くたにし、どうにか飲み下していたのだろうと思う。オカンにガラスの破片が刺さっている。そう認識していたのは確かなのに、オカンはどうにも被害者には見えなかった。不本意であればそれはお互い様、あくまでもオカンと破片は対等だという風に見えた。くだけた場でも友達の母親達みたいに軽口を叩かなかったのは、破片が抑止力になっていたからやろうか。
夜になると破片がほんの少し下に傾いている時があって、私はそれを見ていつも、落ちたらどないしよ、とハラハラした。オカンは破片がなくなったらえらく悲しむんではないか。ヘタしたら泣き出してしまう? 破片が感情のコルクやったとしたら? えぇぇん、あかんもうなんもする気起きんわ、むりむりむり、風呂もよう入らん、あんたら明日自分でパン焼いて学校行きや、だってオカンは破片ないんやからな、もうおしまいや、オイオイオイオイ。こうなったら絶望ではないか。そんなことばかり考えた。私はこと破片に関してはとても臆病だった。普段から感情的になることのないオカンの、戸惑いや悲しみを受け止める勇気はないに等しかった。
破片をそのままの状態でキープしておくには、できるだけ顔まわりの筋肉は動かさないほうがいい気がして、私は極力話しかけたり触れたりしないようにと心を砕いたが、たいてい夕食の片付けが終わってオカンがタバコを吸いはじめると、破片はゆっくりと元の角度に戻った。それは知りうる限りのどんなものの動きよりも悠然としていて、めっちゃ、大人や、と思い、私はなぜかそのたびに普段の自分の落ち着きのなさを恥じた。破片をじっと見つめる様子は何か物思いに耽っているように見えるようで、オカンはいつも「なんや、ジュースいれたろか?」と見当違いなことを言ったが、私は「ううん」と言って慌てて視線を外し、漫画を取りに行ったりしたくもないトイレに立ったりした。寝る時はどないしてんねやろと考えたが、結局いつもオカンより後に寝ることも先に起きることもできず、真相は謎のままだった。自分の首筋におそるおそる指を這わせたことも、一度や二度ではなかった。
この続きは、「文學界」4月号に全文掲載されています。