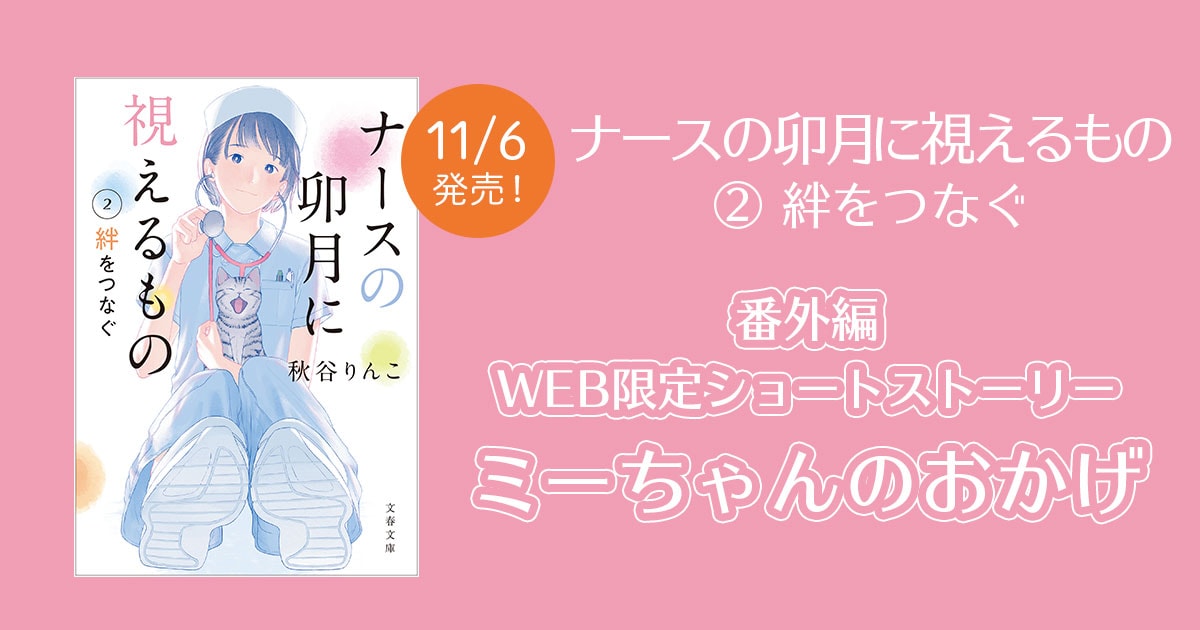絶賛発売中の大人気シリーズ第二弾『ナースの卯月に視えるもの2 絆をつなぐ』。あることがきっかけで猫のアンちゃんと共に暮らすことになった卯月咲笑。WEB限定のショートストーリーをお楽しみください!

爽やかな秋の風が落ち葉をかきまわして去っていく。私は乱れる髪をおさえて、空を見あげた。広く澄んだ青が広がっている。
向かう先は、このあたりで一番大きな病院、青葉総合病院。私が勤めている長期療養型病棟は、完治の見込めない患者さんが多く大変ではあるけれど、病を持ちながらもよりよく生きることへのお手伝いができるのではないかと、やりがいも感じている。
職員用の入り口までとことこ歩く。
「卯月さーん、おはようございます」
聞きなれた声にふりむくと、同僚の山吹奏が手を振って駆け寄ってきた。
「おはよう。あれ、山吹、車通勤なの?」
山吹は、職員駐車場のほうからきた。いつもは徒歩通勤だから、方向が違う。
「いや、歩きですよ。実は、駐車場に猫がいて」
「猫?」
山吹は、キャットフードの袋を見せてきた。
「昨日、遠野と一緒に新しくできたラーメン屋に行ったんですよ」
山吹は、後輩の名前をあげながら「あっちのほうの」と職員駐車場の向こう側を指した。
「そんで、帰りに近道だからって駐車場を突っ切ったら、にゃーって聞こえて」
「猫がいたの?」
「そうなんです。子猫じゃなくて、大人の猫。めっちゃ人に慣れてるから、どこかで飼われている子かも」
話しながら二人で更衣室へ向かう。
「まだいるかな、と思ってさっき見に行ったら、同じところにいて。コンビニでキャットフード買っていってよかったです」
山吹はにこにこしながらエサの袋をバッグにしまった。
「きれいな三毛猫で、かわいいですよ」
「いいなあ、私も会いたい」
私は最近、母から譲り受けてアメリカンショートヘアという種類の猫を飼い始めた。名前はアンちゃん。最初は、慣れない環境に戸惑ったのかベッドの下に隠れて怯えていたけれど、三ヵ月たった今ではすっかり仲良しだ。
今までも猫はかわいいと思っていたけれど、飼い始めてからは、かわいいという言葉じゃ語りつくせない愛おしさを感じている。インターネットやテレビでも、猫が出てくるとつい注目してしまう。
「仕事のあと、また見に行ってみましょう」
「そうだね」
更衣室で白衣に着替えて、病棟へ向かう。勤務が終わるまでは、猫のことはいったん忘れて仕事に集中しなければ。
「あ、あそこにいますよ」
山吹の指すほうを見ると、駐車場のはじ、車の往来のない芝生の上で、毛並みの良いかわいい三毛猫が堂々と横になっていた。仕事終わり、日が暮れ始めていて、街灯が猫を照らしている。
「かわいい。毛もきれいだね」
「そうなんです。野良じゃないですよね」
ゆっくり近づいても、猫は逃げなかった。山吹がそっと手を伸ばすと、猫は体を起こしてニオイを嗅いだ。
「ほら、慣れてます」
「ほんと。逃げないね」
山吹のことを、エサをくれる人だと覚えているのか、猫は立ち上がってしっぽをぴんと立てた。
「お食べ」
山吹がキャットフードを芝生の上に出すと、猫はカリカリといい音をたてて食べ始める。
「人間の前で普通にごはん食べるんだから、やっぱり野良じゃないですよね」
「普通、もっと警戒しそうだもんね」
しばらく夢中で食べていた猫は、満足したのか少量を残して食べ終えた。少し離れたところで体を横たえ、おもむろに毛づくろいを始める。お腹まわりは充分な肉づきがあるから、やっぱり飼い猫のように思えた。
「猫って、本当に気まぐれだよね」
あまりに自由なふるまいに思わず笑ってしまう。
「いいですよね、気ままで。癒されるわ~」
夕暮れの気持ちいい風がふいて、並木のイチョウがさわさわと揺れた。
「猫ちゃんはお腹いっぱいになったみたいだから、私たちも何か食べに行きましょう」
「そうだね」
「昨日、遠野と行ったラーメン行きます? おいしかったですよ」
「え、山吹、二日連続じゃないの?」
「ぜんぜんいけます!」
自信満々に笑う山吹と一緒に、猫を残して歩き出す。駐車場を出るときに振り返ると、猫は前肢で器用に顔を洗っていた。
「あれ? 卯月さん、これ見てください」
ラーメン屋に向かう途中、山吹が見つけたのは電柱に貼ってある迷い猫のチラシだった。
【猫を捜しています。名前:ミーちゃん。三毛猫のメス。特徴:背中の黒い模様がハート形に見えます。〇月〇日に脱走しました。お心当たりのある方はこちらまでご連絡ください。沢田】
写真と電話番号が載せてあり、それはさっきまでかわいがっていた駐車場の猫に似ていた。
「え、この子、駐車場の三毛猫ちゃんじゃない?」
「似てますよね」
「背中にハートマークなんてあったかな」
「それは気づかなかったですけど……ちょっと戻ってみます?」
「そうだね。まだいるかもしれない」
私たちはチラシの写真をとって、急いで駐車場へ引き返した。
「ああ、まだいますよ。よかった。ねえ、君は沢田さんちのミーちゃんなの?」
猫は毛づくろいしていた場所から動いておらず、横になってリラックスしていた。
「ちょっと失礼するよ。あ、言われてみればちょっとハート柄っぽいですよ」
山吹が猫の背中をそっと確認している。私も写真と見比べてみる。たしかに、顔も似ているようだ。
「飼い主さんに電話してみましょうか」
「そうだね」
猫とはいえ、飼い主にとっては大事な家族だ。私だって、もしアンちゃんが逃げてしまったら、と思ったらぞっとする。
山吹がスマホを耳にあてる。
「もしもし、あの、沢田さんの携帯電話でよろしいですか? 迷い猫ちゃんのチラシを見たんですけど……あ、はい。それで、もしかしたらミーちゃんかなっていう子がいるんですけど。そうです、今ここに」
青葉総合病院の職員駐車場に似ている猫がいると伝えると、飼い主の沢田さんはすぐに来るという。患者さん用の駐車場じゃなくて職員駐車場のほうです、と山吹が念をおして、電話を切った。すぐ近所に住んでいるらしい。
「捜している子だといいね」
「そうですね」
風が冷たくなってきた。昼間はまだあたたかいけれど、日が暮れてくると一気に冷える。この猫がもしミーちゃんじゃなかったら、夜中どこで寒さをしのぐのだろうと心配になった。
「あ、あの人かな?」
山吹が立ち上がる。ひとりの女性がケージを持って駆けよってきた。
「沢田さんですか?」
「ああ、お電話をくださった方ですか?」
「そうです。あの、この子、ミーちゃんに似ていませんか?」
沢田という女性は、五十代くらいだろうか。少しよれたロンTを着ていて、とても痩せていた。
「ああ、ミーちゃんです。よかったあー」
沢田さんはケージを置いてミーちゃんにそっと近づき、抱き上げた。両脇から手を入れて持ち上げると、ミーちゃんはだらりと長く伸びた。特に逃げようともせず、おとなしく沢田さんに抱えられた。
「どうして逃げちゃうの。もう……心配したんだから」
沢田さんはミーちゃんに頬ずりをしてから、そっとケージにいれた。
「このたびは本当にありがとうございました。お礼できるものがなくて……」
「いやいや、いいんです! 見つかってよかったですね」
「そうですよ。お礼なんて、気にしないでください」
「すみません。本当に、ありがとうございました」
何度も頭をさげてから立ち去ろうとした沢田さんが「あ、そうだ」と立ち止まった。
「こんなものしかありませんが、もしよかったら」
そう言って、ポケットから近所のお寿司屋さんのクーポン券を出してきた。
「あ、よっちゃん寿司」
山吹が嬉しそうに声を出す。
「ミーちゃんを捜すチラシを配っていたときにお店の方にいただいたんですけど、お寿司なんて食べに行きませんので、もしよかったら……」
「ありがとうございます! ちょうだいします」
ご好意に甘えていただくことにした。
その一瞬、あれ……と気になるものを目にして、少し動揺する。見間違いか……。
「本当にありがとうございました」
何度も頭をさげてからケージを抱えて去っていく沢田さんを見送る。
「ラーメンはまた今度ですね。よっちゃん寿司行きましょう!」
元気に言う山吹の声がどこか遠く感じる。沢田さんのロンTからのぞく細い手首に見えた、誰かにつかまれたような濃い内出血が目に焼き付いていた。
「手首につかまれた痕って、DVとかですかね?」
山吹が、うに軍艦を頬張りながらもごもごと話す。せっかくクーポンをもらったからと、ラーメン屋ではなくよっちゃん寿司に来た。
「わかんない。何かでケガをしただけかもしれないし、もしかしたら内出血に見えただけでうまれつきのアザがある方かもしれないし……」
「ミーちゃんのことはかわいがっているように見えましたけど、全体的にちょっと疲れてそうでしたよね」
「うん。ずいぶん痩せているようだったし」
他人様の体型や顔色から、健康状態を勝手に推察してしまうのは、看護師の悪いクセであると思う。よくない事態を想定するのも、この仕事ならでは、な気がする。
たとえば見ず知らずの人でも「あの人、黄疸でてる。肝機能悪そう。ちゃんと受診しているかな」など、医療につながっているか心配してしまうのだ。その人に言わせれば失礼な話だし、余計なお世話なのだろうけれど。
「もしDVかなんかだとして、私たちに何かできることってありますかね」
「うーん。今の段階では、なさそうだよね」
「ですよねえ……」
私はホタテのお寿司を口にいれる。沢田さんは、「お寿司なんて食べに行かない」と言っていたけれど、今頃何を食べているのだろう。
家に帰ると、ニャニャッと鳴きながらアンちゃんが出迎えてくれた。いつも以上に玄関の開け閉めに気を遣う。脱走予防の金網などを設置している家もあると聞くけれど、賃貸では限界があるので、いつも慎重に家に入るようにしている。
「ただいま」
アンちゃんがスンスンと鼻を鳴らしてニオイを嗅いでくる。よその猫ちゃんを触ってきたから、気になるのだろう。
アメリカンショートヘアはセミコビーというタイプの猫だから、ミーちゃんと比べると少し小柄でずんぐりしている。三毛猫のミーちゃんは、手足の長い日本猫だった。いろんな種類がいて、どの子も個性があってかわいい。
「ちょっと待ってね。手を洗ってくるから」
いつもより念入りに手を洗い、服も着替えてからアンちゃんを抱っこする。猫の病気には感染するものもあるから、気をつけないといけない。
「お留守番ありがとう」
アンちゃんはゴロゴロとのどを鳴らし、私のあごのあたりに額をおしつけた。
「アンちゃん、脱走したりしちゃ絶対にダメだよ」
銀色に輝くつやつやの毛をもじゃもじゃと撫でながら、ふいに寂しい気持ちになる。アンちゃんがいなくなってしまったら……想像しただけで心配でたまらない。
「どこかに行ったりしちゃ、嫌だからね」
ぎゅっと抱きしめると、もぞもぞともがいて抗議された。
「ごめん、ごめん」
そっと床におろす。ボサボサになった背中の毛を、撫でて整えてあげた。
「今日こそラーメン、リベンジしましょうか」
数日たった日勤後、山吹が声をかけてきた。外は細かい雨が降っている。あついラーメンに心惹かれた。
「いいねえ、行こう」
雨のなかをのんびり歩き出す。職員駐車場を突っ切ろうとしたときだった。
「あれ! あそこにいるのミーちゃんじゃないですか」
車の下で香箱座りをしてじっと雨を眺めているのは、たしかにミーちゃんだった。
「また逃げちゃったのかな」
山吹が小走りに近寄る。
「おーい。ミーちゃん、沢田さんが心配するよ~……あ!」
山吹が大きな声を出す。
「え、どうしたの」
「卯月さん、ミーちゃんケガをしているかも」
「え!」
「見てください。血が出てる」
雨宿りをしているミーちゃんの、左の額に赤い血のようなものがついていた。
「本当だ。血みたい」
「ミーちゃん、ちょっとおいで」
山吹が手を伸ばしても、ミーちゃんは逃げなかった。山吹は傘を閉じてしまったので、私の傘に一緒にいれてあげる。服が濡れるのもかまわず山吹はミーちゃんを抱き上げた。
「ちょっと傷を見てみよう」
私はバッグからティッシュを出し、そっと血を拭いてみる。少し粘性があって乾ききっていない。ミーちゃんはぜんぜん嫌がらず、おとなしい。まさか、ミーちゃんにまで暴力をふるう家族がいるのだろうか。私は、嫌な想像をふりはらって丁寧に血をぬぐう。
「あれ、ミーちゃんの血じゃないのかな」
きれいに拭きとってみると、ミーちゃんはケガをしていないようだった。
「本当ですね。なんだったんだろう。ネズミでもつかまえたんですかね」
「それなら、口に血がつくんじゃない?」
二人で首をかしげながら、沢田さんに電話してみることにした。
「もしもし、沢田さんの携帯電話ですか? あの、数日前にミーちゃんを見つけた者なんですけど……はい。そうです。同じ場所です。わかりました」
山吹が電話をするあいだ、ミーちゃんを抱っこする。傘をさしたまま猫を抱くのは難しかった。傘の柄を肩と耳ではさむようにして、両手でしっかりミーちゃんを抱える。思ったよりずっしりと重くて、あたたかくて、毛は湿っていた。
「沢田さんの息子さんが迎えに来てくれるそうです」
「また逃げちゃうなんて、困っちゃうね」
逃げちゃうミーちゃんも、だけれど、何度も脱走させてしまう飼い主さんにも責任があるのではないかと思ってしまう。自分だったら、一度脱走させてしまったら絶対に二度目はないように気をつける。
タッタッタと駆けるような足音とともに、大きな傘が近づいてきた。
「あ……すいません、沢田っす」
柔道でもやっていそうな、大きな体の青年だった。
「じゃ、すいませんでした」
青年は、高校生くらいだろうか。その年齢特有の不愛想な感じで、それでも手際よくミーちゃんをケージにいれて私たちに頭をさげた。
「あの、ミーちゃんのお顔に血がついていたので、拭いてあげたんですけど……」
青年の顔色がサッと青ざめる。
「ミーちゃんの血じゃないっす。……じゃ」
青年は顔をふせるようにして、駆けていってしまった。
山吹と顔を見合わせる。
「ミーちゃんの血じゃないってことは、誰かほかの人の血ってこと?」
「この前お会いした沢田さんでしょうか?」
「息子さん、体格よかったよね」
「……え、まさか息子さんが沢田さんを?」
「いや……他人様の家のことをそんな風に言うのは失礼なんだけど」
「でも、家のなかで誰かが出血してるってことですよね?」
「そう……だよねえ」
山吹は青年が去っていったほうをじっと見て、
「行きましょう!」
と言った。
「え!」
「沢田さんの家まで行きましょう! 余計なお世話かもしれないけど、けがをしている人がいるかもしれない。もしかしたら、何か力になれるかもしれませんよ!」
私はうなずいて、ふたりで駆け出した。
青年は、大きな傘が特徴的ですぐに見つけられた。こっそりあとをつける。
「ミーちゃんの扱いはやさしい感じでしたから、あの男の子が、とは思いたくないですね」
「うん。でも、沢田さんはすごく華奢だったから、息子さんは暴力を振るうつもりはなくても、ちょっと手があたっちゃっただけでけがをすることもあるんじゃない?」
「……そうですね。それか、息子さんはミーちゃんを迎えにきてくれるってことは沢田さんを嫌ってはいない。だから実は旦那さんがDVをしているとか?」
「考えだしたらキリがないね」
五分も歩くと、青年はある一軒家にはいっていった。大きいけれど古い建物で、庭木が荒れている。表札には「沢田」と書いてあった。
「ここですね、ミーちゃんのおうち」
「けっこう近かったんだ」
「で、どうしましょうか。家までついてきちゃいましたけど、ここで何ができるってわけじゃないですよね」
「うーん、そうだね。せめて沢田さんのお母さんのほうにお話を聞ければ、安心なんだけど……」
余計なお世話とわかっているけれど、どうしてもおせっかいの虫がさわぐ。
そのとき、ガラガラと音が鳴って家の窓が開いた。そこから、するりと身をひるがえして、ミーちゃんが出てきた。
「あ! さっそく脱走しています!」
「本当だ。ミーちゃん!」
私たちの声に、にゃーっと言いながらミーちゃんは足元にすりよってきた。おとなしくしているので、そのまま抱き上げる。自分で窓を開けてしまうペットがいると聞いたことはあるけれど、まさかその現場を目撃することになるとは。
「とりあえず、沢田さんに返しましょうか」
「そうだね」
山吹がインターホンを鳴らす。しばらく応答がない。もう一度押そうとしたとき、玄関のなかからドカドカという大きな音と「きゃっ」という小さな悲鳴みたいな声がした。驚いて身をかたくして、山吹と顔を見合わせる。この家、大丈夫だろうか。
少し警戒し始めたとき、細く玄関が開いた。そこから顔をのぞかせたのは、沢田さんだ。
「あの……ミーちゃん、今まさに脱走しましたけど」
山吹が伝え、私はミーちゃんを沢田さんに差し出す。
「あ、すみません。ありがとうございます」
そう言って、ミーちゃんを受け取るためにドアを広めに開けたとき、沢田さんの顔がしっかり見えた。その目元にはアザがあり、鼻には血のにじんだティッシュが詰められている。
「え……おけが、大丈夫ですか?」
思わず声をかけた。
「あっ……大丈夫です。すみません」
ミーちゃんを受け取ると、沢田さんはバタンとドアをしめた。
「え……何、どういうこと? 通報案件ですかね?」
「……わかんない」
家には、沢田さんと息子さんがいるはずだ。鼻血が出ていたみたいだったから、ミーちゃんについていた血は沢田さんの鼻血だろうか。やっぱり、あの息子さんが母親に暴力を?
「どうしましょう」
「とりあえず、明日樺沢さんに相談してみよう」
樺沢ゆかりさんは、病院のソーシャルワーカーだ。ソーシャルワーカーとは、福祉、介護、医療、教育などを総括的に捉えて支援する職業である。役所との橋渡しもしてくれて、地域との連携にも欠かせない存在だ。樺沢さんは若々しくて溌剌としていて、頼りになる。
「そうですね」
私たちは後ろ髪をひかれながら、沢田家をあとにした。
雨はやみ、清々しい秋の爽やかさがもどってきた。談話室の窓からの光が、きらきらと廊下を照らしている。
「家のなかのことは、外からはわかりませんからね……」
樺沢さんに、沢田さんのことを相談してみた。地域医療や福祉の状況に詳しいため、私たちより家庭内の問題の難しさを知っている。
「民生委員さんに相談してみます」
民生委員とは、特別職の地方公務員で、社会福祉の増進につとめる立場の人たちだ。その地域の住民たちの一番近くで相談にのり、必要な援助をおこなう。家庭訪問や地域での情報収集をしながら、高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・母子家庭などに問題がないか見守っている。また、虐待の早期発見、DV、不登校などへの介入、援助もおこなう。
「患者さんのことじゃないのに、すみません。よろしくお願いします」
「とんでもないです。地域の方からの情報がとても大事なんですよ。誤解だったならそれでいいし、問題が見つかれば介入できますから」
樺沢さんはにこにこしながらナースステーションを出ていった。
民生委員さんが見に行ってくれるなら安心だ。私は病棟の患者さんたちに集中しよう、と気持ちを切り替えた。
「卯月さん! 沢田さんのお宅のこと、本当にありがとうございました!」
樺沢さんから連絡がきたのは、イチョウがすっかり散って、道路に黄色い絨毯を作るころだった。
「何かわかりましたか?」
「お知らせするのが遅くなってすみません。実は、沢田さんのお宅にはおばあちゃんが一緒に住んでいまして……」
樺沢さんの話によると、あの家には沢田さんの実母が同居しており、認知症の症状が重く、徘徊や暴力がひどかったそうだ。沢田さんは離婚しており、あの息子さんはまだ中学生で、誰にも相談できずに抱え込んでいた。民生委員さんが訪ねたときも、最初はなかなか家の状況を話してくれなかったらしい。自分の家のことは自分でどうにかする。そう思い込んで誰にも相談できない人はけっこういる。人に頼ることに罪悪感をもってしまっているのだ。
「卯月さんたちのおかげで、おばあちゃんは治療を開始して、訪問看護も導入しました。母子家庭の手当ももらっていなかったので、その援助も始められましたし、沢田さんご自身もそうとうお疲れだったので、心療内科に通い始めることができました。息子さんへのケアもはじまっています」
私は、ホッと胸をなでおろした。
「それは本当によかったです。病棟では、医療につながったあとの患者さんにしか看護ができません。でも、地域では、誰に相談すればいいかわからないまま大変な状況に置かれている方がたくさんいらっしゃるんですね。樺沢さんと民生委員さんがいてくださってよかったです」
「とんでもないです。卯月さんたちが気づいてくださらなかったら、また私たちの手からすり抜けてしまうところでした……。ところで、どうして沢田さんのお宅のことに気づいたんですか?」
「ああ、それは……」
私は、最初に山吹が駐車場で猫を発見してからのことを話して伝えた。
「そういえば、私がお宅に訪問したとき、猫ちゃんいました。きれいな三毛猫ちゃんですよね」
「そうです。もう家出していないかな。脱走の常習犯なんです」
「ぜんぜんそんな感じじゃありませんでしたよ。おとなしくて、外に出ようなんてまったくしていませんでした」
脱走に少しはこりたのだろうか。家で穏やかに暮らしてくれているなら一安心だ。
山吹と職員駐車場を突っ切って歩きながら、樺沢さんとの会話を伝える。
「ミーちゃんのおかげですね!」
山吹が、笑顔を見せる。
「そうだね。たしかに、ミーちゃんに会えなければ、今回の介入はできなかったね。ミーちゃんなりに、家のなかの居心地が悪かったのかなあ」
「いや、違いますよ。ミーちゃんは、自分の家族が大変な目にあっているって、理解していたんですよ。それで、ミーちゃんは医療者に助けを求めるために、この駐車場で誰かに見つけてもらうのを待っていた……。だから、全部ミーちゃんのおかげです!」
自信満々に、嬉しそうに語る山吹が空を見あげる。我慢してしまう人間と比べたら、猫は自由だし、つらいときはつらい、と言えるのかもしれない。人を頼ることに、罪悪感なんてもたないだろう。
もしかしたら、本当にミーちゃんからのSOSだったのかもしれないな。
我が家では、アンちゃんが待っている。私の大事な家族だ。いつまでも一緒に暮らしていきたいから、私も元気でいよう。そう心に決めて、空を見あげた。