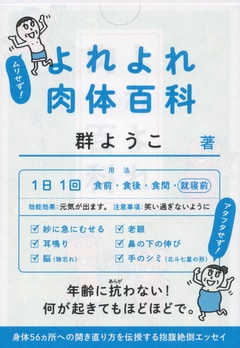〈携帯ギライの群ようこさんが、スマホ購入をついに決断! でも、携帯ショップはカルチャーショックの連続で…〉から続く
愛する老ネコの緊急事態に備え、あの携帯ぎらいの群さんが、ついに重すぎる腰をあげてスマホを購入‼ そのスマホ初体験の日々を綴った話題のエッセイ『スマホになじんでおりません』が待望の文庫化。普段、私たちの日常生活になくてはならない便利なはずのツールですが、前期高齢者の群さんにとって“初スマホ”はカルチャーショック、驚きの連続だった。
電話の切り方が分からず、電源を切る。小さすぎる文字盤の文字入力にすったもんだでえらく時間がかかる。でも、めげないのだ!
携帯ショップを初めて訪れた群さんが、早くも厚い壁にぶちあたる第2話「携帯ショップでパスワード地獄」の続き(後編)、ぜひご堪能ください。

震える指で何度も打ち間違えたショートメール
私があまりに無知なせいか、それとも他に誰も客が来店しないせいか、友だちは、
「ふつうはここまでしてくれないのよ。あのお兄さん、とても親切だわ」
という。彼は携帯も持ったことがなく、スマホを前にしても、「えっ」とか「はあ」しかいわないおばちゃんを、不憫(ふびん)に思ってくれたのかもしれない。
とにかく彼が親切にいろいろとやってくれたおかげで、使えるスマホが私の手に入った。
「ショートメールが使えますから、どなたかに送ってみたらいかがですか」
彼は勧めてくれた。私はショートメールという言葉を聞き、それはいったい何ぞやと思っていたのだが、電話番号宛にメールを送れるというではないか。何でそんなことができるのか、不思議でならなかったが、この頭でスマホのシステムについて考える余裕などないので、文字を打つ方法を友だちに教えてもらいながら、共通の友だちで携帯やiPadは持っているが、まだスマホは持っていない人に、
「いまスマホを買いにきています。もうたいへんです」
と震える指で何度も打ち間違いを繰り返したあげく、たった二十三文字を打つのに、ものすごい時間がかかった。

「はあ」
これだけでも大仕事である。スマホはなぜ、文字を打つ部分がこんなに小さいのか。パソコンのキーボードで文字を打つのは、ピアノを習っていたせいか、とても速いと自負していたのに、一本の指を使って、こんな短い文章にこんなに時間がかかるとはと、がっくりした。
あー、頭が全然動いていない……
するとしばらくして返信がきた。私はぼーっとしていて、それすら気がつかなかったのだが、お兄さんと友だちが同時に、「返信が来た」と教えてくれたのである。
「わあ、すごい。私もがんばらなくちゃ」
彼女にそういわれて、私もがんばらなくちゃと思った。
とりあえず、ショートメールのやりとりはできるとわかり、家での接続をどうするかという話になった。うちはWi―Fi環境にはしていない。なぜかというと、仕事で使っているパソコンは、線でつなげていないとどうも不安なのである。彼はパソコンともども、Wi―Fiにしたら安くなると勧めてきたが、パソコンが不安定になると仕事に影響する。しかしスマホを使うにはWi―Fi環境がないと、アップデートもできず、タクシーも呼べないらしい。その場合は工事なしで、設置して通電するだけで使える機械があるという。この件については家に帰って検討するので、のちほど返事をしますといっておいた。
この時点ですでに一時間半以上経過していて、覚えなくてはならない事柄が、私の頭の容量を明らかに超えていた。確認のための書類が目の前に置かれ、そこには担当者がきちんと説明をしたかなど、チェック項目がいくつも並んでいた。彼はそれを読み上げながら、ひとつひとつチェックしていくのだが、彼の言葉に、「はい」「はい」と返事はするものの、そのすべてが左の耳から右の耳にまっすぐに抜けていって、頭の中には何も残らなかった。
(あー、頭が全然動いていない……)
それだけはよくわかった。書類にサインをし、
「それではこちらのコピーをお渡しします」
と彼が裏に引っ込むと、勢いよく店のドアが開いて、スーツにネクタイ姿の七十代くらいの男性が飛び込んできた。
「あのね、鳴らなくなっちゃったんだよ、スマホが。壊れたみたいなんだ」
彼はものすごくあわてていた。彼の仕事にとってスマホは重要な位置を占めているのだろう。
「昨日まではそんなことなんかなかったのに。いったいどうしたんだろう」
店長が、
「ああ、そうですか」
とスマホを受け取って調べていると、すぐ、
「ああ、これですね。ここがほら、オレンジ色がみえているでしょう。こうなっていると音が……」
といいかけたとたん、彼の言葉をさえぎった男性は、
「あーっ、あーっ、そうなっちゃってた。そりゃあ、鳴らないね。どうもどうも、ありがとう」
と急いで店を出ていった。友だちは、
「ああいう人もいるから、大丈夫」
と小声で私にいった。

難関を乗り越えた群さん、ついにスマホを手にする
数々の難関をのりこえて、スマホが私の手に渡された。私よりもずーっと喋りっぱなしの彼のほうが疲れたに違いない。私はバッグの中に入れていた、プロポリス入りのど飴をわしづかみにして、
「どうもありがとう。このくらいしか御礼ができないけど」
といって彼にあげた。近年、こんなに頭を使ったことがないので、私はくたくたになっていた。店の外に出ると友だちは、
「さあ、カバーとかいろいろと必要だから、ついでに買いにいきましょ」
と近くにある東急ハンズに向かって、元気よく歩き出した。