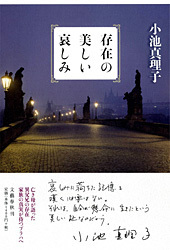──「わたし」の母・奈緒子が最初に嫁いだのが、芸術家を多く輩出している芹沢家です。芹沢家のこと、そして奈緒子の家のことなど、「家族」をテーマにして物語は進みます。近刊『ストロベリー・フィールズ』でも、家族のことが描かれてますが、テーマとして多くとりあげている理由はなんでしょうか。
小池 私にとって親身な問題になったということでしょうね。二十代のとき、生意気にも両親に向かって「私はあなたたちの老後の面倒はみない。私は私の道を行きます」と宣言しました。父も母もその言葉の意味することを理解してくれましたが、自分が五十を過ぎてから、なぜあんなに家族に対して頑なに背を向けていたのかと思うようになりました。そう思っていた頃、父が不幸な病を得て施設暮らしになりました。話せない、歩けない、筆談もできない。それでも父は前向きに生きていました。ワープロのキーをひとつひとつ打って、気持ちを伝えようとしてくれました。そんな父に付き添ううちに、頑なさが溶けてきたんですね。父親は最期まで自分の生き方を貫きました。とても立派なことだと思っています。そのような人間に寄り添ううちに、家族について深く考えるようになったと言えます。
──年齢も性別も違う複数の視点を使って構成することで、「家族」が立体的に見えてくると思いました。さて、各章についてお聞きします。第二章「天空のアンナ」は自分の死期を知った奈緒子が一人で高級ホテルのスィートルームに泊まった夜のことを描いた作品です。
小池 第二章は難易度が一番高かったですね。第一章は「わたし」なのに、次は視点が「奈緒子」ですから。彼女の視点で過去に何があったのかを知らしめなくてはいけない。ただ、「天空のアンナ」がうまく書けたので、第三章「我々は戦士だ」で、奈緒子の同僚だった若者の視点にするという冒険ができました。
──「我々は戦士だ」というタイトルにはびっくりしました。しかし、この章を読むと、小池さんの意図がはっきりと伝わってきます。娘は「母」としての顔しか見えませんが、その「母」も家庭の外に出ればひとりの女性です。若者を視点にすることで、一人の女性として生きた奈緒子の姿が浮かんできます。
小池 若い頃、親は自分との関係性の中でしか捉えられなかった。しかし、いまは小説家として「神の目線」で俯瞰して見ることができます。父の遺品を整理しているだけでも、これまで気づかずにきた彼の人生が見えてきますから。
──タイトルは最初から決まっていたんですか。
小池 テレビで「ダッカ・ハイジャック事件」のドキュメント番組を見ているときに、この言葉がテロップで流れたんです。感動しましたね。ハイジャックをした日本赤軍兵士の言葉ですが、この時代を経験してきた人間として、思想活動ということではなく、別の意味で深く響いてきました。
──〈別に革命家やテロリストじゃなくても、私たちだって、いつも戦ってるじゃない、いろんなことと。生きてくことは大変で、でも生きている以上、死ぬわけにいかないから、死ぬまで戦って生きていくしかなくて……〉 病魔に冒される奈緒子の感動的なセリフです。
小池 結局、みんな戦っているわけですよ。戦いながら、半分諦めることもあるし、絶望するときもある。それでも、人は生きていくんです。人が残してきた足跡を否定しないという強さ、そういうものが全編に漂えばいいと思いました。