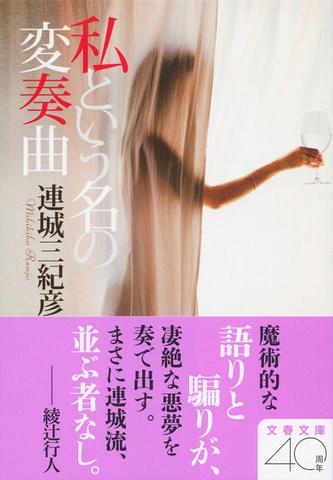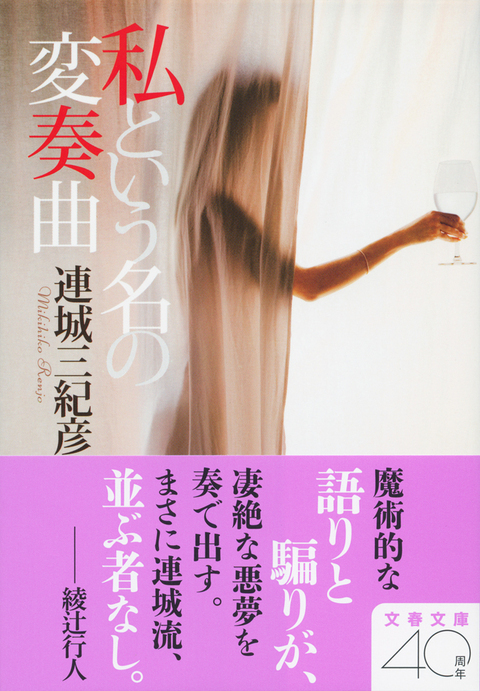まず、冒頭の「私」の章では、最初から死ぬ気でいるレイ子の巧みな心理的誘導によって、何者かが彼女を毒殺する場面が描かれている。やがて死体は通いの家政婦に発見される。現場には、レイ子に婚約を破棄されたため彼女を怨んでいた医師の指紋が数多く残されていた。警察から嫌疑をかけられて逃亡した医師は部下に対し、毒物を携えて現場に行ったことは認めたものの、レイ子を殺したのは自分ではないと主張し、彼女を殺したいほど憎んでいたという七人の男女に揺さぶりをかけて真犯人を炙り出すよう依頼するのだった。
この導入部からしてただならぬスリリングさを孕んでいるが、著者の本領が発揮されるのはここから先なのだ。この小説で著者が挑戦したかった趣向を示すために、単行本のカヴァーと帯に記された「作者のことば」を引用しておきたい。
他の多くのミステリーと同じように、この物語でも殺人事件が起こります。しかし。普通のミステリーでは最後まで隠しておいた方がいいことが、この作品では第一章で明かされています。事件は、他殺と自殺が同時に起こっていて、加害者と被害者の二重奏ともいうべきものかもしれません。その、重要な真相の一部が、最初から読者に提示されています。
もうひとつ――。この物語には、確かに女主人を死にいたらしめた犯人と言える人物が存在していますが、それが登場人物のうちの誰なのか、作者自身が知らずにいます。従って、この作品には“犯人”の章がありません。
二つのルールを破って、それでも、謎があり、解決があるミステリーを書くことが可能か。―――それに挑んでみたかったのです。
これを読んで、本書を読みたくならないミステリファンがいるだろうか。フランスの作家セバスチアン・ジャプリゾの小説『シンデレラの罠』(一九六二年)が刊行された際、版元のドノエル社が掲げた「わたしの名前はミシェル・イゾラ。/歳は二十歳。/わたしが語るのは、殺人事件の物語です。/わたしはその事件の探偵です。/そして証人です。/また被害者です。/さらには犯人です。/わたしは四人全部なのです。いったいわたしは何者でしょう?」(平岡敦・訳)という有名なキャッチコピーに匹敵する、ミステリアスで挑発的な謳い文句と言えるだろう。
この「作者のことば」通り、目次にある各章のタイトルは「私」「発見者」「警察」「容疑者」「警察」「誰か」「誰か」……と続き、「共犯者」という章で終わっていて、「犯人」という章はない。読み進めるうち、ある章で早くも犯人は明らかになったかのように思える。だがそれも束の間、驚くべきことに、新たな「犯人」が次々と登場するのだ。犯人候補である七人の男女はいずれも自分がレイ子に毒を盛って殺したと確信しているため、他にも犯人らしき人物がいるという奇妙な状況に困惑する。いや、もっと混乱するのは、この物語に目を通している読者だろう。七人の男女がレイ子を殺害した状況が全く同じという、悪夢を見るような不可解極まりない謎に直面させられるのだから。誰もが真っ先に推理する可能性は「レイ子は他の六人を相手にした時はお芝居をしていただけで、最後の七人目の時だけ実際に殺されたのだ」というものだろうが、よく読むとどの犯人も、被害者が絶命していることをその場で確認しており(また、本書は地の文に嘘を書いてはいけないというミステリのルールにきちんと則って書かれているため、「死体」という記述があればその通りに解釈しなければならない)、レイ子が死んだふりをしたという可能性は否定されてしまうのだ。そう、この作品のメインとなる謎は、「誰が犯人か」ではなく、「七人もの男女がどうやって同じ人間を殺すことが可能だったのか」というものなのだ。よくもこんな強烈で眩惑的な謎を思いついたものだと感嘆させられる。しかもその謎に、これしかないという意外かつ合理的な解決が用意されているのだから舌を巻くしかない。