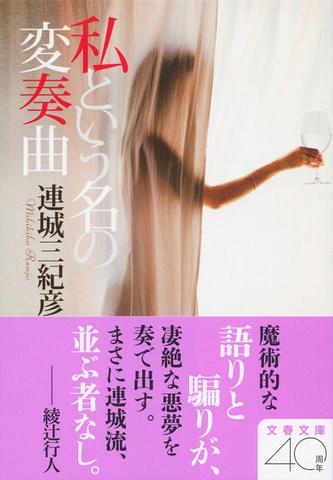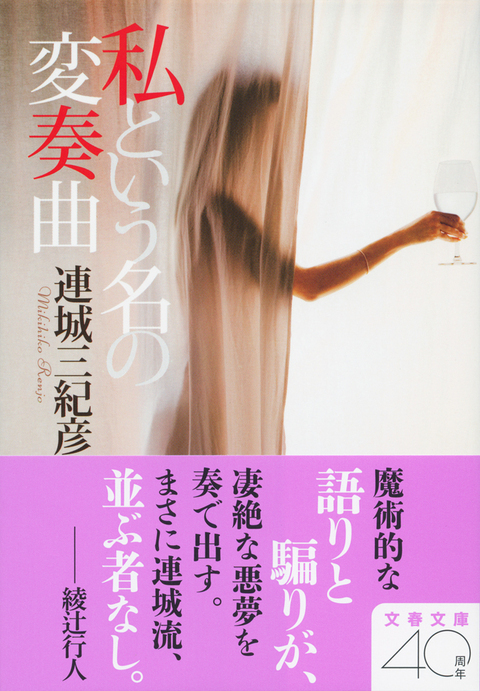人間の死という深刻なモチーフを扱うことが多いとはいえ、基本的にミステリとは、そんな死さえも甘美な物語へと変えてしまう人工的な夢の世界である。現実には、ミステリに出てくるような凝ったトリックを使ってひとを殺めるような犯人は滅多にいないけれども、それをもってミステリの世界を現実離れしていると評するほど野暮な行為もあるまい。
ミステリに出てくる奇抜な、時には華麗なトリックは、最後には解き明かされる運命にあるという意味で、犯人がおのれのすべてを懸けて咲かせた儚い花であるとも言える。だが、すべてを懸けて誰かを欺こうとするのは作中の犯人だけではない。ミステリを書く作家もまた、読者を騙すことに一生を捧げた存在なのである。
そんな騙しの花を生涯咲かせ続けた作家の中でも、とりわけ恐るべき才能を発揮したのが連城三紀彦である。一九七八年に短篇「変調二人羽織」で第三回幻影城新人賞小説部門を受賞して以降、『暗色コメディ』(一九七九年)、『戻り川心中』(一九八○年)、『夜よ鼠たちのために』(一九八三年)、『宵待草夜情』(一九八三年)、『敗北への凱旋』(一九八三年)、『黄昏のベルリン』(一九八八年)、『どこまでも殺されて』(一九九○年)、『落日の門』(一九九三年)、『終章からの女』(一九九四年)、『美女』(一九九七年)、『人間動物園』(二○○二年)、『造花の蜜』(二○○八年)……等々、著者が発表してきた作品の多くは、大胆にして綿密な仕掛けを読者の心理的死角を利用することで成立させた、騙しのお手本のようなミステリだった(なお著者の経歴については、著者歿後に最初に刊行された文庫である『流れ星と遊んだころ』双葉文庫版の解説に記したので、詳しくはそちらを参照していただきたい)。二○一四年三月には、単行本未収録短篇を集成した『小さな異邦人』が文藝春秋から刊行された。著者のファンにとってはこの上ない贈り物と言える一冊だ。しかし、旧作を再評価し、読み継いでゆくのもファンの役目である。今後は品切れになっている旧作の復刊が待たれるが、その先鋒を務めるのが、数多(あまた)ある傑作長篇の中でも掛け値なしの最高傑作である本書『私という名の変奏曲』だ。
本書は、《小説推理》一九八四年二月~三月号に連載され、同年八月に双葉社から単行本として刊行された。《週刊文春》の年間ベストテン投票では国内部門八位に選ばれている。双葉文庫版が一九八八年、新潮文庫版が一九九一年、ハルキ文庫版が一九九九年にそれぞれ刊行されており、今回で文庫化は四度目になる。
ヒロインの美織レイ子は世界的なファッションモデル。五年前、彼女は交通事故で顔に傷を負ったが、天才外科医による整形手術を受けて絶世の美女へと生まれ変わった。しかし彼女は、自分を虚飾に満ちた境遇へと追いやった七人の男女を憎悪し、彼らのみを掴んで脅迫していた。そのため、彼らもまたレイ子を憎むようになる。そして、ついにそのうちの誰かがレイ子に毒を盛って殺害した――だが、その行為さえも彼女の目論見通りだったのだ。