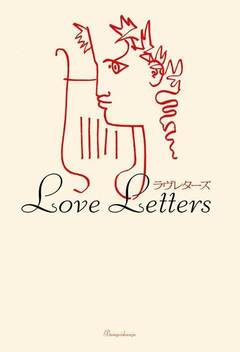父の死を見つめた『エンディングノート』、スタジオジブリに密着した『夢と狂気の王国』など、ドキュメンタリー映画の若手監督として知られる砂田さんの2作目の小説である。
「長崎の原爆資料館に行ったときに、展示物に添えられていた言葉が目に飛び込んできたんです。『長崎はその日、厚い雲に覆われていたが、一瞬の雲の切れ間に原爆が投下された』という……それで、一瞬の悲劇的な出来事によって日常が変化せざるを得なかった人たちを書きたいと思ったんです。まずタイトルを決め、連作短篇形式にしようと考え、交通事故を起こした人物とそれに関わる計5人を描くという骨格を設定すると、それ以上の細かいディテールは決めずに書き始めました」
車の事故で8歳の息子を亡くした母親、加害者となってしまった女性、同乗していた夫、彼と不倫をしていた同僚の女性など5人の視点から描かれる。
元々は、執筆中の長編に行き詰まっていた際、編集者の提案で書き始めたものだと言う。
「今回は映像化を前提に書いたものではなく、その日その日、頭に浮かんでくるものを書き写していくような感覚でした。自分の中から湧き上がってくるものを素直に出しながら書き、改稿しつつ、その精度を上げていくという作業を何度も繰り返しました。
映画はなんだかんだ言っても人物が分かりやすい、複雑そうでも一本筋が通ったキャラクターでないと観客が寄り添えないところがあります。でも小説はそこから少し離れても読み手が併走してくれる感じがあるので、伸び伸びと書けます。キャラクターが次に何を言い、どんな場所に行ってもいいんだ、という自由さがありますね」
事故の当事者にしろ、少し離れて見ている人物にしろ、物語の登場人物たちは皆なんらかの喪失感を抱えて生きている。それを救ってくれるのは、アルバイト先のオーナーや、かつての同級生など、脇役ともいえる人々。
「映画は登場人物が5人いたら、俳優の表情や雰囲気で読み取れる部分はあっても、その人たちの発言以上のことを事細かに説明するのは無理ですよね。文章の面白さは、発言の奥に何層もの心情があるのを表現できること。映像と違い、表面からは読み取れないことを細かく書きたいし、そういうときには強いキャラクターよりも、日常では陰に隠れるような人たちをできるだけたくさん表に出したいんです」
頭の中の映像を文字に落とし込むだけでは単なる変換作業になってしまうと言う砂田さん。肩に力を入れ過ぎずに書けたからこそ生まれた名作だ。