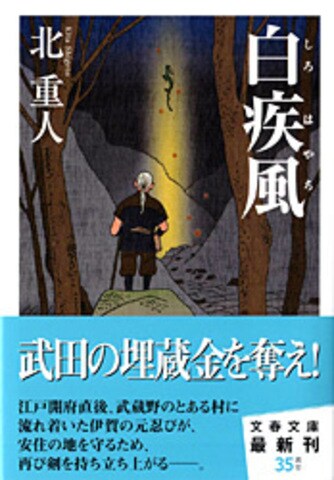しかし作者の故郷への思いは必ずしも郷愁一辺倒ではなく、むしろ敬遠していた時期が長かった。さきに引用した文章に“故郷を想うことは、後ろを振り返ること”という一節があったが、それと同じことを二〇〇八年九月に行われた酒田の講演で語っている。
その講演では、浪人時代から大学時代の苦労話、友人との会社経営と銀行との確執、会社再建の詳細、小説を書きはじめた時期の話(北夫人が最初の読者で、夫人が小説を読み、ほめたという)、文学賞受賞から発病までを振り返り、最後に故郷に対する屈折した思いを吐露したのだけれど、これが胸に響いた。
バブルのときは、ずっと故郷を振り返らずがむしゃらに仕事をしてきた。過去をふりかえることが、自分のエネルギーをそぐように思った。前へ前へと突き進むためには故郷は振りかえる必要はないと思っていた。ところが、バブルがはじけ、さまざまなことを考えるようになり、いつしか故郷に思いをはせるようになった。自分は故郷酒田に育てられた……といって、壇上で思わず感極まり涙ぐんでしまったのである。
それほど故郷への思いが深かったのだが、それは酒田を舞台にした直木賞候補作の短篇集『汐のなごり』(徳間書店)を読めばわかる。時代小説として地元の庄内を舞台に選ぶことは、庄内藩をもとにして海坂藩を作り上げた鶴岡出身の藤沢周平の小説とかぶることになるのだが、北重人は、北前船がつき米相場が開かれていた湊町の水潟(酒田)を舞台にすえる。元遊女でいまは料理屋を営む女将(おかみ)が一人の男を待ち続ける「海上神火」、母親の姿を思いだせない古手間屋の男が、最後の最後に本当の母親の姿を知る「海羽山」、男児ばかり失う祖母の哀しみを捉える「木洩陽の雪」ほか秀作揃いだ。
この作品集のなかには、三十年間、兄殺しの仇討ちでさまよった男が絵師として故郷に帰ってくる「歳月の舟」という作品がある。庄内を舞台にした長年の仇討ちの物語といえば、藤沢周平の初期の名作『又蔵の火』を思い出してしまうが、味わいは異なる。藤沢の初期作品は、直木賞受賞作『暗殺の年輪』をはじめとして暗い情念がほとばしるものが多いけれど、『又蔵の火』もそうで、藤沢周平は登場人物たちの情念を際立たせていく。いっぽう北重人は、ミステリの興趣をもたせ、絵師の人生を静かにやさしく浮き彫りにすることを選択する。藤沢作品が精神の暗黒をのぞかせるノワールなら、北作品は叙情的サスペンスとなるだろうか。藤沢作品よりも強くリリシズムをうちだしている。