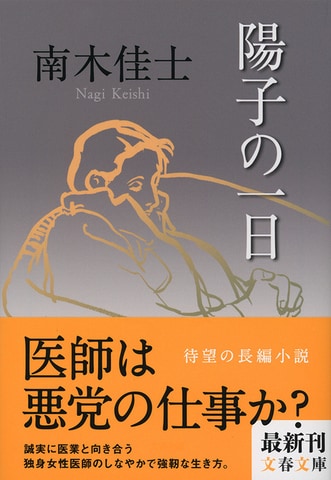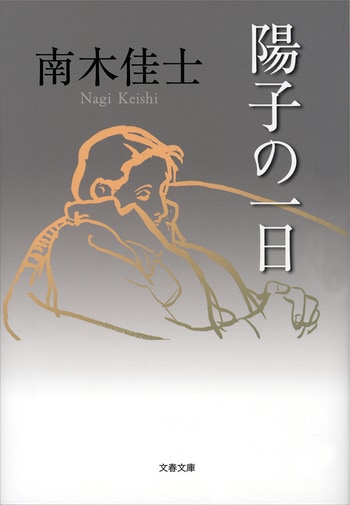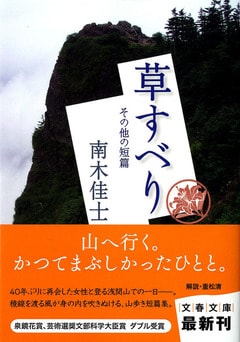三年前に還暦をむかえたとき、なんとなく『自選短篇小説集』を造ってみたくなった。文學界新人賞を受賞して小説家の末席に加わったのが二十九歳だったから、ほぼ三十年、懲りずに私小説を書き続けてきたことになる。おのれの書くものから「わたし」「ぼく」が消え、「こころ」という単語を用いなくなり、代わりに「からだ」が頻出するようになったのはいつごろなのかを確かめたくもあったのだが、自作を読み返しているうちにそんな些事はどうでもよくなってしまった。
研修医二年目のころ、このまま医者を続けるのはなんとか可能な予感はするけれど、生きてゆくうえでなにか大事なことをやり残している居心地の悪さを覚え、気がつけば勤務を終えた深夜、原稿用紙に向かっていた。はじめは、小説というものを一作でよいから完成させ、そのレベルが純文学系の新人賞応募作品のなかのどのあたりに位置するのかを確認し、上位に入らないなら才能なしと判断し、定年までのおおよその人生絵図が描けてしまう勤務医としての生活にどっぷりつかってしまおうと思っていた。
あなたは書きたいものを持っている。
新人賞の一次選考にも残らなかった処女作を読んでくれた編集者からの電話での殺し文句にそそのかされ、とにかく書いて、書いて、いまに至る。
「文學界」に掲載が許可される精度を保った小説を書きながら勤務医の生活を続けるのは、若いうちこそさほど苦にならなかったが、厄年の前あたりで心身が悲鳴をあげ、書くことも医業もままならなくなった。小説など書かなければよかった、と本棚の自著をながめてはうらみがましいため息をつき、とにかく死なないでいるのだ、とじぶんに言い聞かせ続けるだけで精力を使い果たす日々を過ごした。
やがて、底上げ以前の、ただ存在しているだけで許された、おのれの生まれ育った小さな山村の世界をことばで再構築する『阿弥陀堂だより』や、勝手に醸成した都落ちの悲哀で身内を埋めつくし、余裕なき学生時代を過ごした秋田での生活を、じぶんが読みたくなる類のユーモアを交えて再現する『医学生』を、だれからも締め切りを決められずに筆のおもむくままに書くことで、そして、これらの作品が少なからぬ読者に読まれているのがわかって、なんとかこの身の存在意義を見いだせた。
書くことで心身を病み、書くことで寛解を得る。そんな三十年だった。
ふだん、おのれの小説を読み返すことはめったにないのだが、自選短篇集を編む必要に迫られ、短篇にかぎってすべてを読んでみると、処女作である「破水」の文章に最も勢いがあり、いま、どんなにがんばってもこの種のものは書けないな、と実感した。自選集にはあえて文学賞を受賞した作品は収めなかったから、新人賞受賞作である「破水」もはずした。
「破水」は、東京の大学病院で同僚である医者との子を孕み、結婚を望む彼の海外留学についてゆくのをいさぎよしとせず、大学医局から地方病院に派遣された女医が主人公で、彼女が独りで子を産んで育てようとしている姿を描いた短篇だが、この女医、陽子に託した作者の想いがあまりに過剰で、若書きのそしりはまぬがれない。でも、その過剰さが、なぜかたまらなく懐かしい。
こんにち、医者同士の結婚では、女医のほうが勤務先の主導権をにぎるのもめずらしくないから、状況設定も古びつつある。男女の在り方は、時代の流行ではなく、より掘り下げた本質に迫らないと風化するのだ、という大事を教えてくれる作品でもある。
しかし、「破水」を読んでいるうちに、作者だけが勝手に歳を重ね、わけしり顔で評価を下しているだけで、地方病院で地道に働き続け、きちんと子も育てあげた主人公の陽子に還暦をむかえさせてあげないのはすこぶる不公平ではないか、との、もはや過剰とは縁遠い、淡いけれど作家としての根に浸みこみやすい想いが湧き、『陽子の一日』を書かせるきっかけになった。
なぜ書いたのか、と問われれば、ためらいなく、陽子が好きだから、と応える。
二〇一五年 初夏 信州佐久平にて
著者
(「文庫版あとがき」より)