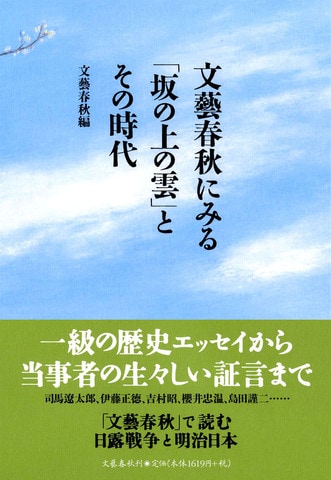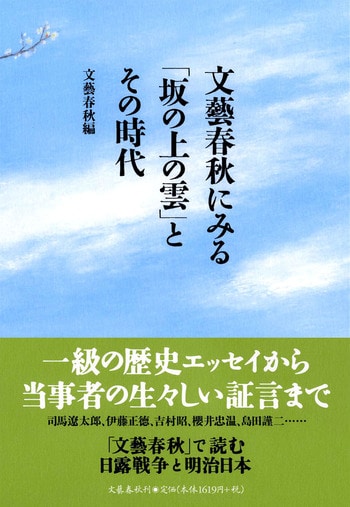NHKが司馬遼太郎の『坂の上の雲』をテレビドラマ化したというので、この作品に対する関心が高まっているのは当然だろう。しかし、司馬作品がテーマとした日露戦争そのものが、日本人にとって、いま振り返ってみるべき巨大な転換期であることも間違いない。本書は、『文藝春秋臨時増刊』(昭和四十七年十一月号)を中心に、『文藝春秋』に掲載された日露戦争関係の論文を集めているが、さらに戦前刊行されていた『話』からも、日露戦争関連の実に貴重で興味深い記事を収録している。
もちろん、司馬遼太郎の「日露戦争の世界史的意義」、児島襄(のぼる)の「大山巌と東郷平八郎」、池田清と江藤淳の対談「海軍の明治」などは必読といえるが、司馬ファンにとっても、日露戦争に関心を持つ読者にとっても見逃せないのが、実際に日露戦争に従軍した人たちによる手記や座談会だろう。
私が、まず読んだのは、旅順攻撃に加わった橋爪米太郎の「白襷(しろだすき)決死隊に参加して」だった。周知のように、白襷決死隊は激闘の末、千人のうち生還したものはわずか四十九名に過ぎなかった。
〈「乃木希典謹んで諸君にお願いする……」
と悲痛な声で言われて、又一渡り皆の顔を見渡された。三千の目は何(いず)れも将軍の温顔に注がれている。名状し難い感動に満ちた眼ざしで……。
と、次の瞬間顫(ふる)える声が我々の耳を打った。
「総員必ず死んでくれッ」
将軍は言われたのだ〉
橋爪は戦闘中、敵が投げ返してきた爆弾をさらに投げ返した刹那、機関銃で前膊(ぜんはく)を貫通される。それでも痛みをこらえて前進しようとしたとき、地雷が爆発して戦友たちがばらばらになって空高く蹴上げられた。この手記には、こうした酸鼻をきわめる戦闘の様子が克明に描かれている。
田村友三郎の「二〇三高地攻撃一番乗り」も、日露の壮絶な陣取り合戦の様子を伝えている。
〈われ等が丁度山頂に達した頃、わが二十八珊(サンチ)榴弾砲は旅順の港内に蟄居していた敵艦に射撃を向けた。わが巨弾は一敵艦に命中し、忽(たちま)ち大火災を起し、真黒な煙を上げていたのを見下ろした時は、誠に目前にある敵を忘れて、自然と皇国の万歳を叫び、もう死んでも恨みはないという気持ちになった。
ややあって敵は奪取された陣地を再び取り返そうと、猛烈に爆弾を投げ逆襲してきた。
わが部下は再び土工器具を棄て憤然と鹵獲(ろかく)弾薬や、石塊を無茶苦茶に投げつけ、これを撃退した。こんなことを繰返して居る間に夕闇も追々迫まって来て歩兵の数も次第に増加したので、確実に此の旅順の天目山といわれる二〇三高地を占領し得たのである〉
ロシア側の記録としては、バルチック艦隊の幕僚ポリトゥスキーが妻に送った手紙が収録されている。この手紙は『坂の上の雲』に頻繁に引用されたが、ごく最近までインターネット上の私家版訳で熱心な読者に読まれてきたにとどまる(長村玄『リバウからツシマへ』文生書院として刊行)。次の手紙は、マダガスカルで書かれたものだ。この時、旅順がすでに陥落したことはバルチック艦隊にも知らされている。
〈極東に於ける我が戦艦の全滅と旅順陥落後は万事、根本的に一変した。今や我等は極東に急ぐの必要を失った。……我が不幸なる祖国の残艦は悉(ことごと)く港内に集合している。我等は既に一箇月前、タンジエールに於て別れた諸艦と此処で会合したのである。露国のものとして残る諸艦はみな此処に集った。これらも亦(また)何等の名誉もなく、恥ずべき滅亡を追わんとするものではないか。ああ我が諸艦は大海軍滅亡の大悲劇の最後の一幕を演ぜんとするものに非ざるか?〉
日露の海戦については、当時の兵曹・機関兵・水兵が参加した座談会「実戦中心の日露海戦勇士の『話』の会」が、近代海戦というものの過酷なむごたらしさを余すところなく語っている。まず、朝日に乗り組んでいた山本半二の証言から、旅順港閉塞戦における広瀬武夫の最期を読んでみよう。
〈一等機関兵曹の小池が「やられました」と云うと、「そうか元気を出せ、代れ代れ」と云ったか云わぬ瞬間、「ウーン」と云う声だか、呻きだか分りませんが、鈍い叫びと共に、ふと私が頭を上げると、少佐の首は見えず、真赤な血が、モクモクと首元から湧(あふ)れ出ると見る中に、その胴体がコロリと海に落ち込んでしまいました。それは一瞬間の出来事です〉
日本海海戦の前哨戦となった黄海海戦で、八雲に乗り組んでいた住吉富蔵の証言を読んでみよう。戦闘中の食事であるビスケットと砂糖を食べようと皆でテーブルについたとき、敵の六インチ砲の砲弾がもぐりこんできて内部で破裂した。
〈その破裂した場所が恰度(ちょうど)十五六人列(なら)んでいるまん中です。それでみんな両脚を掻っ払われちゃった。それが重要な下士官ばかりでした。……渡邉啓四郎という人が弾が中(あた)ったまん中に居ったものですから、乳から下が全部なくなった。……一番ひどいのは工藤了之助という人が両脚をやられて、こんな体で生きていたって仕様がないからといって将校のつけて居った短剣を取って割腹しようとした。それをやらせまいとする。その工藤という人は気が遠くなっていよいよやりきれぬというので、万歳々々々々々々で死んでしまった〉
こうした戦場の生々しい証言に衝撃を受けるが、同時にポーツマス講和会議で交わされた背後の暗闘についての証言にも愕然とさせられる。ハーバード大学を出て金子堅太郎の側近を務め、小村寿太郎外相の秘書官として活躍した阪井徳太郎の「明治の指導者」は、ポーツマス講和会議の舞台裏を知る上で欠かせない。
周知のように、金子はセオドア・ルーズベルト米大統領のハーバード大学の同級生ということもあって、日本とロシアとが講和をむすぶための仲介役をアメリカ合衆国が果たしてくれるよう依頼し、日本の内情についても可能な限り話していた。そうすることが、ルーズベルトのさらなる信頼を勝ち得ると信じていたからだった。
しかし、ロシア側の全権代表であるセルゲイ・ウィッテは、陰謀うずまく宮廷政治を潜り抜けて、ロシアの近代化を推進してきた老練な政治家だった。講和会議に臨むさいにも講和を戦争の延長と考えて、ロシアが敗れたとは認めない姿勢を貫くだけでなく、報道機関が発達したアメリカの世論を味方につけるマスコミ対策すら画策していた。そのことはウィッテの回想記『日露戦争と露西亜革命』に詳しいが、阪井がポーツマスで目撃したのも、まさに回想記に記されたとおりの手ごわい戦略的行動だった。
最初ルーズベルトは日本に対して同情的に見えたが、賠償金と樺太の両方にこだわる金子に対して、突如、手紙で賠償金はあきらめ樺太は南半分で妥協するよう勧めてきた。阪井が手渡したルーズベルトの手紙を読んだ金子は愕然とする。
〈ねぼけ眼でそれを一読するや、金子さんは忽ち満面紅潮、ベッドの上に起き上がり、「馬鹿野郎!」と怒号した。そしてわしづかみにした手紙をもう一度よむや、「馬鹿野郎、こんなこと出来るもんか。」というなり、ゆかの上めがけて、その手紙をたたきつけたのであった。私は驚いて走りよって大統領の手紙を拾い上げた〉
それだけではなかった。ポーツマス条約締結の二、三年後、阪井はある雑誌にルーズベルトが金子に送ってきた手紙が全文掲載されているのを発見する。それはロシア側からリークされたもので、ウィッテはルーズベルトから、金子宛の手紙の内容を完全に知らされていた。ルーズベルトは金子を二重に裏切っていたのだ。表の華やかさとは裏腹の、外交というものの陰湿さと恐ろしさを教えてくれる好論文である。
ここで特記しておかねばならないのが、伊藤正徳の「『三笠』の偉大と悲惨」「続・三笠の偉大と悲惨」の二論文だろう。第二次世界大戦後、ソ連は三笠を廃棄するよう要求したが、アメリカの仲介によってかろうじて保存することができた。ところが今度は、大蔵省が三笠の処分を進めていることを知って、伊藤は激しく抗議するとともに、国民に訴えて三笠保存運動を展開することになる。
〈具体的に言うと、関東財務局は、三笠の艦側に保全されてあったマスト、砲塔、煙突、艦橋の鉄類を、屑鉄商人に払い下げて了ったのである。……そもそも之等の重要部分品は、アメリカの当局が、ソ連と妥協して撤去はしたが、「時勢が改まったら復原を許そう」と考えて、わざわざ艦側にコンポーして保存させておいたものである。外国人さえ惜しんでいたこの三笠の生命を、日本の大蔵省が我が手にかけて断ったのだ〉
伊藤は財界に働きかけて資金を調達しようとしたが、目標金額を達成することができなかった。かわって、目標以上の資金を集めたのが一般からの醵金(きょきん)だった。〈大いに意を強くした歓びは、国民大衆の醵金が予定を六割以上も上廻って、財界の不足分を十分に償った一事である〉。いま横須賀で、三笠の勇姿を見ることができるのは、ここに収められた伊藤の論文があったればこそなのである。
もっと紹介したい論文やエッセイあるいは証言が多くあるが、残念ながらここでは割愛せざるをえない。
この本は『坂の上の雲』の副読本として興味を持って読めることはもちろん、日露戦争そのものについて、もっと理解を深める史料集としても益すること大だろう。付け加えておくと、最近、司馬史観と呼ばれる司馬遼太郎の思想について論じられることが多くなったが、司馬史観の研究を深めるためにも、ぜひ手許に置いておきたい一冊といえる。