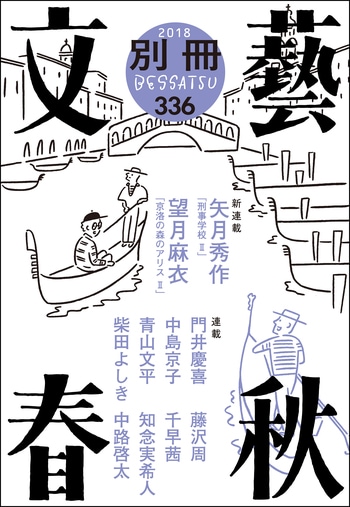「まことにすまん。私から謝っておく」
「別に謝っていただくようなことじゃありません……お義父さん、何か気づきませんか」
「何かって?」
「ここのところずっと、元気がないように思うんです、達夫さん」
「忙しいんだろう。新憲法に合わせて、いろいろといじらなきゃならん法律があるからな。こんなときに法制官僚をやっているなんて、因果なものだ」
そう言って、孝三郎は練炭が燃えるストーブへ足を伸ばした。冷えた足裏を炙る。昭和二十二年二月の寒い時季だった。
前年の十一月には日本国憲法が公布され、施行はこの五月に迫っている。
「忙しいのは、忙しいのでしょうが……」
「あいつ、体に悪いところでもあるのか?」
「達夫さんに聞いても、『疲れているだけだ』って言うばかりで」
「やっぱり、そうだろう」
しかし、雅子は納得のいかない顔つきだ。
「職場で何かあったんじゃないかと思うんです」
雅子の深刻な顔を見て、孝三郎も少々心配になった。だが、役所勤めをしていれば、気にくわないことがあるのは当たり前だ。
「心配いらんよ」
「でも……役所は自殺する人が多いと言いますし」
孝三郎の呼吸が一瞬、止まった。
「いくらなんでも、それはないだろう」
「私も、そうは思うのですが……」
「新しい憲法が施行されたら、あいつも一息つけるさ。新緑の中でハイキングでもすれば、元気を取り戻すだろう」
孝三郎が明るい声で言うと、雅子はうなずいて引き下がったが、その顔はやはり浮かないものであった。
翌朝、布団の中にいた孝三郎は、雅子が庭にいる気配を感じた。まだ薄明の中だが、朝食のお菜をとるために畑に出ているのだろう。とっくに目が覚めていながら、無為に仰臥していた自分を、孝三郎は恥じた。
そのうちに雅子が、
「あれ、あれ」
などと言うのを聞いた。とても驚いた声だ。
何事だ――。
孝三郎はがばと起き上がった。寝巻きの上からどてらを羽織り、慌てて庭に出る。
雅子は竹箒を手にして、畑の脇にしゃがみこんでいた。お腹が痛くなったのだろうか。
「大丈夫か?」
しかし、振り返った雅子は、昨日の憂い顔が嘘のように明るい笑顔だった。立ち上がると、地面を指さす。
「お義父さん、出てきましたよ」
目があまりよくない孝三郎は歩み寄り、雅子が指さした先をのぞき込むように見た。地面から細長い葉がいくつも生え、その真ん中に、緑の茎が十数センチ伸びている。そしてその先端には、うつむくように白い花がついていた。