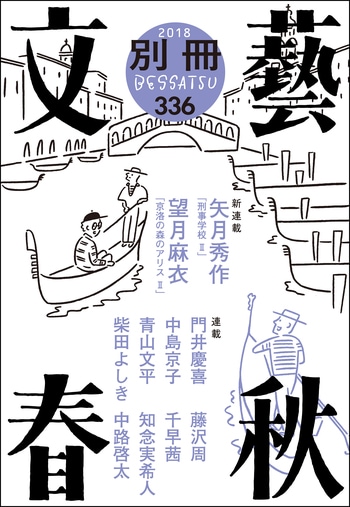「スノードロップですよ」
雅子の声は興奮したものだ。
「たしかに、スノードロップだな」
孝三郎の声も、つい大きくなった。
倅の好きな花だった。
達夫の植物に対する関心は玄人跣で、若いころから、学校の勉強のかたわら、植物学の本やら、植物図鑑やらを図書館で借りては読みあさっていた。このヒガンバナ科のスノードロップも、もともと日本のものではなく、ヨーロッパからコーカサスにかけて野生するらしいが、竹久夢二の絵に描かれているのを見て気に入った達夫は、八方手を尽くして株を入手し、庭で咲かせたのだ。
日本で育てるのは、それほど簡単な花ではないようだった。欲しいという人がいると、達夫は快くわけてやるのだが、よそで育てようとするとすぐに枯れてしまうとのことだ。
しかし、達夫が大事に育て、守っていた庭のスノードロップも、空襲にあってから、見当たらなくなってしまった。「家が焼けたときに、根本から焼けてしまったのだろう」と言って、達夫はひどく残念がっていた。それが、戦災から二年経って、たった一輪だけだが、ひょっこり顔を出したのだ。
三枚の花弁を閉じ加減に、頭を垂れる花の姿は、まるで無沙汰をしていたことを詫びているかに見えた。この花にそれほどの思い入れを持っていたわけではない孝三郎も、冬の朝の寒さを忘れるほどの熱が、体全体から湧いてくるように感じた。この花を見れば、倅の元気もいっぺんに蘇るに違いない。
「達夫はまだ寝ているのか? はやく教えてやれよ」
「そうですね。いま、すぐに」
雅子は駆け足で家にあがった。
やがて、寝巻き姿の達夫が、革靴をつっかけて、雅子とともに庭へ出てきた。髪には寝癖がつき、眠たそうな顔で、風の冷たさに肩をすぼめている。
「ほら、見て。咲いてるでしょ」
雅子が示した花の前で、達夫はしゃがんだ。
「ああ、ほんとだね……どうして、いまごろになって出てきたんだろうね」
感激して笑うわけでも、泣くわけでもなく、寝ぼけたような口調でそう言っただけだった。やがて、立ち上がると、
「寒いね」
と言い残して、家の中に引き返してしまった。
孝三郎は茫然と、雅子と見つめ合った。
こりゃ、なかなかの重症かもしれない――。
見上げると、さっきより朝の光が強くなっている。
「憲法施行まで、あと二月半か……それまでは、やつも大変だよな」
雲一つない真冬の東京の空に向かって、孝三郎はつぶやいていた。