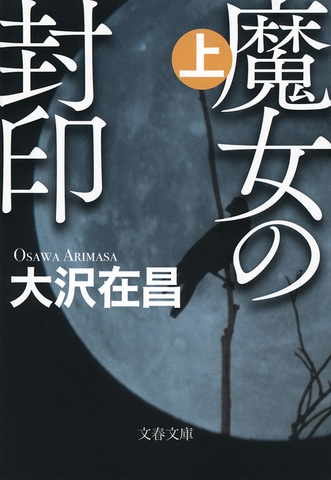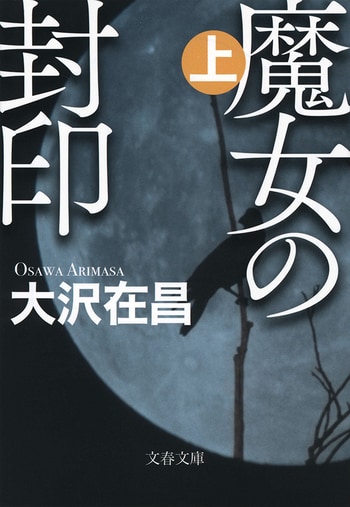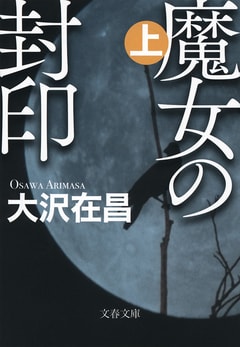日本のミステリー、ハードボイルド史上、こんなにカッコいい女性主人公はちょっといない。今回もラストはあっけにとられた。この女はこんな決着の仕方を選ぶのか。しかし、これしか考えられないなという展開。やはり、魔女水原から目が離せない。
『魔女の笑窪(えくぼ)』(二〇〇六年刊、文庫は〇九年)『魔女の盟約』(〇八年刊、同一一年)に続くシリーズ三冊目となるのが本書『魔女の封印』(一五年刊)である。
第一作『魔女の笑窪』の最初の何章かで、彼女のライフスタイルを垣間見ることができる。午後五時に起きて、東京・麻布台にある事務所に出るのはたいてい午前零時過ぎ。闇のコンサルタントとして裏社会を生きる。駐車場に並ぶのはお抱え運転手がハンドルを握るメルセデスにポルシェ九一一、アコード。闇の投資も辞さず、金に不自由はない。必要に応じて拳銃を手に入れ、ためらわず引き金を引く。男の性格を一目で見抜く力を生かし、タフに冷徹に怜悧に仕事をこなすクールビューティー。気晴らしは高級リゾートでの男遊びとくる。
この水原の活躍を女性読者が知ったら、ハートを射貫かれること請け合い。現に私がそうだ。
普通、男性作家が描く女性は「こんな女いないよ」と女性陣に言わしめることが多い。従順だとか優しいとか、待っていてくれる、許してくれる都合のいい存在。ロマンチックな男の夢想を託した女性像だからだ。ところが水原ときたら、ものの見方や発言に驚くほどリアリティーがある。
『魔女の笑窪』で初登場した時、一夜限りの相手をこう斬り捨てる。〈男が射精(だ)したいとき女をナンパするように、女もやりたいときがある。つまりは道具でしかないのだ。なのに道具以上だと自分を錯覚する。ただの自惚(うぬぼ)れだ〉
本書では、誰かを殺した後の気持ちを聞かれて〈死んで当然だ、とそのとき思い、そして忘れる〉とさらり。
また、〈ひきしまった肉体やひたすら奉仕できる体力、なめらかな肌といった上べの歓びだけを、若い男には求めた〉(『魔女の封印』)と年下と寝る理由を明かす。
本来女は率直で辛辣なのだ。でも、実社会では周囲に気配りした方が生きやすいと知っているから、爪を隠している。ここには本音があふれている。だからこそ水原の言動に胸のすく思いがし、憧れるわけだ。
しかも彼女は十四歳で、実の祖母によって地獄島に娼婦として売られた過去を持つ。男を見抜く目も、何千人もの客を取ったから。必死の思いで島抜けしても、見つかったら追っ手がかかり連れ戻される。整形して別人として暮らす。圧倒的な悲しみや恐怖、孤独をその身に抱えている。そのうえでのタフさ、クールさである。
昨今何かと問題になるセクハラ、女子受験生差別や職場のガラスの天井……。ままならないことが多い現実に、ため息を漏らしながら日々を送っている女たち。それ以上に困難な状況の中、すっくと立つ水原にしびれずにはいられない。
それにしても大沢在昌は、なぜこんなに女のリアルがわかっているのか。文学賞などのパーティーや取材の現場で見る大沢さんのたたずまいはマッチョだ。『新宿鮫』のイメージもある。よほど女遊びしたのか。いや、キーボードの手が滑った。作家の洞察力と想像力のなせる技だろう。もう一つ、この作家の「優しさ」というキーワードもあるような気がする。
大沢さんが日本推理作家協会や文学賞の二次会で、マイクを握った時の司会や挨拶は、場を華やかに明るくする。座持ちがいい。これには持って生まれた素質と、周囲を慮る視線が必要なのではないか。また、インタビュー対応してくれるときには細やかで優しい。こちらの求めていることをすくいとってくれるようなところがある。実は気配りがすごいのではないだろうか。気配りという点では、心性の半分が女なのかもしれない。
「魔女」シリーズは女性のリアリティーだけでなく、そんな大沢さんによる人間観察、社会観察がふんだんに入っている点も魅力だ。
水原の男性分析は面白く、さまざまな男の見本市を見る思いがする。大沢さんは誰かモデルを思い浮かべているのだろうか。
男女論もある。〈女は金で買えるサービスが好きだ。食事の内容よりもレストランの雰囲気を優先したり、何人ものエステティシャンに奉仕されるのに歓びを感じるのは、……それをうけられる自分の立場に酔う楽しみがあるからだ〉〈男は、女を楽しませることによってしか楽しめない。楽しませた女たちが、その夜ベッドルームで、どれだけの返礼をしてくれるかだけを期待してやってくるのだ。/男は損な生きものだ。だが損をしていると感じないのが、たぶん男の才能なのだろう〉(『魔女の笑窪』)
〈ビジネスの元手もなく、コネももたない人間が始められる金儲けが犯罪なの〉(『魔女の封印』)などと社会の流れを切り取ってみせてもくれる。
何となく感じていたり、まったく気づかなかった人間や社会の様相が言葉できっちり説明される快感がある。現実社会を緻密に映し出した物語世界の上で、地獄島をはじめとした大胆な設定も自由に異彩を放つ。
このシリーズはまた、一冊ごとにイメージも規模もぐんぐん変わっていく。
『魔女の笑窪』は地獄島に搾取された女の逆襲だ。背景を彩るのは日本の裏社会と韓国勢力の進出。今から思うと、水原を水原たらしめた地獄島との対決を早くも一巻で終わらせてしまってもったいない気がするが、大沢さんはそんなけちな作家ではない。
第二巻『魔女の盟約』の舞台は釜山、上海、日本と俄然広くなった。上海の元女刑事の復讐を軸に、民族マフィアの萌芽に巻き込まれる。
そして『魔女の封印』は「頂点捕食者」との戦いだ。
問題は、その頂点捕食者である。一般的には生態系の中で最上位に位置する生きもののこと。ノルウェーの生物学者ヘンリック・オルセンが提唱した理論によると、人類が七十億を超えるほどいる現状で地球の頂点捕食者でいるのはおかしい。〈人類は滅亡するか、自然の摂理が新たな頂点捕食者を作りだす〉だろうというのだ。
これを読んだときはなるほどなとうなり、背筋が寒くなった。こういう警告は実際にあるんじゃないかと早速ネットで検索してみたら、どうやらこれは大沢さんの創作らしい。しかし、地球環境を破壊している我々の罪を思うと、〈これだけ数の増えた人間が頂点捕食者であるのは自然に反している〉と言われれば、どこか納得するものがある。現実から予想できるほんの少し先の未来のあるかもしれない形を提示して、説得力がある。しかも、今まで頂点捕食者がいても世界の片隅で孤独に生きるしかなかったものが、ネット社会であるからこそ仲間を見つけるチャンスを得たと展開されると、いちいち膝を打ってしまう。
そういえば、『天使の牙』(一九九五年刊)『天使の爪』(二〇〇三年刊)に登場する脳移植で生まれ変わった女刑事がいた。「天使」と「魔女」で好対照の女主人公。SF的設定も似ている。こちらも読み始めたら、あっという間に手に汗握って物語に没頭してしまった。エンターテインメント小説を構築する手際にほれぼれする。
最後にシリーズにおける水原という人物像の幅の広がりに触れておきたい。
クールさで私たちをとりこにした水原だが、第一巻後半で地獄島育ちの秘密を元警察官でおかまの星川に突然、話す気になった箇所がある。のちに水原への助力を続けることになる星川にぽつりぽつりと語る。星川が、水原の“相棒”になり得た印象的な場面だ。
第二巻では、自らを窮地から救ってくれた元女刑事に恩義を返す。冷徹でありながら違う一面ももつ人となりについて、第三巻で頂点捕食者の堂上はこんなふうに分析する。〈自分より立場の弱い者、庇護を必要としている者に対しては……利益を犠牲にしても手をさしのべることがある。常に、とはいいません。……自分しかできないと気づいたときに限られる〉。ああ、水原はまさにそういう人間だとうなずいてしまう。
そして年下の西岡タカシに対する特別な感情がある。水原に恨みを抱き、第二巻に続き第三巻でも登場してくる。相変わらず図太く挑発してくるが、水原は〈姉か母親のように、あの子を思っている〉と独白する。〈どれだけ大きくなって仕返しにくるかが、ちょっと楽しみなの〉とまでいう。
水原にどんどん血肉がついて、声が聞こえるかのようだ。願わくば、また水原に会いたいのです、大沢さん。