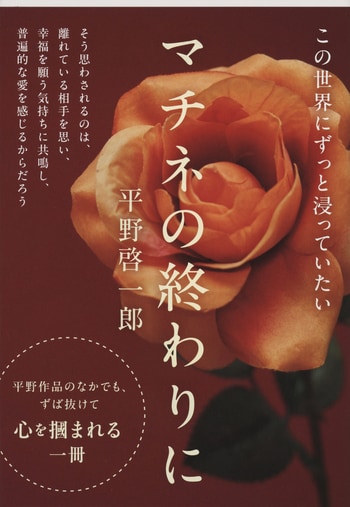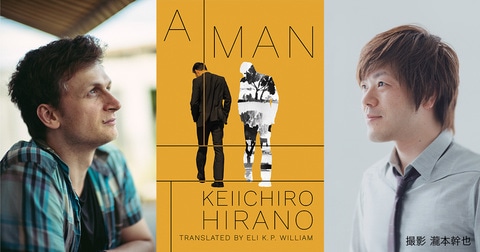『マチネの終わりに』は、二〇一五年に毎日新聞紙上に連載され、翌年、単行本として刊行された長編小説で、文庫化は昨年二〇一九年のことだった。映画化もされ、私自身の本としても、取り分け反響の大きかった、思い入れのある作品である。
本作の構想時、私はとにかく、この世界の殺伐とした現実にくたびれていて、束の間でいいから、何か美しい世界に浸りたいという思いを痛切に抱いていた。しかし、色々な本を手に取ってみるものの、なかなか、ピッタリと自分の心境に合う小説がなく、私はほとんど、自分が読みたい小説を書くようなつもりで、本作に着手したのだった。
小説家の執筆動機としては、何とも内向きであるかもしれないが、結果的に、多くの読者に受け容れられたのは、同じ現代を生きる私たちが、同じ疲弊を共有しているからだろう。
とは言え、私もいい歳の大人であり、あまり人を馬鹿にしたような、夢見心地の話でも白けてしまうので、天才と称されるギタリストの男性と、国際的に活躍するジャーナリストの女性という、浮世離れした二人の愛の背景には、それとのコントラストとして、今という時代の複雑さと困難を、現実的な視点で描くように工夫した。
読者は小説の登場人物の何処に共感するのか? ――なかなか難しい問題で、出来るだけ等身大の、身近な主人公を設定すべきだ、という意見もあるだろう。しかし、私の考えは少し違っていて、例えば『葬送』は、ショパンやドラクロワといった歴史に残る大芸術家を主人公としていたにも拘らず、彼らの人生に共感する読者がたくさんいた。取り分け、仕事をしなければならないと思いながら、一日を無為に過ごして後悔するドラクロワの姿などに、「私は勿論、あんな大画家じゃないですけど、すごくよくわかります。」と言ってくれる人と何度となく会った。
人は出来れば、何か憧れるような世界や人に、自分との共通点を見出して、日々の孤独の慰めとしたいものであろう。それは、文学の備えた優れた特質の一つである。
コロナ禍の自宅待機で、また『マチネの終わりに』を読んでくれた人が多くいたが、パリや東京、ニューヨークといった都市を往来し、コンサートに人々が集い、愛する者同士が抱擁し合うこの小説の世界は、今は格別に愛おしく感じられる。
この先どれくらいの辛抱が必要なのか? 本書が、読者の精神に、ささやかな潤いを齎し得るのであれば、作者としては幸甚である。
(「週刊読書人」2020年7月31日号掲載)