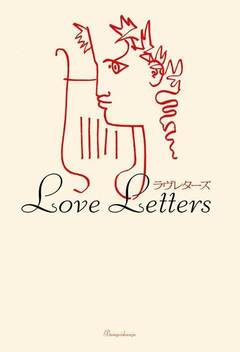小池真理子さんの作品は、どれも虚無の超克をテーマとしている。
それは、別の言葉で言うならば、事の是非善悪を越えて、人間はいかにすれば自由に生きられるのかを常に自作のなかで追究しているということでもある。
虚無というのは人間存在の根幹をなすもので、「不自由」という言葉に置き換えることもできる。なぜなら、虚無は自由意志の一切差し挟まれる余地のない「誕生」によって生じ、これまた一切の意志を撥ねつける「死」によってあらかじめ決定づけられたものだからだ。人は何の意志もなく生まれさせられ、死にたくないと叫びながら死なされてしまう。最初と最後に選択権のない私たちの人生に真実の自由があるはずもなく、その徹頭徹尾不自由な「我が人生」の本質が虚無以外の何ものかであろうはずがないのである。
真実の自由が与えられていないがゆえに、むしろ私たちは、この短くはかない人生の中で自由を求める。自由とは、自分が自分として自分らしく生き通したいという謙虚で切実な願いに過ぎない。小池さんは小説というメディアを使って、その謙虚で切実な願いの成就がいかに困難なものであるかを丁寧につまびらかにし、にもかかわらずそうした自由を求めることが私たちの人生にとってどれほど大切で尊いものであるかを訴えつづけている。
このどうしようもなくむなしい人生に抗うには、否応なく自由を求めねばならない。たとえそのことによって「孤独」という耐え難い副作用を呼び起こしたとしても、最後には一人ぼっちで死んでいかねばならない私たちは、それでもなお自らの自由を守り抜くべきなのだ――そんなふうに小池さんの小説はいつも私たちを励ます。
自由につきまとう孤独をいかにして飼いならすか――これもまた小池作品の重要なテーマの一つである。『恋』にしろ、『欲望』、『無花果の森』、そして私の大好きな『虹の彼方』にしても小池さんは男女の複雑な関係を巧みに表現することで、恋愛が孤独を癒す最も重要な手段の一つであることを示唆してきた。それはまた、人生の虚無自体を一時的に打ち破る、限りなく実体に近い幻影ともなり得るのだと彼女は説き、その小説世界における説得力は圧倒的と言ってもよい。
不動の生死によってのみならず、人は人生の盛りの真っただ中にあっても様々な形で自由を制約される。国家やイデオロギーのくびき、倫理道徳のくびき、金銭のくびき、学校や会社、仕事や結婚、親や子、きょうだいのくびき。数え上げればきりがない。世界は、私たちが生きたいように生き、やりたいようにやることを徹底的に阻むありとあらゆる障害物で満ち溢れているかのようだ。
そうした現実世界の障害物など片っ端から蹴散らしてしまえばいい――不倫、ドメスティックバイオレンス、性的不能、近親相姦といったただならない男女関係を物語の中心に据えて、小池さんは長年、本当の自由の意味を問いかけてきた。何よりも私たちにとって重要な課題は、この人生という虚無とどうやって対峙するのかということ、自由の代償として甘受せねばならない孤独というものとどうやって折り合いをつけるかということ、その二つだけだと彼女の小説はいつも語っている。
言わずもがなも甚だしいが、小説とは人間を描くものであり、人間とは何か? という問いに作家が真剣に答えようとする作業それ自体でもある。従って人間に対する何らかの新しい知見、目を瞠るような表現が一つでも含まれていなければ、それはちゃんとした小説とは言えない。
人間を人間ならしめているものは一体何なのか? 当然人間は他の動物と地続きの存在ではあるが、その発達した神経細胞によって動物的な諸機能を整理、分析、統合し、情動という非常に複雑な系を組み立てている。従って、人間を知るためには、情動を丹念に観察して言語化しなくてはならない。そうすることによって初めて私たちは人間性の本質というものに触れることが可能となる。
この情動という複雑系を描くのが小池さんは本当に上手い。ほれぼれするほどで、私などにはとても太刀打ちできないのだが、負け惜しみとして言うなら、やはりそこには女性という精密な肉体を持たされた者の利点が多分に反映されているのではないかと考えている。
たとえば『恋』という作品で提示されているような、四人の男女を巡る込み入った愛憎関係はあのアクロバティックな筆力がなければとても小説化できるものではないだろう。憎しみに裏打ちされぬ愛などは一時的な感情の明滅に過ぎず、そのような恋愛を描くのは、黒という色を抜いて絵を描くようなものだが、一方、小池さんという作家はその黒の使い方が絶妙の域に達している。だからこそ、『恋』をはじめとした多彩な愛憎劇をあれほどリアルに作り上げることができるのだと思う。
そんな恋愛小説の名手である小池さんが、近年は、徐々に恋愛を介在させない男女関係の世界へと領域を広げているように見える。
実父の人生を半ば借りながら、自分を捨てた父親の晩年に寄り添う長女の姿を追った二〇一二年刊行の『沈黙のひと』にはこれまでのような恋愛関係は出てこない。主人公は、かつて母と自分を置き去りにして愛人のもとへと奔(はし)り、いまは病気によって言語能力を失ってしまった父親の人生を辿ることで、自身の人生と父親の人生とをじわじわと重ね合わせていく。そしてその途上で、たとえ血が通っていたとしても別個の生き物であるはずの父と娘の垣根は次第に取り払われ、二人の過ごした別々な時間もまた神秘的な混ざり合い方をし始めるのだ。
『沈黙のひと』は、中年を過ぎた独身女性の人生を物語りながら、彼女の自由と孤独がいまは亡き父親との関わりによって深い意味を獲得していく過程をしっかりと描き切っている。そうした点で、男女の恋愛を主題としてきたこれまでの小池作品をさらに凌駕するであろう文学的達成を見ていると思われる。
『沈黙のひと』に続いて書かれた本書『死の島』もまた恋愛を持ち込まない男女関係を取り上げた小説だ。
末期の腎臓がんを患う六十九歳の元編集者と、彼の小説講座に通う二十六歳の女性とのあいだに恋愛は成立しない。だが、ここにおいてもその老いた教師と若い教え子とが個別に抱え込んでいた時間は、物語の進行とともに徐々に神秘的に交わり、最終的には老教師の死をもって彼の時間はいまだ生き続ける彼女の人生へと織り込まれていく気配なのである。
「死者は死ぬまぎわ、あまりまともなことを考えないほうがいい」と自嘲する主人公は、一方において、次のように思う。
「生きものはすべて、いずれは自身の死を受け入れるのだ。そして、流れる時が静かに停止する瞬間を待つことができるのだ……。
それは生命をもつものに平等に与えられた才能であり、さらにいえば、ひとつの偉大な力であるような気もした。」
そして、彼は自分を慕う若い教え子に向けて、自らの手で止めた「自分の中を長々と流れ続けてきた時間」を差し出すのである。
この『死の島』は単行本刊行時にすぐに読了した。三年ほど前だが、爾来、この本のことはしばしば思い出しつつ現在に至っている。一番印象に残ったのは、やはり主人公が実行した自決法で、作中の主人公さながら「そんなうまい手があったのか」と感心し、実はいまでも「脱血死」という言葉を頻回に想起している。
というのも、とうに還暦を過ぎた私自身が、最近しきりに、
――一体自分はどうやって死ぬのだろう?
と考え込んでしまうからだ。そして、そう考えるたびに本書の主人公のイメージが自然と呼び覚まされてくる。
そもそも、この主人公の人物設定が私にとってすこぶるリアルなのだ。彼は文秋社という大手出版社で長年文芸編集者として働き、退職後は文秋社が出資し、OBが理事長を務める文化事業団体「東京文芸アカデミー」で小説講座の講師を務めているのだが、まずもってこれがどうにも身につまされる。二十年余りを文藝春秋で編集者として働き、四十を過ぎて作家にはなったもののいまだにサラリーマン気質が抜けていない我が身とすれば、いかにも「俺のことじゃなかろうか」という気にさせられてしまうのである。
小説講座の講師というのも作家にとって身近な仕事だ。小説で食えなくなれば私もそうした講師の口をきっと探そうとするのだと思う。主人公の境遇も似通っている。私も彼同様に四十を過ぎて妻子と別れ、残してきた三十代の一人息子とはほとんど音信不通のありさまだ。両親ともにがん家系とはいえ、幸いいまだがん患者ではないが、しかし三年前に偶然、脳の深部に重大な病変が見つかって、それ以降はその意外な伏兵を前にして毎日をびくびくしながら送るしかなくなっている。
――俺はどんなふうに死ぬんだろうか?
と常々思ってしまうのもやむを得ない状況にはあるのだ。
目を閉じてそのときの光景を想像してみる。死因は何か? 場所はどこで誰がそばにいるのか? 自分はどんな姿で、いかなる心境で末期(まつご)の風景を眺めているのだろうか?
真剣に意識を集中すればかなり正確にその場の情景を予知できるような感じもするのだが、やはりそういう気にはなれない。極度に根を詰めた想像は現実化しやすい、というおそれが自制を生んでしまうのである。
そんな臆病な私にとって、本書に描かれる主人公の心模様は、まさしく自らの死への道筋を目の当たりにさせられるようなリアリティーに溢れていた。心理描写に卓越した小池さんは、非常に丹念に、まるで舌なめずりでもするかのように「脱血死」へと歩みを進める主人公の内面を描いていて、それはもう真に迫ることこのうえない。
死病を得たら俺はきっとこんなふうに考えるのだろうといちいち頷き、まるで自分の番の予行演習でもさせられている気分で随所に赤線を引きながら私は本書の再読を終えたのだった。
いやはや途方もない筆力というほかはない。
聞くところでは、この作品が上梓された直後に、小池さんは、三十数年連れ添った夫君の藤田宜永さんが末期の肺がんであることを知らされたという。そして去年の一月に藤田さんが六十九歳で亡くなるまで彼のそばに寄り添い続けたのだった。そうやって間近で最も大切な人の死をつぶさに観察した小池さんは、いま、この『死の島』で描いた主人公の姿を一体どのような気持ちで見つめ、またそこにどのような新しい発見を付け加えることができると考えているのだろうか?
いずれその答えが見事な作品となって形を成すのを、私はずっと待ちつづけようと思っている。