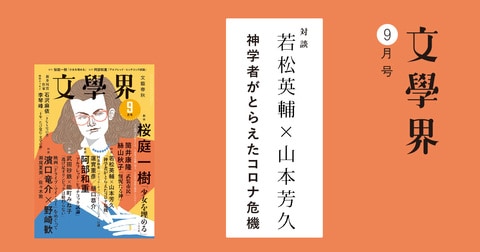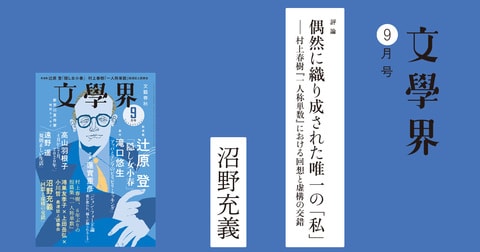村上春樹の原作をみごとに映像化し、カンヌ映画祭で脚本賞ほか4賞に輝いた濱口監督の新作『ドライブ・マイ・カー』。
喪失と再生を描く一七九分を語りつくす!

■冒頭シーンの異様さ
野崎 濱口監督の映画は、いま最も論じられている日本映画ではないでしょうか。濱口さんをめぐる文献が、現代の映画作家の中で例外的な豊かさに達している。観た後にさらに考え、語りたくなるところが濱口さんの映画にはあります。
濱口 観た後で語り合ってほしいと思って毎回作っていますので、すごくありがたいです。
野崎 新作『ドライブ・マイ・カー』はじつに見応えのある映画で、同時に映画という枠にとどまらないとも感じさせてくれます。つまり外に向かって開かれ、いろんなものにつながっていく力がある。映画についての言説はともすれば内に閉じこもりがちだったけれど、そこから先に進んだ次の時代を我々は濱口さんの映画とともに経験しつつある。そう感じさせる作品です。
まず、うかがいたいと思うのは冒頭の場面についてです。試写で観ていて、周りの人たちも息をのむ感じがありました。女性の裸体が映るけれども、背後から撮られていて、かつ逆光でもあり顔が見えない。霧島れいかさん演じる家福音という女性が夫婦でのセックスの後、寝室で夫に向かって不思議な物語を語り出すのですが、あそこで決定的に何かが刻印された感じがしました。あのシーンはいつ生まれたのでしょう?

©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
濱口 冒頭部分はプロットの段階ですでに書き込んでいました。短篇「ドライブ・マイ・カー」を映画化するうえでの様々な変更について、まずは原作者である村上春樹さんに許諾を取らなければいけない。頻繁にやり取りするのは難しいので、「映画化するうえでこういうことをやりたい」というのをできるだけ最初に村上さんに提示しなければいけない。
話をどう膨らませていくか、まず短篇集『女のいない男たち』を繰り返し読むところから始めました。そして短篇「ドライブ・マイ・カー」以外に、同書に入っている短篇「シェエラザード」「木野」を新たに取り入れようと決めました。「シェエラザード」のほうは、短篇「ドライブ・マイ・カー」にはない主人公の妻の描写を足す必要性から、そして主人公の家福悠介(西島秀俊)が最終的にどこへ向かっていくのかと考えたときに、「木野」の要素を加えようと思いついた。家福は具体的にどういう仕事をしているのかというと、原作に「ワーニャ伯父さん」の話が出てきますから、ならば彼はこの戯曲の演出をしているんだと考えていきました。
ただ、妻がセックスの後に物語を語りだすという、「シェエラザード」を基にした設定は、映画の途中で突然出てきたらすごく奇妙なわけです。そこでまずこの状況を当然のこととするようなリアリティの地平を最初に設定する必要性があります。実際この映画は――というより村上春樹さんの小説自体がと言ってもいいのですが――リアリズムではあるけれども、気がついたら現実から浮遊して別の世界へ行ってしまうようなところがある。それを成立させるため、この映画のリアリズムの基準がどのへんにあるのかを設定しなければいけない。冒頭は「こういう映画で、ここから始めます」という、観客への宣言なんです。
野崎 観客への挑戦でもありますよね。それが最初からただならぬ緊迫感をかもし出しています。西島さん演じる家福が妻のその様子を普通に受け止めていること自体も異様ですから。
■異界への入り口
野崎 原作となった短篇集『女のいない男たち』は出版時に読んでいましたが、映画を見て、実は小説のいたる所に異界への入り口のようなものが開いていたことに気づかされました。濱口さんにとっては、それが製作の動機となったわけですよね。
濱口 はい。究極的には僕も自分の映画を異界みたいなところに持っていきたいという思いがある。ただ、いかんせん自分に異界の構築能力がそんなにあるわけではないので、あくまで現実からスタートして、どこまで行けるかということを毎回やっている気がします。村上さんの原作は今まで以上にそれが実現できそうなテキストだった。そのために「ドライブ・マイ・カー」一篇だけではなく、他の短篇に書かれた異界への鍵みたいなものも必要としたんじゃないかと思います。
野崎 冒頭のシーンがどうしてここまでインパクトがあるのか、それはある種の乖離を含んでいるからです。女性の声が聞こえてくるけれども、我々はまだ彼女の顔もちゃんと見ていないので、聞こえてくる声と今見ている女性の姿が一致しているのかどうかよくわからない。しかも声が語る内容が「彼女」という三人称なので、物語と寝室の中の現実がどう結びついているのかもわからない。何か危うさを経験させられるんです。そこで存在感を放つのは「声」です。この女性がその後どうなるかまでは我々は予測できないけれども、何かがズレているという印象は強く受ける。まるで巫女のように、彼女の謎の声の力が魅惑的に働いています。
構成 月永理絵 撮影 平松市聖
(七月二日収録)
はまぐち・りゅうすけ 映画監督・脚本家。1978年生まれ。『ハッピーアワー』(2015)『寝ても覚めても』(18)『スパイの妻』(脚本のみ。20)『偶然と想像』(21)などで海外でも高い評価を得ている。
のざき・かん フランス文学者・放送大学教養学部教授。1959年生まれ。『アンドレ・バザン 映画を信じた男』『ジャン・ルノワール 越境する映画』『夢の共有 文学と翻訳と映画のはざまで』など著書多数。
この続きは、「文學界」9月号に全文掲載されています。