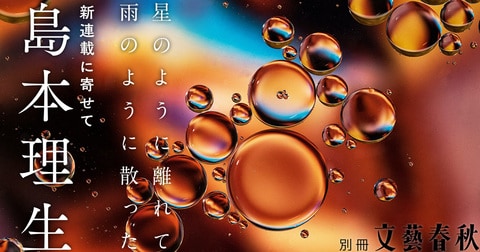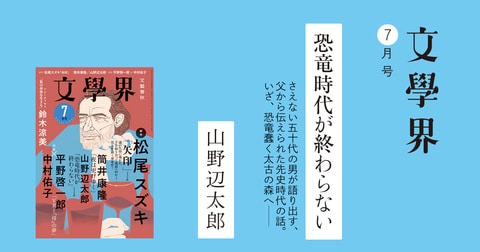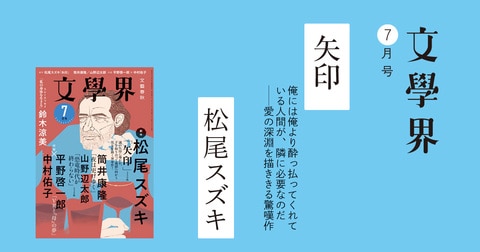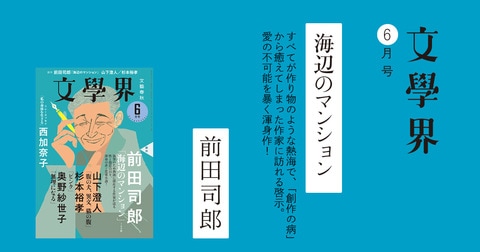鷲田清一『ひとはなぜ服を着るのか』に影響を受けたという二人が、自身のファッションの変遷、洋服によるジェンダー観、作品におけるファッションについてなど、服とどう接してきたのかを語り合う。

――島本さんは本誌3月号のリレーエッセイ『私の身体を生きる』で、『ひとはなぜ服を着るのか』(鷲田清一)に触れながら、ファッションや衣服についてのこだわりや欲望を語ることへの、ためらいや後ろめたさについて書かれていました。山崎さんもまた、同書に影響を受けられたそうですね。
島本 「それなしで生きていけないものを、心のどこかで見下しながら生きるというのは不健康です。」という冒頭の一節が、とにかく衝撃でした。金沢21世紀美術館のミュージアムショップでこの本を見かけて、ふと気になって手に取ったところ、衣服との関わり方を評したその一文に胸を打たれました。それは私自身が、ファッションについて語ることは軽薄なのではないかと、心のどこかで思っていたからだと思います。今の年齢になって考えると、十代から二十代頃の私にとって、ファッションは異性へのアピールに直結していたんです。ファッションとは何か、それをまとう身体とは何なのかという、本質的な言及につながる発想はまったく持っていなかったですし、さらにその先には自身の身体や性差など、色々な角度から論じられる可能性が広がっていることにも、思い至る余地がなかった。
山崎 私の場合は、服の小説を書きたいという思いがまず最初にあって、数年前に『ひとはなぜ服を着るのか』を手に取った記憶があります。もともと私は「かわいい」という言葉が好きで小説やエッセイでわざとよく使っているんだけど、私が十代、二十代くらいの頃は「最近の若い人はなんでも『かわいい』で形容する。言葉が貧困だ」ってくだらない批判があったから、むしろどんどん使っていこうというライフワーク的な思いがあって。今では世界共通語のようにもなっていますが、服を通して「かわいい」とは何かについて書くための過程で、この本と出会いました。私が衝撃を受けたのは、衣服を《第二の皮膚》としてみなす考え方。皮膚の延長として考えれば、服というのはもっと広義に使える言葉かもしれないと思ったんです。
島本 私もその考え方は印象的でした。私は成長する段階で、服そのもののビジュアルだったり、その服が他者に対してどういうことを意味するのか、何をアピールするのかということばかりに関心が向かっていった。でも子どもが生まれてみると、子どもは服をもっと率直な肌感覚で選んでいて、そういえば自分も幼い頃はそうだったなと思い出したんです。今よりも五感が鋭く働いていたときは、そういった感覚に基づいて自分の世界を選んでいたのに、いつの間にか他者や不特定多数の視線に、私というものを明け渡していたということに気づいたんです。
山崎 私の家にいる五歳の子は、服を毎朝なかなか着られないというか、選べない。よく話を聞いてみると、自分の中でその日の気分にしっくりくる服があるはずなのに、目の前にある服はどれもそれじゃないという思いがある。流行に沿っているか、お洒落かどうか、という基準ではなく、今の自分の気分にぴったりではないから着ないと。それは服に対する期待がものすごく高いってことだよね。でも、もしかすると本当に人には誰しも自分にぴったりくる洋服があって、高い期待でそれを求めていくべきなのかもしれない。毎日妥協しながら服を着てるんだなと、私も自覚した。
島本 たしかに。子どものときは服にかぎらず、自分にとっての最適や最高を自然に探していたはずなんだけど、いつの間にか他者を基準にした条件の中から選択する癖がついてしまった。それに関しては、露出とファッションの関係を意識したときに、気づいたことがあります。私自身の話で言うと、数年前に知り合いの男性から、母親なのに肩を出すような服を着るのはよくないと指摘されたんです。たしかに私は肩まわりの開いている服が好きで、よく着ていた。そのときはちょうど、子どもが小学校に入ってPTAに参加したりするタイミングだったので、一般的な母親像というものを自分も踏襲しなければいけないのではないかと思っていた時でもありました。なので自分でも無意識に、肩の出るような服は、男性にアピールしたものではないかと懸念していたというのもあって、首の詰まった服を着るようにしてみたんだけど、なんだかすごく窮屈でした。というのは、私は肩幅が広いので、肩まわりが詰まっていると動きづらくて。そのときに初めて、上半身の可動域が広くて自由度が高くなるから、私は肩の開いている服が好きなんだと気づいたんです。
もっと言えば、他人に自分の服装を否定されたこと自体はあまり気持ちのいい体験ではなかったけど、それについて自分も掘り下げることをしてこなかったなと。特定の価値観を押しつけるようなことを言ってくる相手に対して感じる抑圧はもちろんあるんだけど、自分もそこで思考停止してしまっていた。そうした相互関係から生まれる負の連鎖みたいなものが、いろんなところに潜んでいるのかもしれないと自覚してからは、人目を気にせずに肩の出ている服をたくさん着ようと思っています。
山崎 鷲田さんの衣服を《第二の皮膚》とみなす考え方においては、服を着ることによって、身体にとって本来は外部であるはずの皮膚が、内部に移行する感覚についても書かれていました。だからこそ、他人に服の中に手を入れられるとぞっとしたり、衣服と肌が触れる摩擦の刺激によって自分の身体の輪郭を知覚したりする。むしろ服なしでは自分で自分の存在を確定できないと。
島本 自分にとって最も近いところにある内臓でさえも、医者がいなければ見られない、といったことも書かれていましたよね。それこそ自分の顔だって、普段は他者にしか見えない。だとしたら、他者の目を基準に服を選んでいた自分も、決して間違っていたわけではなかったんだなと思って、その記述には個人的に救われました。
構成:奈々村久生
しまもと・りお 1983年東京都生まれ。98年、「ヨル」で「鳩よ!」掌編小説コンクール第二期10月号当選(年間MVP受賞)。2001年「シルエット」で群像新人文学賞優秀作を受賞。03年「リトル・バイ・リトル」で野間文芸新人賞、18年『ファーストラヴ』で直木賞を受賞。近刊に『星のように離れて雨のように散った』。
やまざき・なおこーら 1978年福岡県生まれ。2004年「人のセックスを笑うな」で文藝賞を受賞。17年『美しい距離』で島清恋愛文学賞受賞。著書に『偽姉妹』『リボンの男』『母ではなくて、親になる』『肉体のジェンダーを笑うな』『むしろ、考える家事』など。
この続きは、「文學界」8月号に全文掲載されています。