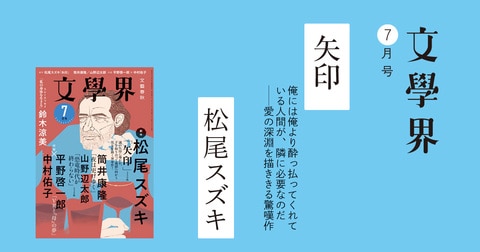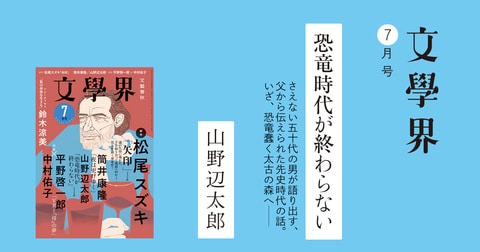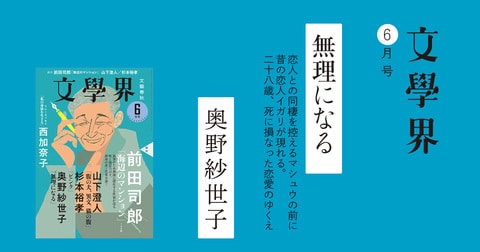森は生きている。
私たちはそこでたしかに息づいている。
文はそうして書き出されている。
当然ながら、これはフィクションではない。これは実際に私の身に起きた、ノンフィクションの文である。
ここに書かれた文のすべては事実であり、ここにあるできごとのすべては、ほとんどそのまま起きた。
もちろんすべてが幻であるという可能性も否めない。それでも私は多くのことを覚えている。私が忘れてしまっていることはほとんどない。
少なくとも、私が忘れてしまっていることについて、私が思い出せることはまったくない。
書かれた季節は夏であり、文の中では春から始まる。
春に降り始めた雪は、今なお降り止むことはない。
こうして文は始まっており、文は次のように続いている。
書いているのは私。
そして読んでいるのは私であり、これらの私は私ではない。
私は一人であり、一人である私の中には、一人ではない私が無数にいる。
私たちはここで、それらの私を私と呼んでいる。
私は無数に存在する。
ただ、目には見えないだけだ。
私はそう考えているように思われた。私の中の何かが私にそう思わせていた。
1
娘の肺には花が咲いている。
花とは文字通りの花であり、何かの冗談でなければ比喩でもなく、正真正銘、植物の花である。
レントゲン写真を見ると、娘の肺は萎縮しており、肺の周辺をぼんやりとした黒い影が覆っていた。右と左の肺の隙間に、ひときわ濃い色の小さな影があった。私はそれを見た。はじめはわずかに、それからじっくりと。影は手を広げるように、肺全体をぼんやりと覆っていた。それが正常な肺でないことは、素人目にも明らかだった。担当した医師は、影の周りを人差し指でなぞりながら、「わかりますか。これが花です。これが肺の活動を邪魔して、それで娘さんは苦しんでいるんですよ」と言った。青色のビニール手袋に包まれた医師の指先には、いくつもの細かな皺が入っていた。診察室にはアルコールの匂いが充満していた。その匂いは、部屋に入ったばかりのときには耐え難いようにも感じたが、次第に慣れていき、話が終わるころには、もうすっかり気にならなくなっていた。私は、そんなことばかりをぼんやりと考えていた。
私は最初、彼が何を言っているのかわからなかった。花という言葉が花という意味に結びつくまでには多くの時間を要した。花という音が何を指し示しているのか私にはわからなかった。私はしばらく沈黙し、それから彼に訊き返した。彼は同じ話を繰り返した。花? と私は言った。そう、花です、と彼は言った。私はふたたび沈黙した。私たちが交わす言葉のあいだを縫うようにして、娘の空咳が、診察室中に断続的に響いていた。
肺の中で花が咲いている。娘の肺の中で、花が咲いている。私はそうした言葉を頭の中で反芻し、うわごとのように口に出した。私は実物の肺を見たことがなかった。肺、と発話されるその音から具体的なイメージを描画するのは難しかった。肺とは脊椎動物が呼吸を行う内臓器官であり、花とは種子植物の生殖器官である。それらの二つの言葉を、具体的な事物として思い浮かべることは、そのころの私にはできなかった。診断結果が出るまでは、肺と花とが距離を置かずに語られるということを、私は想像だにしていなかった。そんなことが事前に想像できる人がいるのだろうか? 私にはわからなかった。何かの冗談だろう、とは誰もが思うところだと思う。
この続きは、「文學界」8月号に全文掲載されています。