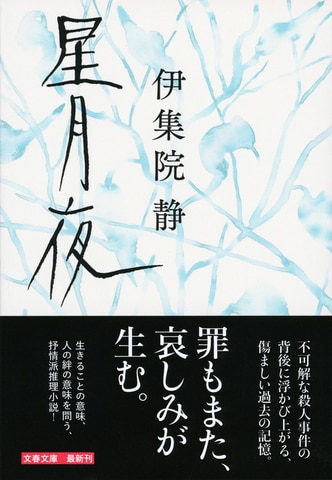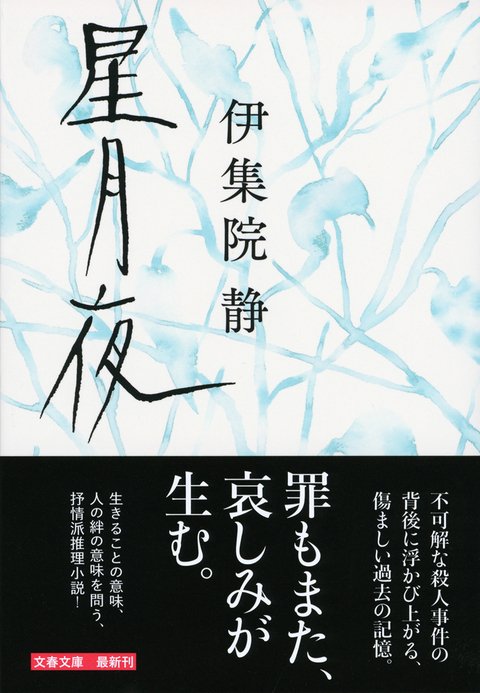東日本大震災から三年たって、『星月夜』が文庫化されることになり、あらためて親本を手にしたら、帯文に「哀しみを抱いて生きる、全てのひとびとへ」とある。そしてゆっくり読み返したら、今回もラストシーンに胸が熱くなった。三年前にも思ったことだが、なんと悲しい結末なのだろう。なんと悲しく、辛く、同時になんと温かいのだろう。
誤解しないでほしいが、『星月夜』にはいっさい大震災の話は出てこない。出てこないけれど、大震災が起きる二ヶ月前に「オール讀物」で連載が開始され、いったん中断して、震災後の混乱のなかで書き続けられた小説である。被災した人たちを目の前にしながら書き続けられた作品には、作者の思いが込められているだろう。「哀しみを抱いて生きる、全てのひとびとへ」とは、まさにそれなのではないか。
それに触れるまえに、物語を紹介しよう。物語はまず、浅草でおこなわれる「行方不明者相談所」の場面からはじまる。
年に一度、一カ月間だけ行方不明者を探す人たちの相談を、警視庁鑑識課の「身元不明相談室」から派遣された職員が担当する。その日は葛西隆司巡査部長と皆川満津夫巡査だった。あらわれたのは、岩手県で農業をしている佐藤康之で、孫娘の可菜子が農業高校を卒業後、美容師をめざして上京したあとしばらくして連絡がなくなったという。可菜子の両親は彼女が六歳のときに山津波で亡くなり、たった一人の身内だった。二人の刑事は何とかして探してやりたい思いにかられる。
そのころ、島根県出雲市の素封家に嫁いだ滝坂由紀子は車で、東部の三刀屋町の実家に向かっていた。実家に出入りする女性の話だと、一人暮らしをしていた八十五歳の祖父の佐田木泰治がいなくなったというのだ。元鍛冶職人である祖父の仕事場をのぞくと、何かを作っていた痕跡があった。
やがて、東京湾で、若い女性と老人の遺体が発見される。佐藤可菜子と佐田木泰治だった。岩手出身の若い女性と島根県の老人の元鍛冶職人に、いったい何があったのか。
捜査にあたるのは捜査一課の畑江正夫警部補と草刈であり、葛西や皆川などの鑑識課の面々である。とくに葛西は、“鑑識課の家具”と呼ばれるほど鑑識の部屋で静かに仕事をしていて、粘り強く証拠にあたり、被害者像や犯人像を推理する。
作者が“新しく、何かに挑もうと決めた。初めての推理小説を書くことにした”(親本の帯文)と作者が語るように、本書はミステリである。殺人者を主人公にした秀作『羊の目』もジャンルわけをするならノワールであり、広義のミステリに入るけれど、作者のいう“推理小説”とは、犯人探しの謎解きのことだろう。実際、物語では、警視庁の鑑識課のメンバーを中心にして、些細な手掛かりを丹念に追いながら事件を追及していく。