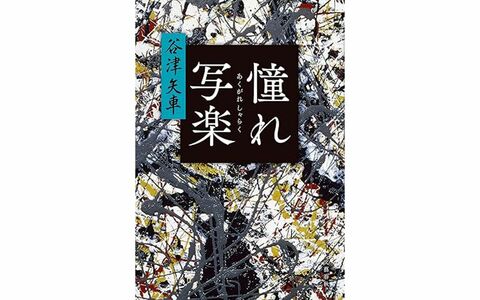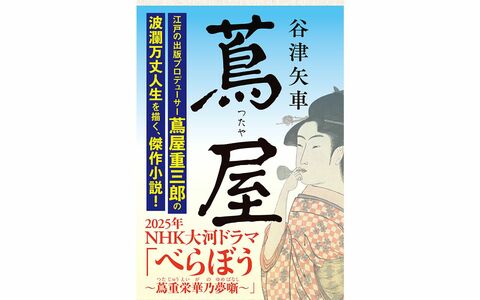佳境を迎えるNHK大河ドラマ「べらぼう」。いよいよ謎の絵師・東洲斎写楽が登場しました。しかし、ドラマ内で描かれた「写楽の正体」をめぐり賛否両論が……。「写楽もの」をこよなく愛し、自らも『憧れ写楽』でその謎に挑んだ谷津矢車さんが、創作と史実の関係について語ります。
◆◆◆
この原稿を書いている今、大河ドラマ「べらぼう」がX(旧Twitter)で賛否両論に晒されている。あ、もしかすると、わたしの周囲だけかもしれないのだけれども、そこは当方の世事の疎さゆえ、お許し願いたい。
なぜこんな騒ぎなのか? わかりきっている。「べらぼう」で東洲斎写楽を巡る物語がスタートしたからである。今回の騒ぎを目にするだに、東洲斎写楽の知名度、カリスマ性はなおも健在なのだなあ、と思わされてしまう。そして、写楽正体もののミステリ『憧れ写楽』を昨年刊行したわたしとしては、してやったり半分、冷や汗半分といったところだ。

東洲斎写楽がこうも耳目を集めるのは、写楽の来歴と、後世での人気の高まりのためだろう。
寛政六年に突如蔦屋重三郎の耕書堂から絵が版行され(実はこれにも諸説あるので一概には言えないのだが)、わずか十ヶ月程度活躍、その後ぱたりと足跡が途絶えてしまう。当時の人々は派手な売り出しをされた新人浮世絵師、くらいの認識であったろう。しかし近代期に入って彼の人物像が忘れ去られるのに反比例するように評価が上がり人気が爆発、海外の学者が「世界三大肖像画家」と評したなどの虚説が流布し(この辺りの事情は高井忍『写楽ブームの正体』(行舟文化)に詳しい)、ついには謎の絵師扱いされるに至った。現代風に言うなら、さしずめ「(文藝春秋の新人賞である)松本清張賞でデビューし、空前のプロモーションで売り出されたのに結局一作だけで作家としてのキャリアを終え、後世、カルト的人気を獲得した作家」みたいなものだろうか。色々差し障りがあるな、この喩え。
歴史小説、ひいては歴史創作の世界では、謎だらけ、正確には、「謎があると見なされている」人物は往々にしてぶっ飛んだ扱いをされるものだ。似た存在に、シェイクスピアや源義経がいる(前者は海外の創作物で別人説がよく取り沙汰され、後者はチンギス=ハンとの同一人物説が盛り上がった時期がある)。どちらも人気があり、年譜に不明なところがある人物だ。東洲斎写楽もそうした一人だろう。
歴史学、あるいは歴史の事実を好む方からすれば、意味不明だろうし、怒りの種だろう。「なぜ、歴史的事実に沿わない物語を作るのだ?」と。実際、今回の『べらぼう』の大騒ぎも、「既に正体がはっきりしているのに、古くからある巷説を引っ張り出してきたこと」に対する批判がかなりの数あった。そう、東洲斎写楽の正体ははっきりしている。斎藤十郎兵衛という能役者だ。歴史創作ならば写楽=斎藤十郎兵衛で書くべきだ、という主張には、それなりの正当性がある。事実、歴史小説内部にすら「史実はできる限り作品に反映するべき」という派が存在する。

しかし、である。物語の受け手としてのわたしは知っている。巷説を援用して描かれた創作物には、そこでしか描けない絵解きと、煌びやかさがあるのだ。
例えば、石ノ森章太郎『死やらく生』(中央公論新社)。写楽の正体をああしたことで、蔦屋重三郎や周囲の文化人たちの怒りが浮かび上がる仕組みになっている。
例えば、泡坂妻夫『写楽百面相』(創元推理文庫)。写楽=斎藤十郎兵衛説を採らない写楽ものだが、当時の江戸の文化人人脈が粒立って立ち現れ、読者を幻惑する。本作を読むと史実がどうかなどどうでもよくなり、泡坂妻夫の作り上げた幻影の江戸に身を沈めていたくなる。
有り体に言えば、書き手としてのわたしはそうした先人の優れた仕事に連なりたい立場である。拙作『憧れ写楽』は、先人への憧れによっても形作られている。
「創作物に史実を反映しているかどうか」は、歴史創作においては無視できない評価ポイントではある。しかし、歴史創作ウォッチャーであるわたしにとっては、作中世界に用意された趣向が我々の魂を揺さぶってくれるのかどうかが一番の関心事である。
なので、わたしとしては、あの説を採った「べらぼう」がいかに我々を唸らせ、面白がらせてくれるのか、わくわくしているところなのである。