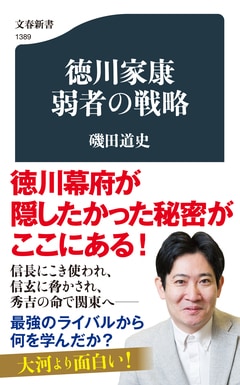蔦屋重三郎は一七五〇年(寛延三)に新吉原(いまの浅草寺裏の千束四丁目)で生まれ、一七九七年(寛政九)に亡くなった版元、つまり出版業者である。本姓は喜多川で、名を珂理と言い、屋号が蔦屋で、店の名を耕書堂と称した。狂歌連での狂名は蔦唐丸である。父は尾張出身の丸山重助、母は江戸の廣瀬津与。数え年七歳の時に母が家を出たという。
重三郎は養子に入ったので、自身の姓は喜多川になった。そして一七七三年(安永二)ごろ、新吉原大門口五十間道に貸本、小売りの本屋を開店した。
なぜ作家ではなく出版業者であるのに、後世にまで名を知られているのかといえば、北川勇助という青年を、世界的に著名な「喜多川歌麿」に育てたからである。また能役者・斎藤十郎兵衛という芝居好きの人物から才能を引き出し、「東洲斎写楽」という浮世絵師にしてしまったからである。サブカルチャーとしての江戸文化を活性化した江戸っ子の代表「山東京伝」を、危険なほどに先鋭化させたからである。その結果として、重三郎自身、「財産半分没収」という処分を受けた。
他にも、蔦屋重三郎の店には黄表紙を作り上げた恋川春町や、パロディの天才大田南畝=四方赤良=蜀山人や、葛飾北斎が出入りし、十返舎一九がアルバイトし、曲亭馬琴が番頭として働いていた。蔦屋耕書堂は、江戸文化を代表する人たちが才能を発揮する「場」だったのだ(図1)。つまり、蔦屋重三郎を語ることは、江戸文化を語ることになる。ここで言っている江戸文化とは、江戸時代前半の上方文化ではなく、後半に開花した「江戸の」文化である。

看板に蔦屋の家紋が見られる。
『画本東都遊』1802 年(享和2)より
蔦屋重三郎は一七九七年に満四七歳で亡くなった。山東京伝のその後の活動や、十返舎一九、曲亭馬琴、葛飾北斎の活躍時代を見ていないが、蒔いた種が芽を出し葉が繁るように、重三郎ゆかりの人々が、その後の江戸文化を支えていった。蔦屋耕書堂は一八六一年(文久元)まで続いたが、その後途絶えて今日に至る。
蔦屋重三郎は生涯、経営者としての版元であるだけでなく、優れた「編集者」であった。編集には、その先への「たくらみ」がある。
たくらみは「企」と書き、つまりは「企画」「目標」「目的」と呼んでも良いわけだが、「企画」は企業のものとされ、「目標」は営業マンのものとされ、「目的」は政治家のものとされる。そのどれもが「カネ」を得るためだ。しかし編集者にカネは降ってこない。カネがかかるだけである。
では蔦屋重三郎の編集は、何をたくらんだのか? 上方から伝わり、江戸で生まれ変わった江戸っ子のための江戸文化を、メインカルチャーとしての上方伝統文化に対峙した、堂々たるサブカルチャーとして作り上げ、守ることだった。
その時「守る」とは、まだ「表現の自由」という言葉を持たない時代における、幕府の「治世完璧主義」から守ることである。つまりは秩序優先、事なかれ主義の権力と対峙することだ。蔦屋重三郎の根の国すなわち生まれ育った場所は、吉原である。吉原は「悪所」と呼ばれた。芝居町もまた、「悪所」であった。悪所に生きる者たちこそ、悪所を守る気概を持っていたのである。悪所には江戸文化が凝縮していた。しかしそれは、権力に立ち向かう「思想」などではない。江戸文学を深く理解していた作家の石川淳の言い方にならえば、そんなふうに思った途端、つるりとすべって小バカまわしにされる。彼らは思想においてではなく、日常生活において「別世」を作ってしまったのだ。
政権や常識に反対表明しつつ対抗言語を掲げること、つまり「声を上げ続けること」は、現代ではとても大事なことだ。そうしないと、別の価値観があり得ることに気づいてもらえないからである。江戸では、どうしたか。編集したのである。境界を定め、地図を作り、集め、結合し、相似したものを見つけ、比喩し象徴し見立て、競わせ、装飾し、強調し、俳諧(諧謔)化し、哄笑し、気がついたら政権の思惑とは全く違う世界が、悪所にはできていた。喜ぶべきことに、浮世絵や本を売る絵草紙屋も「悪所」のひとつになっていた。
そんなことをしないで政権を奪取すれば良いのに、と現代の闘士は思うだろう。実際それをやったのが明治維新である。
明治維新は革命ではない、という人がいるが、当の藩士たちは長年倒したかった幕府を倒したのだから、彼らにとっては革命である。しかしその結果何をしたかというと、幕府の権威への依存を、天皇の権威への依存に入れ替えただけで、前代未聞の天皇制中央集権国家を作り上げ、琉球処分、日清戦争、日露戦争、韓国併合、第一次世界大戦、シベリア出兵、満州事変、日中戦争、太平洋戦争と、立てつづけに戦争と侵略をおこなった。その間に実施した言論・芸術弾圧は江戸幕府の比ではない。こういう革命なら、もうごめんである。
江戸っ子たちも江戸の幕臣や武士たちも、そういうことはしなかった。
雪ふれば炬燵櫓に盾こもりうつて出づべきいきほひはなし
ねてまてどくらせどさらに何事もなきこそ人の果報なりけれ
これは幕臣、大田南畝の狂歌である。皮肉でも韜晦でも負け惜しみでもない。この通り、なのだ。まずは、こたつの中で寝ていられる社会を作ったのは江戸幕府である。それは見事だった。世界では戦争し続けているのに、二五〇年間にわたる「戦争のない国」を作ったのである。偶然ではない。決断して作った。しかしそうするには、国内を強引にでも、まとめねばならない。二七〇以上ある大名家を反発が起きないよう巧みに懐柔し、あらゆる乱を抑え、外国からの援軍要請を断り、幕臣・藩士には学問を身につけさせ、物資の流通を盛んにし、「ものづくり」を盛り上げ、全国の交通網を整え、そして出版と悪所を自己管理させた。つまり、まだ民主主義という言葉も人権という概念もない時代、平和を守るために政治思想を行きわたらせ、「管理」したのである。
平和だが、息苦しい社会だ。特に規則に縛られていた武家社会では、給与の単位である「家」は絶対に守らねばならなかった。家が潰れれば家族および家臣全員が生きていかれなくなる。そこで、基本組織である「家」の内部にはそれぞれの「役割」があった。全体を統括する主人、その妻、隠居した父母、後継たる長男、他家との繋がりに役立つ次男以下および娘、万が一後継がいない時のために子供を産む妾、幼少期の子供の世話をする乳母、そして家臣たちである。
商家もやがて、同じような役割分担をするようになった。子供は今日のように独立した人権がある、とは考えられていなかったので、家に役立つ役割を果たすために生きるべきだった。そこで結婚は政略結婚となり、家が経済的困窮に陥れば、娘は自分を遊廓に売って借金をしたのである。遊廓は家族制度に不可欠だった。「役割」意識と、そこに醸成された「親孝行」の倫理、女性の「自己犠牲」の美意識、その全てが遊廓の経済構造を成り立たせたのである。
遊廓はその経済構造の上に、その息苦しさを解放する別世界として、徐々に濃く深い存在になっていった。無論、顧客にとって、である。そこで、想定外のことが起こった。妓楼や茶屋の経営者たちは、平安時代以来の日本文化を、まるで平安京のような碁盤の目状に作られた吉原遊廓に、再現したのだった。和歌、書、琴、香道、生け花、茶の湯、双六、囲碁、漢詩、俳諧等々。それを担う遊女たちは、公家か、大名の娘たちか、と見まがう品格をそなえた。
平安時代の歌合せの現場は、江戸の市井に移(写)されて狂歌連が無数に生まれた。連歌の場はすでに俳諧の座になっていた。花鳥風月雪月花は浮世絵になった。歌舞伎役者たちは、『平家物語』や『太平記』の登場人物になって舞台を縦横無尽に動き回った。時間空間が自由自在に重ね合わされ、つなぎ合わされるこの江戸時代の文化を、そのような「別世」に演出した主役が、出版業であった。そこに蔦屋重三郎が現れた。
本書ではまず、印刷や出版の歴史を踏まえて、蔦屋重三郎が生まれ育った時代が、江戸時代の中でいかなる時代だったのかを考えてみる。幼少期に心に刻みつけたことが、彼の編集の原動力になっていると思われるからだ。
次に、吉原を本という媒体の中でどう編集したのか、実際の本を使ってその方法を見てみる。蔦屋重三郎の場合、その拠点となっていた吉原の編集にこそ、「たくらみ」すなわち編集意図が現れているからである。
さらに、天明狂歌という、前代未聞の江戸人たちの活動を見ていく。これは、高位の武士、下級武士、大商人、さまざまな町人、職人、役者、浮世絵師、遊女などが「狂名」で参加した文化運動である。その渦の中で成し遂げた蔦屋重三郎の狂歌本の編集は、「狂歌師の編集」でもあった。俳諧がそうであったように、狂歌も個人のみの営みではなく、古代以来の「宴」と「歌合」の型を使った「連」で生み出された。そこには集め、結合し、見立て、競わせ、俳諧(諧謔)化する編集が生きている。狂歌師の編集は連を活性化し、連の活性化は他のジャンルに及んだのである。重三郎は自ら狂歌連の一員になり、狂歌と浮世絵を一体化させた狂歌本を編集した。ここに、幼少期に心に刻みつけたであろう、多色刷り時代の高揚感が見える。
その狂歌師との合わせわざ編集が、高度なプロフェッショナルの浮世絵師・喜多川歌麿を育てた。絵入狂歌本が、当時最高の線を描いた歌麿と、歌麿とともに仕事をした彫師・摺師など職人の居場所となり、そこからやがて、歌麿の美人画が出現したのである。
もう一つの悪所である芝居町でも、やはり大量の芝居浮世絵がつくられ、絵草紙屋から販売されていた。当時の売れっ子浮世絵師は歌川豊国で、芝居は老若男女さらに子供まで人気があったから、豊国を中心に、芝居浮世絵は芝神明前の伊勢屋や和泉屋で大量に売り捌かれていた。そこに蔦屋重三郎はアマチュア絵師・東洲斎写楽の個性をぶつけた。本も浮世絵も編集によって、従来からあって馴染んできたものに異質なものを投げ込み驚きを与えることができた。写楽の役者絵は、馴染んできた豊国の役者絵に対し、その輪郭をカリカチュアライズして強調し、人々が実際は何を見ているのか気づかせた。カリカチュアライズはフェイクではなく、事実への気づきである。しかし前衛はいつまでも前衛ではいられない。驚きは長くは続かない。写楽は短期間で浮世絵の世界を去ったが、そこに示された「視覚は変わり得る」という事実は、江戸文化全体に通じることだったのだ。
本書では、「蔦屋重三郎の編集」とはどういう特徴があったのか、そもそも「編集」とは何か、縦横に語っていきたい。
「はじめに」より