お寿ずの死から1年たって

――本シリーズのひとつ前の作品『こいわすれ』では、麻之助の妻・お寿ずと、生まれたばかりの小さな娘・お咲が亡くなるという衝撃的な事件がありました。読者の方からはどのような反応がありましたか?
畠中 主人公にとても近い人間が亡くなってしまったので、とても驚かれましたね。「えーっ!」という感じで。でも実際に江戸時代は今と比べると死亡率がとても高くて、特に出産時は危険だったんです。それに「まんまこと」シリーズは時間を進めるということを最初に決めていたので、登場人物がずっと同じままでいるということはないようにしたい、と考えていましたから。
――今回の作品はお寿ずが亡くなって1年が過ぎたところから始まります。「朝を覚えず」では、まだ妻を亡くした痛みから充分に回復していない麻之助が時折お寿ずの名を呼ぶ場面があり、それが夢の中のときもあれば、醒めてからのときもあって、とても切ないものがありました。そして麻之助は、ある眠り薬をめぐる騒動を調べるなか、最後に医者に捨て身の啖呵を切ります。麻之助には珍しい、伝法な口調で切られた啖呵が、素晴らしく感動的でした。
畠中 麻之助はこれまでも今もずっとふらふらしていて、そのなかでお寿ずさんの死を引きずっています。そういうとき、町名主としてしなければならないことができたらどうするのか――。「朝を覚えず」はそんなことを考えながら書いた物語です。作中にあるように、お寿ずさんの命が危なくなったときに特効薬があったら、たとえ危ないといわれているものでも、麻之助はどうにかしてその薬を手に入れて、お寿ずさんに呑ませたはず。でも実際にそれはできず、お寿ずさんは死んでしまった。その悔しさと怒りからなのか、結局「危ない薬」を麻之助は自分で呑むことになるのですが……。
――下手をすると麻之助は死んでいたかもしれませんね。危ういところにあえて突っ込んでゆく麻之助の姿にはらはらさせられる、とても魅力的な始まりの物語だと思いました。
「たからづくし」は、本シリーズではとても珍しい、清十郎が意外な形で失恋する物語ですね。
清十郎と吉五郎の意外な女難
畠中 女たらしの清十郎に何か女難が降りかかる――ということは以前から考えていました。町名主の職を継いだ手前、そろそろ縁談をして身を固めなければならないことは、清十郎もわかっていたはずです。親戚達もうるさく迫ってくるし、縁談をまとめれば持参金の1割が手に入るので、仲人達も話を沢山もってきます。健康で適齢期の町名主との縁談なら、持参金はかなりの額になったでしょうからね。
――親類から強く嫁取りを迫られた日に、清十郎は失踪します。麻之助は吉五郎と一緒に清十郎を探そうとしますが、吉五郎はお役目でも忙しく、探索に専念できません。さらに麻之助は両国の貞からも面倒な頼みごとをされて……。ここら辺りから、だんだんと麻之助が忙しくなってきますね。
畠中 立場上、麻之助は忙しくならざるを得ません。お寿ずを失った悲しみから完全に回復はしていませんが、時間が経つにつれ、それは嫌でも薄れてゆくはず。それにいつまでもめそめそしていたら、周りの人間も困りますからね。忙しくしているくらいのほうがいいんですよ。
――清十郎が遺した書き損じの文言を手掛かりに複数の謎が氷解、清十郎の失恋もその全貌がわかります。
畠中 「女性に声もかけられないって、なんなんだ清十郎さん!」と言いたいですね(笑)。これからも清十郎の嫁取りに関しては、いろいろなことが起こると思います。
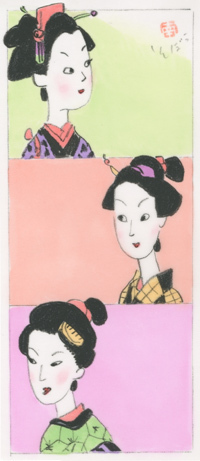
麻之助とおこ乃の「これから」は?
――「きんこんかん」では、清十郎と対照的なカタブツの吉五郎がとつぜんモテ始める物語が描かれます。清十郎がふられる「たからづくし」の直後に読むと、非常に印象深く感じます。
畠中 もちろん吉五郎さんが大モテになるのは裏の事情があるわけですが……。団子屋を開く「おきん」、汁粉屋を開く「お紺」、煎餅屋を開く「お寛」の「きんこんかん」と、貞の手下の「銀次」「権助」「岩太」の「ぎんごんがん」、その言葉の語感とゴロも楽しんでもらいたい物語です。
――「きんこんかん」では、最近ますます亡くなったお寿ずに似てきたおこ乃が、はじめて麻之助のことを意識しますね。 「私、麻之助さんのこと、どう思っているのか、な」と。麻之助もおこ乃をいつもお寿ずに見間違えていますし、このふたりの関係も、これからがとても気になりました。
畠中 私も気になります(笑)。江戸時代は今より夫婦が別れることも死別することも多かったので、当然再婚することも珍しくはなかったはずです。でも仮の話としても、お寿ずそっくりのおこ乃ちゃんが、麻之助の「後添い」でよいのかどうか……。
――難しい問題ですね。2人ともお寿ずのことは意識せざるを得ないでしょうし。
畠中 ネットで「後妻の大変さ」を綴ったサイトを見たことがあったのですが、そこでは「前妻さんの写真をどうするか」から始まって、とても複雑で微妙なことが書かれていました。単純にそれをおこ乃ちゃんと麻之助に当てはめるわけではありませんけど、再婚と後添いの問題は一筋縄ではいきませんね。……本当に2人はどうなるんでしょうか(笑)。でも、おこ乃ちゃんと麻之助のことも含め「別れること」「死ぬこと」「その後をどう生きるか」ということは、このシリーズの大きなテーマです。
――確かにそれは通底するテーマになっていますね。「すこたん」では麻之助がお茶と皿、どちらが大切なのかという馬鹿馬鹿しい裁定をした後、しばらくして同じ相手からあらたな裁定を頼まれます。今度の裁定には「緒すな」という、わがままだけれど持参金が高い女性との縁談のことが絡んでいて、問題が複雑でした。緒すなは疱瘡を患ったことがあり、あばたが少し顔に残っています。
畠中 江戸時代、あばたに悩む女性は相当多かったみたいですね。「疱瘡は器量定め、麻疹は命定め」と言われていましたし。病気から命が助かっても、あばたは顔に残ってしまったケースは多かったと思います。
――物語の結末近く、わがままな緒すなは危機に陥ります。その危機から緒すなを救ったのは、とても意外な人物でした。そしてその後の物語で、その人物と緒すなが縁づくことが暗示されます。
畠中 持参金や家柄とは違うところで縁づいた方が、緒すなさんにはいいんじゃないでしょうか。子供ができたりすれば、おかみさんとして、きっとしっかりした人になると思います。
高利貸しの丸三が求めていたもの
――「ともすぎ」では高利貸しとして恐れられる丸三の不思議な友情譚が描かれます。吉五郎のことを考えて、強面の丸三が見せる意外な側面が、とても新鮮でした。
畠中 丸三のような人間が年齢や立場を越えて純粋な友を得ることの難しさについては、シリーズを書きながらずっと考えていました。もしも丸三と誰かの友情があり得るとしたら――と思いながら、この物語を書きました。
――「ともすぎ」で麻之助と清十郎、そして丸三の3人は吉五郎を探しに、舟で両国橋から市谷御門まで向かいます。しかしいざ市谷御門で降り立つと、そこは延々と塀ばかりが続く武家地で、3人は途方に暮れます。
畠中 実はストーリーに関係なく、武家地のことが気になっていたんです(笑)。以前、幕末の番町あたりの武家地の写真を見たことがあって、強烈に印象に残っていました。武家地は両側に長屋塀がずーっと続いていて、なかなか門に辿り着かない。尾張屋敷なら尾張屋敷の塀が延々と続く――その不思議な光景の印象が残っていて、今回の舞台に使いました。町屋と全く異なる風景なので、その違いが出ているとよいのですが……。
――そしてその武家地で聞かされたことが元で、丸三は災難に遭います。災難にあう直前の丸三の言葉「あたしは吉五郎さんの友達ですからね」には、初めて友を得た喜びのようなものを感じました。
畠中 友を得ることの難しさは、丸三自身がいちばんわかっていたことでしょうからね。「友達」は本当に遣いたかった言葉だと思います。
「とき」が「くすり」になるとき
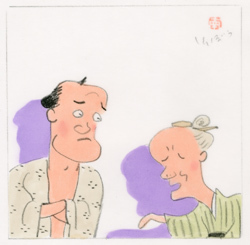
――本巻最後の作品となる「ときぐすり」は、1つの作品としても6つの物語を締めくくる物としても素晴らしく、非常に感動的なものだと思います。そもそも「ときぐすり」という言葉自体が、とても訴えるものがありますね。
畠中 「ときぐすり」は現代ものの小説を読んで知った言葉で、文字通り「時がたつのが薬になる」意味で遣われていました。いい言葉だなあと思って調べてみると、江戸時代に「時薬(じやく)」はあっても、「ときぐすり」という言葉はありませんでした。でも江戸時代にはもちろん「とき」「くすり」どちらもある。作中の滝助のように「時薬(ときぐすり)」と読んで「時がたつのが薬になる」意味で遣われる可能性はあるのではないかと思って、この言葉を題名にしました。
――本作では北国から流れてきた少年・滝助、麻疹で跡取り息子を亡くした袋物師の数吉、糊売りの老婆・むめ婆の不思議な結びつきが描かれます。3人が出会って時が過ぎる中、少しずつお互いがお互いを気に掛ける関係が作られてゆく。その過程が、とても感動的でした。
畠中 滝助・数吉・むめ婆、みんなひとりでしたからね。このままいけば、むめ婆を看取るのは、もしかしたら滝助と数吉のふたりかもしれません。
「その後」を生きる物語
――本作には滝助の来歴をめぐるサスペンスも仕掛けられていて、最後までハラハラさせられました。そしてラストシーンで、麻之助が滝助、数吉、むめ婆の「今まで一人だった三人」を見て、今度は自分にとって何が「ときぐすり」であったのか考えます……妻と娘を失った悲しみからの立ち直りをようやく自覚した麻之助の姿が、本当に感動的でした。
畠中 周囲に人間が「いてくれた」ことを意識できるのは、悲しみからすこし離別することですね。「ときぐすり」の麻之助は、泣き暮らしていた時期とは違う人間になっているのではないでしょうか。
このシリーズは時間を動かすことだけを最初に決めて書き始めたものでしたが、こういう展開になるとは正直自分でも思っていませんでした。物語の中の時間はこれからも進めてゆくつもりですが、麻之助はこれからどうするのか、清十郎の縁談はどうなるのか、吉五郎と義理の父の微妙な関係はどうなるのか、おこ乃ちゃんはどうなるのか、そして彼らは本当に成長するのかどうか、見守って頂けましたら幸いです。このシリーズは、自分の居場所や、自分のやってゆくことも探す物語なのだと思います。読者の方も、物語に触れながら、いつもの生活の中で、気に掛ける人を探したり、暮らしていくことの意味を考えて下さったら嬉しいですね。















