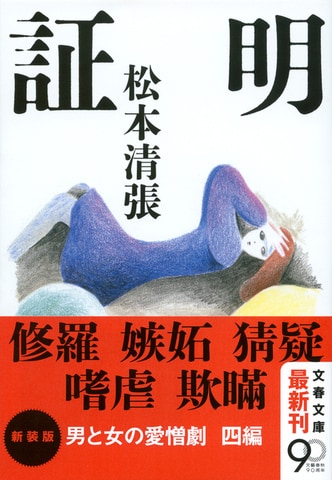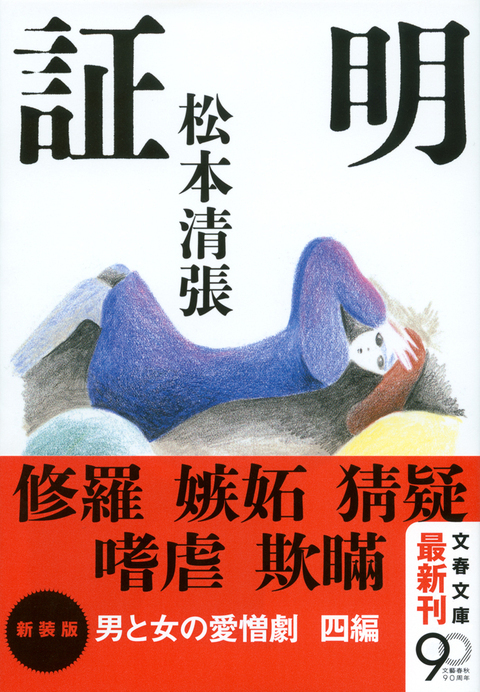考えてもみよう。もともと松本清張は推理小説を書こうとしてスタートしたわけではなかった。初心はちがっていた。デビューのころの作品がそれを表明している。『或る「小倉日記」伝』『菊枕』『火の記憶』『啾々吟』『腹中の敵』、みんな社会や人間の暗部をえぐる普通の小説だ。歴史小説がやや多いようだが、これは当時の大衆小説の書き手にはよくある傾向で、その意味でも普通の小説の書き手であった。ただ謎を見つけ出し“謎を解く”ことには強い好奇心と執念が初めからあったことは疑いない。
そして、その好奇心は……現実の社会に伏在する謎を追究することであり、それとはちがうゲーム性の強いタイプ、すなわち奇っ怪な殺人事件が起き、稀有のトリックを名探偵が解くといったたぐいの謎解きはおそらく嫌いだったろう。
ところが一つの契機として『点と線』を書いたことにより(私はことさらにこれがターニング・ポイントであったと思うのだが)大変な人気を集めてしまった。『点と線』は殺人がありトリックがあり謎解きがあり、紛うことなき探偵小説のパターンを踏んでいる作品だ。同じタイプのものが『眼の壁』『ゼロの焦点』と続くとこれがまたすごい評判だ。
――読者はこういうものを求めているのか――
しばらくはこのパターンを踏襲し、生涯これとつきあうこととなった。ここにおいても松本清張は“絵空事はいやだ。あくまでも小説は社会と人間の真実を描くもの。謎解きのミステリーも犯罪に走る人間の心理と動機を現実的に見すえれば必ず社会と人間の真実を描く文学となる”と信じて、それを実行した。松本清張だけの功績ではないが、ここに従来の探偵小説から推理小説への発展があった、と私は思う。脳みそのゲームとしての犯罪小説ではなく、社会をえぐる犯罪小説へ、と言えばわかりやすいだろうか。江戸川乱歩から松本清張へと言ってもよいだろう。
とはいえ、それが推理小説である以上、トリックや謎解きはやっぱり不可欠だ。多くの読者はそれを望む。そこに松本清張の矛盾があった、と私は考えてしまう。ありていに言えば、松本清張が書きたかったのは社会であり人間であった。それに謎解きをからませることは、大衆を喜ばせる道にはなったが、それは松本清張にとって第一義ではなかっただろう。トリックは充分に巧みであったが、現実性のあるトリックには限界があったし、そこに重きを置くと本末転倒になりかねない。だから私は思うのである。もし松本清張が推理小説に深入りしなかったならば、社会の謎に挑みながら推理小説とは少しちがう堂々たる普通の小説を書いたのではなかったか、と。晩年にはその意欲が見え隠れしていたし、それが天晴れ完成していたら、それこそが代表作になっていただろう、と。