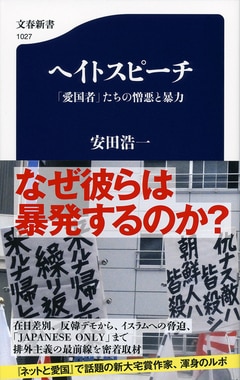二〇一六年に入り、新薬の投与が始まった。待ちに待った投与だった。けれど母は肺炎を起こし、入院。二月初めには一時退院を許されたものの、再び体調が悪化。二月十五日に再入院。そしてその日、早くて一、二週間、もっても一、二カ月という、まったく予想外の余命宣告を聞かされた。「まだ書きかけの作品があるんです。」という私に、主治医は「もう書くのは難しいと思います。」と言った。確かに、私の目から見ても、母は作品を書ける状態ではなかった。意識が朦朧としていたし、言葉も不明瞭になっていた。作品を完成させてあげられない。その現実を受け止めることができなかった。新作に取り掛かったばかりのころ、冗談めかして言った母の言葉が頭をかすめた。
「あんたには全部話してあるんだから。間に合わなかったらあんたが書いてね。」
書けるわけがない。母が十二歳の時に他界した兄のことと、ヒトラー・ユーゲントの話だということは聞いていた。でもそれがどんな風につながるのか見当もつかない。具体的なエピソードや作品への想いも聞いたはずなのに、適当に聞き流していたせいか、詳しくは思い出せない。手の施しようがなくなってからでも、十分な時間があると信じ込んでいたことを悔いた。
そしてその日から三日後、母は息を引き取った。
母の身体を引き取って家に帰ると、母の書斎の机には、プリントアウトされた新作の原稿が積まれていた。ところどころに赤が入っている。目を通さなくてはと思いつつ、母の友人たちが部屋の片付けを始めてくれていたので、そのどさくさで見失わないように、箱に入れて書庫の奥にしまい込んだ。葬儀の準備をしながらも、作品のことが気にかかっていた。母が最期に書いた作品をなんとか世に出したい。でも、まだ完成していない状態のものを人目にさらして母は喜ぶだろうか。古くから知っている編集者にも意見を聞いた。その人はその場で深く考え込み、慎重に案を出してくれた。たとえば、いつか全集が出るときに付録として発表する。あるいは電子書籍の形で無料配布する。それならば、未完の作品でも母の名前を傷つけずに発表できるだろう。確かにそれは最善の方法だと思えた。でも、それで本当にいいのかわからない。いつまでもぐずぐず悩み続けていた。