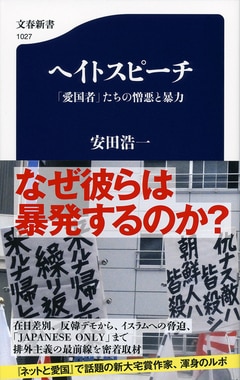「残された原稿を読ませてほしい」と、文藝春秋の担当者の方から連絡をいただいたのは、葬儀も済んで一息ついた頃だったと思う。二月初めに一時退院したときに、作品はほとんど完成していると、母がメールを書き送っていたという。ほとんど、といってもどの程度なのかわからない。とにかく読んでみると約束して電話を切った。
書庫にしまい込んだ原稿を取り出して確認すると、途中までしか打ち出していない章があるようだったので、まずはパソコンに残されたデータを探して、一通り原稿を印刷し直した。データの最終更新履歴は二月十一日。息を引き取る一週間前だった。三九度を超える熱を薬で押さえながら、一日のほとんどをベッドで過ごしていた頃だ。集中して執筆できたはずがない。それでも、作品を読み返し、手を加えようとしていたのだろうか。私がひとりで看病することに限界を感じ、介護の申し込みなどで走り回っている間にも、母はひとりこつこつと作品に向かっていた。母にとって、言葉を発し、求め続けることは、生きることそのものだったに違いない。
私は夢中で作品を読んだ。読み進めるうちに母が話していたことが次々とよみがえる。ダウン症だった兄との思い出。大家族の空気。人々の視線。記憶をたどる手触り。こうしてひとつの作品に編み上げられて、初めてその意味が理解できる。
それは、出会ったことのない差別の話だった。
描かれているのは、差別とはなにか、いや、人間とはなにかという問いだ。どうしたら差別を乗り越えられるかと言っているだけで差別をわかったつもりになっていた。目をそらしてきた心のなかを突きつけられて、人間の複雑さを思い知らされた。この作品をいま、差別のなかで生きる人々に届けなくてはいけない。そう思い決めて、私は担当者の方に原稿を渡した。幸いなことに、作品を読んだ出版社の方々も、これはひとつの完成した作品であるとして、最善の方法で刊行できるよう考えてくださった。
こうして、「狩りの時代」が津島佑子の最後の作品として刊行されることに決まった。
いつも慎重に推敲を重ねる人だったから、おそらくまだまだ手を入れるつもりだっただろう。これを完成と言ったら不本意かもしれない。でもきっと、母はこの刊行を喜んでくれていると思う。いま、この時代に、母が聞き届けようとした声を形にできて、私も胸をなでおろしている。刊行のためにご尽力いただいた方々に心から感謝し、津島佑子の言葉がひとりでも多くの方に届くことを願ってやまない。