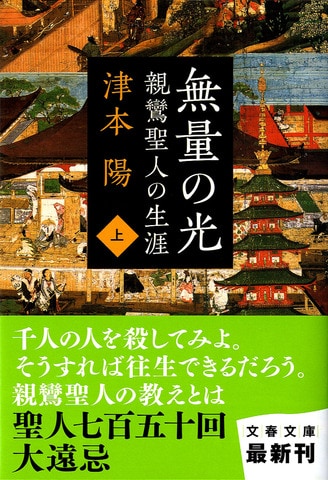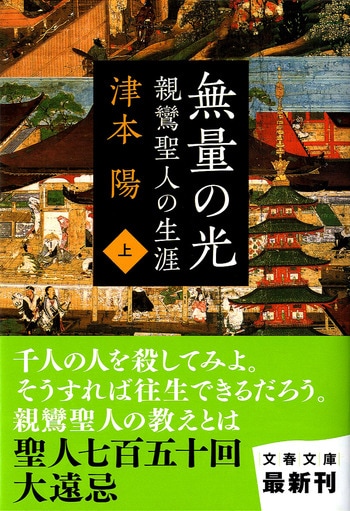──津本陽さんの新刊『無量の光――親鸞聖人の生涯』は親鸞の一生とその教えを描いた書き下ろし長篇小説です。津本さんにとって書き下ろしは久し振りなのではないでしょうか。
津本 いえ、久々どころか本当に初めてのことなんです。五年前に着手してようやく完成しました。
──しかも原稿用紙約千枚の大作です。ご苦労も多かったのではないでしょうか。
津本 私は先に親鸞聖人伝を二〇〇〇年から〇一年にかけて新聞連載して、『弥陀(みだ)の橋は――親鸞聖人伝』(文春文庫)というタイトルで出しているのですが、聖人を描く、もう一度書くというのは大変なことでした。途中でやめようと思ったことさえありました。浄土真宗の門徒の家に生まれた私ですが、聖人を描くのはつくづく難しいと感じますね。
──今回上梓(じょうし)された『無量の光』は親鸞の教えに重きを置かれています。『弥陀の橋は』でその生涯を描かれたのとは趣きが異なりますね。
津本 ある大学教授が、親鸞聖人の主著『教行信証』の教えを小説でここまで読み解いて描くのかと驚いて下さった。
──教えに重点を据えられたのは、やはり津本さんご自身が浄土真宗の門徒だからでしょうか。
津本 私の先祖は、祖父母、両親までは熱心な門徒で毎朝毎晩、念仏を称(とな)えていました。
私が子どものころは、お客僧という僧侶が毎月家に来て下さいましたね。それに家で説教もするのですが、玄関に雑賀(さいか)講と書かれた大きな提灯(ちょうちん)を下げて、部屋をつなげると百五十人くらい入れるんですが、仏間には演壇もつくってやっていました。女性は普段着ですが、男は柿色のそろいの裃(かみしも)を着ていましたね。で、翌日はお寺に行くんです。子どもだった私は手を引かれて一緒に行っていました。そういう特別のときでなくても、おばあさんによくお寺に連れて行かれて。ですから、幼稚園ぐらいまでは正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)を暗誦していました。その後は忘れてしまいましたけれど。
それからずっと経って昭和四十九年に母が亡くなるんですが、本当に悲しかったですね。その時、正信念仏偈を称えてみたら、その間は母と話が通じているような気がするんですよ。それでときどき仏前に座って称えていました。私の胸中には、やはり祖母に教えられた浄土信仰があったのです。
もともと私は小説家として暮らしていくとは夢にも思っていなかったんです。それで、作家として、何を書き続けてきたかというと、人生の虚しさ、無常観といったものを書き表わしてきたんです。無常観が小説の根っこの部分にあります。子どものころに仏教で刷り込まれたものがあるんでしょう。
──そういう下地があるからなのですね。『無量の光』を読むと親鸞聖人の難しい教えがすっとからだの中に入ってくるような気がします。
津本 私は一般向きでない小説家ですが、人生で二回も親鸞聖人のことを小説に書くことになりました。これは何か私に「書け」という思(おぼ)し召しがあったのかなと思いますね。いま八十歳ですが、書き始めた頃は完成するのは八十歳を超えるだろうと思っていました。それまで生きているだろうかということも考えましたよ。もし生きていたら親鸞聖人の七百五十回大遠忌(おんき)(二〇一二年)にお参りに行こうとは思っていましたが。
『弥陀の橋は』を書いて数年、今度『無量の光』を書くにあたって『教行信証』を何度も読んで、あ、こういうことだったのか、とあらためてつかめてくるところがありました。
──『弥陀の橋は』から『無量の光』まで七~八年空いていますが、その間、日本の置かれた状況も随分変わってきました。そういう、時代の背景の影響というのも小説には現われてきているのでしょうか。
津本 それはもちろんありますね。この七年間でものすごく社会が変わってしまいました。毎年三万人もの人が自殺するような日本の国を背景にこの小説を書いてきたわけです。
──もし親鸞聖人がいらしたら、現代の我々を救ってくださるのでしょうか。
津本 まあ、癒してくれるのでしょうね。親鸞聖人が生きた十二~十三世紀というのは社会政策など何もできない時代でした。農民などは年貢を毟(むし)り取られ、牛馬のように働かされて死んでいくような状況です。いまの日雇い派遣社員の待遇と共通するところがあるかもしれませんね。
親鸞聖人はそういう人たちの魂の救済をされたんです。物質的な救済はできませんから、念仏を称えることによって極楽浄土に往生できると教える。それも最初「南無阿弥陀仏」と十回称えるといっていたのを、流行病で十回も称えられずに死んでいく人もいて、それが一回でいいということになっていきます。必死で救おうとしたんですね。
──歴史的に見て、いまも大変ですけれど、当時はさらにひどい時代だったのですね。
津本 戦乱が起き、飢饉(ききん)が発生し、子どもがばたばた死んでいますから、平均寿命も二十代だったのではないでしょうか。そういう時代、苦しむ人々に心の安定を与えようとしたんですね。その拠って立つところとして、お経を研究しました。お経はパーリー語で誕生し、インド、チベット、中国を経て日本にやってきました。親鸞聖人は訳に訳を重ねて釈迦の法理を突き詰めていったのです。
──一二〇七年に後鳥羽上皇による専修念仏の停止(ちょうじ)があり親鸞は流罪で越後に配流されます。一二一一年に許され入洛の許可が下りますが、京都に行かず、その後東国に布教に行き、その地の門徒は一万人に及びます。
津本 東国での布教は成功します。そのままいれば生活が安泰だったのに、わざわざ六十歳を超えてから京都に戻って、経の研究に没頭します。当時の一万人ですから、ものすごい数です。やろうと思ったらなんでもできたでしょう。でも、それを振り切っています。
京都では地所はなく、家を持たず、お寺に住まわせてもらって、自分のそばにいるのは末娘の覚信尼と甥の二人だけ。東国からの寄付などで食いつないでいます。でもそれもだんだん減っていきます。ですから、「私は何の力も無い。私が死んだら二人が何とか食べていけるだけの援助をしてやってくれ」と死ぬ前に東国の門徒に手紙を書いているくらいです。
飢饉とかがきたらとたんに飢えかねない状態だったでしょう。そういう状況で著述を続けています。高齢で、眼鏡もない時代にですよ。享年九十ですから、目も悪く歯もほとんどないからだで庶民を救うために研究をしていたわけです。
本当に仏のような人ですね。親鸞聖人の一生はまさに相次ぐ苦難の連続です。一年として平穏な年はなかったでしょうし、なんにも面白いこともなかった生涯でしょう。聖人は現世の苦労はあって当たり前だと、もしここで命が尽きたら、あの世にいってまた現世に仏として戻ってきて人を助ける、と。生きる目的が初めから私たちとは違いますね。あまり物質に振り回されない、抜け出ているというのでしょうか。それでいて楽天家です。くよくよしない人ですね。
──書き終えられて、親鸞のイメージは変わられましたか。
津本 変わりはしません。親鸞聖人がいかに最後まで真実を求めつづけた強靭な思想家であったかということは実感しました。
私は雑念の多い人間ですが、この小説を書いているときには驚くほど没頭、集中できたんです。なんだか自分の力だけではないように感じました。
──小説をいつも書いておられるときと、集中の仕方が違っておられたわけですね。
津本 この馬鹿に小説を書かせてやろうということでしょうね。何か力があったように思います。
私は親鸞聖人が入滅された年齢に近づいてきました。だけど聖人は今の私の歳からさらに十年、研究、執筆を続けています。驚くべきことです。
──仏教に詳しいご門徒の方が読むための小説かと思ったのですが、そうではないですね。日頃、仏教と無縁の私も興味深く読ませていただきました。
津本 現代に生きづらさを感じている方にも読んでいただけたら嬉しいですね。