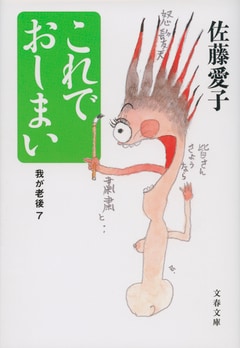老作家・藤田杉のもとにある日届いた訃報。それは青春の日々をともに過ごし、15年の間は夫であった男のものであった。杉は遠い記憶の中にあらためて男の姿を探し始めた……。『戦いすんで日が暮れて』から45年、佐藤家の凄まじい生を描いた『血脈』から14年、あらたな傑作長編小説『晩鐘』を上梓した佐藤愛子さん。瑞々しい青春時代から老境の寂寥まで「人生のすべてを懸けて描いた」その背景を伺います。

――本作にはこれまでもさまざまな形で佐藤さんの小説やエッセイに登場する「かつて夫であった男(作中では『畑中辰彦』)」のことが書かれています。あらためて彼のことを書こうと思ったのはなぜだったのでしょうか。
「辰彦」について書くことは、時期はともかく、ずっと考えていました。作中にもあるように、尊敬も信頼もしていましたが、ずいぶんと苦しめられもしました。実際に彼が亡くなって数年が経ちますが、やはり考えても「わからない」ことばかりなんです。書くことによって何かがわかるのではないかと、漠然と考えておりました。
――実際に作品を書き始められたのは3年前ですね。
そうです。88歳のある時、尊敬する古神道家の相曽誠治氏から「佐藤さんは90まで生きます」と言われたことを突然思い出し、計算してみるとあと2年しかないことに気づいて……。そこから「こうしちゃいられない!」と、とにもかくにも書き始めました。何に対して「こうしちゃいられない」のか、よくはわかりませんでしたが(笑)。
――本作は「梅津玄へ藤田杉の手紙」という書簡形式の一人称で書かれるところと、三人称で書かれるところがあります。この構成は最初から決めていたのですか?
いえ、この形式を思いつくまでは、とても苦労しました。自分(佐藤愛子)でもある「杉」の行動や心情を地の文だけで説明するのはどうしてもくどくなって、小説が必要以上に重いものになってしまう。手紙形式ならば余計な説明はいらないし、杉の友人・田代雪枝のような客観的・批判的な視点を入れることもできる。
ずいぶん書き直しはしましたが、形式が決まってからの苦労はありませんでした。作品の中での時間の往来も自由になって「作品を書く」というより、「作品の中を生きる」という感じになりました。

――本作では辰彦と杉、そして共に文学を志した仲間たちとの瑞々しい青春時代、金銭問題に苦労する怒涛の壮年時代、ひとりきりになってしまった杉の老境の寂寥が、時間を往来しながらさまざまに描かれています。
青春時代から老境の寂寥までを書くためには、実際の90年の歳月が必要でしたね。若いころには書けなかったことを、この『晩鐘』の中では書いていると思います。
――本作であらためて描かれる辰彦の姿には、やはり独特の凄まじさを感じました。金銭的なことに苦しみ、人にも多大な迷惑をかけているのに、本人はあまり悪びれもせず、それどころか「よりにもよって」の出来事や人間関係から最後まで離れることがない……。
この小説はその辰彦のことをわかろう、理解しようと思って書き始めましたが、書いているうち、理解しようとすることや意味づけに「意味がない」ことがわかってきました。そもそも人をほんとうに「理解する」ことなんて、できることではありません。辰彦がかく考え、行動したのは「彼がそのような人間だったから」。辰彦以外の登場人物もそうで、皆かく生き、かく懸命に生きたということだけでしかない……それが今回「わかった」ことですね。
だから今は、これまでの怒りや批評的な考えが随分と治まってしまって、なんでも「そういうものだ」と肯定する、全体的な愛の境地にいる気分なんです(笑)。
――「およそ人間ほど高く育つものはない。深く滅びるものもない」というヘルダーリンの言葉を辰彦は口癖にしています。辰彦とこの言葉の距離の変化も、この作品の読みどころになっていると思います。
昔からよくその言葉は言ったり書いたりしていました(笑)。辰彦は本当にヘンな人でしたが、そのヘンな人にずっとつきあう杉も相当にヘンな女。そのことも今回「わかった」ことですね(笑)。