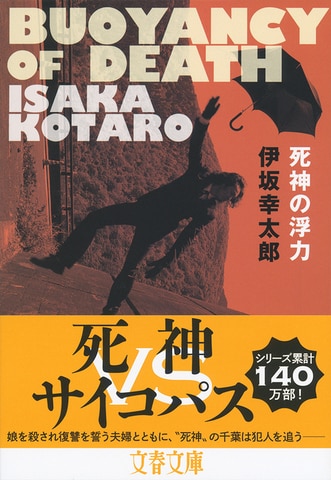
- 2016.07.10
- 書評
笑いを誘う一方、怖さも感じさせる“死神”を登場させた伊坂幸太郎の技
円堂 都司昭 (文芸・音楽評論家)
『死神の浮力』 (伊坂幸太郎 著)
出典 : #文春文庫
ジャンル :
#エンタメ・ミステリ
こちらもおすすめ
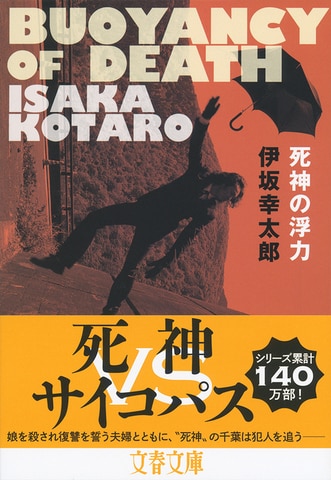
『死神の浮力』 (伊坂幸太郎 著)
出典 : #文春文庫
ジャンル :
#エンタメ・ミステリ