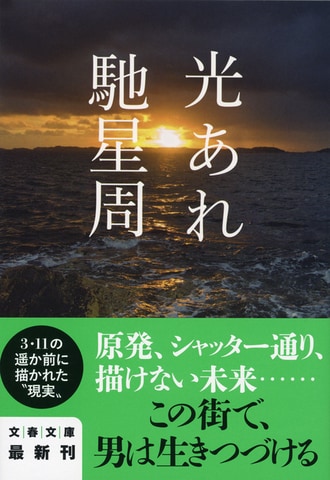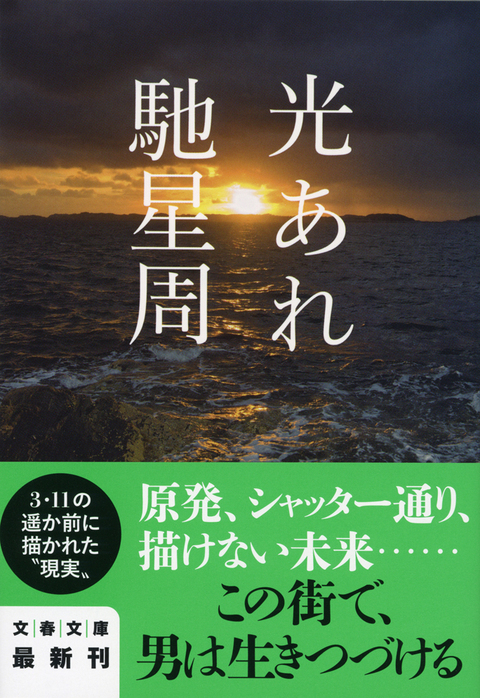最近、三十代から四十代の初めぐらいの人たちと仕事をする機会が増えた。彼らは概ね優秀で如才なく、仕事が滞ることもない。かなり年上の私から見ても仕事ぶりは堂々としている。もちろん、若さによる無知や経験不足で、多少のミスがあったとしても、私が若い時のように、ただただ混乱して自滅する、なんて無様なことにはならない。
だから仕事の時は何の不満もないのだが、一緒に食事や酒を飲み、話を聞いていると、ずいぶん爺むさいなあ、と感じてしまう。
思い描いた人生の路線から外れることなど想像もしていない。出身地から大学受験で東京へ出て、そのまま就職している人でも、とくに大きなことを考えているわけではないようだ。地元に残る家族や友だちが大好きで、過去の自分に誇りを持っている。昔語りをしたがる若者に、ときどき辟易するのだ。
昭和の高度成長期に生まれ、右肩上がりの経済とともに、日本はずっとよくなっていくと信じ込んでいた世代の私が「もっと外に打って出たらいいのに」というと、僕らはバブルを知りませんから、と答える。今が一番いい時だ、と子どもの頃から信じているから、無理に背伸びはしないんです。と言われると、返す言葉もない。
『光あれ』の主人公、相原徹もバブルを知らない世代である。五作の短編連作は、徹の半生の一シーンをそれぞれ切り取ったものだ。一作目の『事故』は現在の四十歳間近。それから二十五年ほど遡り『チェルノブイリ』は中学時代、『ふっかつのじゅもん』は高校生、『花かえ』は高校卒業後の就職時、そして最後の『光あれ』でまた現在に戻ってくる。少年から青年、そして中年に足がかかるくらいの歳月が描かれている。
私が都会で一緒に仕事をしている連中と違うのは、生まれてこの方、地元の敦賀を一足たりとも出たことがない、ということだ。親の後を継ぐような家柄でもなく、その土地に縛り付けられる理由などないのに、なぜか故郷を離れない。怖いのか、気力がないのか、最初から選択肢に入っていないのか。経済的にも疲弊した地方都市にへばりつくように、職を転々としながら生きていく男。