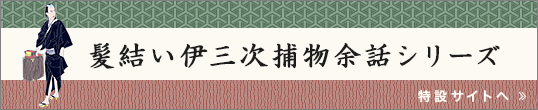「宇江佐真理さん、いいよね」という声を複数の編集者から聞くようになったのは15年ほど前、宇江佐さんがデビューして間もない頃だと思います。当時、絵のやり取りは手渡しが基本でしたから、時間があると彼らと長々と無駄話をするのが通例でした。そんな流れの中で、ふと、真顔で「宇江佐さん、いいよね」という彼らの声を聞くようになっていました。
挿絵の仕事はその頃、現代物が多かったのですが、徐々に増え始めた時代物の中に宇江佐作品もあり、「宇江佐さん、いいよね」と言われたとき、ぼくはすぐに賛同しました。と同時に、宇江佐真理という作家は一体何者だろうと思いました。というのは彼らの言葉には、時代小説にとうとう大型新人が登場したという、歓迎の意味も含まれていたのにも拘わらず、彼女の個人情報が十分にぼくには伝わっていなかったからです。宇江佐作品が注目を集め始めたのは、池波さんや藤沢さんがお亡くなりになって、大きな穴がぽっかり空いた時期と重なっていました。
その後、彼女が生まれ育った函館で主婦のかたわら作家活動をしている、ぼくより少し歳上の二児の母だということ、そして宇江佐真理という美しい名前がペンネームだということが分かりました。
やがて、宇江佐作品にじっくり向き合う機会が訪れます。短編集『深川恋物語』(1999年刊)の装画を依頼されたからです。この本はタイトルのとおり、江戸深川あたりの男女の恋にまつわる物語です。読み進めると、ぼくは参ってしまいました。あろうことか、途中で涙が止まらなくなってしまったのです。
宇江佐作品の魅力は時代小説がフィクション性の高いものであるにも拘わらず、細部に妙に生々しいリアリティがあるところです。世評は彼女を江戸情緒を巧みに描く新進作家と表現しました。この『深川恋物語』でも職人の動作を見てきたように書き、働く女の仕草を戦前の時代劇でも観ているように描写します。また、深川の町を俯瞰する目はまるで自分が住んでいるようです。
その中にこんなくだりがありました。橋から堀割をのぞき込んで子供達が騒いでいます。何だろうと近寄って一緒に下をのぞくと、クラゲがぷかぷか浮かんでいるのが見えます。
「これは函館だ」と直感しました。残暑の中、海水が混じり合う港町の川の情景を、宇江佐さんは記憶からたぐり寄せたのではと思ったのです。あるいは、日常の一こまを描写しただけかもしれません。そう考えると、宇江佐文学の持つ妙に生々しいリアリティのもとが分かるような気がしました。彼女は深川を描いているのではなく、昭和の函館を江戸の枠組みを借りて愛情深く描いているのに違いないと。
宇江佐さんはずっと函館にいました。少女時代の夢も青春時代の恋も失恋も、すべて函館の町が知っています。彼女はこの町を長い間彷徨いながら、あるいは経験と空想のあいだを彷徨いながら喜びや悲しみ、焦燥や孤独を抱きかかえて「書かずに、死ねるものか」と何度も思ったに違いありません。ですから、彼女の初期作品は所々に私小説のにおいがしたのです。