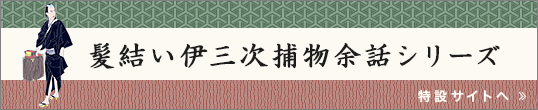とはいえ、時代小説は現実にはありえない娯楽性を楽しむジャンルですから、その点はぬかりなく宇江佐さんは仕掛けを用意します。デビュー作の『幻の声』はこの「髪結い伊三次」シリーズの1作目で、脛に傷持つ廻り髪結いの伊三次と深川一の売れっ子芸者お文を登場させます。彼女は誰もが冒頭から中村勘三郎あたりが演じる『髪結新三』を思い描くのを織り込んでいます。つまり1作目から、派手な手を使っているのです。
実はぼくは、宇江佐さんが上京したおり、歌舞伎座で中村屋さんの『髪結新三』を一緒に観たことがあり、彼女の江戸文化に対する「あこがれ」を目の当たりにしました。そして、その正体が昭和のころ日本中に溢れていた東京に対する「あこがれ」だと、ぼくも北国秋田出身なので、すぐに伝わりました。ですから、1作目が「あこがれ」の江戸文化の象徴である歌舞伎に題材をもとめたのは当然の成り行きだったはずです。
今では信じられないでしょうが、あの当時(昭和30年~40年)の田舎の青少年は、空想の中で「あこがれ」の地「東京」で幸せを探す旅を始めたとき、魂は解放され自由になっていったのです。ただ、多くは郷里を捨て、東京へ出てくるうちにそれは淡い初恋のように記憶の彼方に消えていきます。
しかし宇江佐さんは「あこがれ」をずっと持ち続けていたのです。何故ならこのシリーズに出てくる女たちは、幸せをずっと探し続けているからです。もちろん幸せはシャボン玉のように捕まえようとすると逃げ、触るとすぐ壊れるのは半ば承知です。それでも、追いかけます。そして、シャボン玉が浮んで消えるまでをじっと描写し、シリーズのスタイルとしていきました。
『君を乗せる舟』『雨を見たか』『今日を刻む時計』『心に吹く風』。これはシリーズのタイトルですが、どれも時代小説とは思えません。ニューミュージックの、いやその前のフォークソングのアルバムタイトルのようです。これも、彼女の「あこがれ」の強さを表す証拠ではないかと思っています。
ところが、伊三次とお文の恋の成就から、このシリーズは大きく変わります。
結婚は色恋よりよほど苦労の種です。子供が産まれ家族がふえ、我が身の心配は後回しです。表現の特徴である妙に生々しいリアリティには娘の視点に、親の視点が加わっていきます。この頃の彼女の作品には主人公が苦悩する若者のはずなのに、いつの間にか息子を心配する母親の独白のような一編もあり、思わず笑ってしまった記憶があります。彼女の小説は常に日常を反映しているのです。
そして、最近の作品には季節の記述、とくに花の記憶が登場します。この本でも章タイトルの半分は花にちなんでいます。花は美しさと儚さの象徴です。確かなものなど何もないこの世の中で、季節の中に一瞬でも咲く花の美しさを大事に記憶にとどめることが、この世に身を置く証しだと言わんばかりです。これが今度の本のタイトル『明日のことは知らず』の意味するところで、作家「宇江佐真理」の成熟の始まりとぼくは読みました。
最後に、いま時代小説ブームと呼ばれ新しい作家が次々に登場していますが、市井物においては宇江佐真理がその扉を最初に開き、多くの作家に影響を与えてきたのをぼくは目撃してきました。