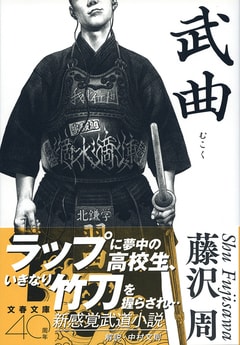書評という体であるにもかかわらず、主観に寄って申し訳ないが著者である中村文則は僕と同じ1977年の生まれだそうだ。
それで腑に落ちた。
この小説を読んだ時、同じ時代を生きた者特有の感覚を妙に生々しく感じたからだ。
これまでの読書の中で、ひと昔ふた昔前の実際の事件がモチーフとして取り上げられたり考察されたりしてきた。
例えば、津山30人殺し事件であったり、若者による一連の左翼運動であったり、そういった僕が生まれる前の事件を、小説を通じて追体験してきた。
『私の消滅』では、あの幼女連続殺人事件の宮崎勤について言及される。
これは「歴史」ではなく、リアルタイムで知っている「事件」だ。
しかも書かれるのは事件そのものに加え、宮崎勤が取調べや公判で供述し、気味の悪いスケッチとしても残されている空想のキャラクター、「ネズミ人間」に関して。
宮崎勤のネズミ人間は、あの事件をリアルタイムで知っている者なら頭の隅にずっと引っかかってた興味ではないだろうか。
かくいう僕も忘れられない奇怪な物として頭の隅どころか中心にあったように思う。
『私の消滅』からは宮崎勤の理解しがたい事件とネズミ人間の意味不明さに、一つの答えを見出そうという不気味な熱意を感じる事が出来る。
宮崎勤の弁護を中村文則が務めたなら、判決に何らかの影響があったんじゃないかとさえ思った。
同じ世代の人間が感じていた、体温を持った「不可解」に真っ向から潜って行ける本がこれから増えていく予兆を感じ、僕も薄気味悪い期待に胸が高鳴った。
加えて『私の消滅』には、罪を犯した人間が受けるべき最も理想的な罰の形が提示されている。
それを自分の頭の中で反芻するたび、行き場を失った悪意のエネルギーがどうしようもなく頭の中をグルグル回る。