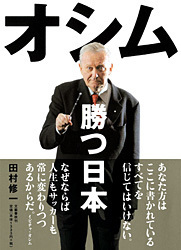二月のサラエボは、街なかに雪こそ降り積もってはいたものの、思ったよりずっと暖かだった。
「こっちは毎日雪が降っているのよ」
日本を発つ数日前の電話で、「東京は寒波がぶり返して今は寒いです」と伝えたとき、アシマ・オシム夫人がこう答えたので、万全な防寒態勢で出かけると、意外にも東京よりも穏やかな、春を感じさせる暖かさだった。
昨年十二月に来日した後、オシム夫妻は自宅のあるグラーツ(オーストリア)ではなく、息子アマルと娘イルマが住むサラエボに戻った。現在、イルマとともに暮らす家には、一日おきにフィジオセラピストが、リハビリのトレーニングに訪れている。
「このまま(リハビリを)続ければ、車を運転できるようになる。そうなれば行動範囲もずっと広がる。監督の仕事も、またできるようになる」
二か月ぶりに再会したオシムは、溌剌(はつらつ)としていた。
Number誌の最初のインタビューは一年半前、一昨年秋のグラーツではじまった。場所は、近隣諸国はもとより、遠く南アフリカからも患者が訪れるという、グラーツ郊外のリハビリセンター。そこでトレーニングに励むオシムは、ダイエットで体重を落としたため頬はこけ、手足の動きは緩慢だが、ときおり浮かべる眼光鋭い眼差しは、われわれのよく知るオシムそのものだった。
リハビリセンターのロビーで、隣の教会のレストランやカフェで、われわれは話し込み、シュトルム(収穫したてのブドウを絞ったアルコール飲料)を飲んだ。シュトルムを炭酸水で薄めながら、オシムは饒舌(じょうぜつ)だった。
二度目は雪の舞う冬のグラーツ。その後も春のグラーツ、夏のサラエボ、秋のサラエボ、冬の東京と、季節が巡りながらインタビューは続いた。
最初はこちらにも遠慮があった。一時間から一時間半の話が二~三度聞けて、一緒に食事もできればそれでいいかと。だからアシマ夫人にも、駄目でもともとと思いながらそうリクエストを伝えた。
「そんなに?」と驚きながら、夫妻は誠実に対応してくれた。オシムの話しぶりは、日本でもお馴染みの皮肉とユーモアに富んだオシム節というよりも、真摯(しんし)で情熱に溢(あふ)れていた。そしていつまでも尽きることがなかった。以降、長時間のインタビューが、オシムとの暗黙の約束になっていく。