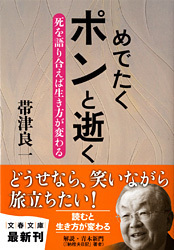──文春文庫から『めでたくポンと逝く――死を語り合えば生き方が変わる』が刊行されました。「文藝春秋SPECIAL」の連載対談「死を想う」でホスト役を務めるなど、ここ数年「死」について積極的に語られていますが、その決定版といえる内容です。どんなきっかけで、死について執筆されるようになったのでしょうか。
帯津 『納棺夫日記』(文春文庫)の著者である青木新門さんと出会ったことが一つの転機でした。十五年ほど前、私が講演で死について話したところ、しばらくしてその講演を聴いた新潟の方から手紙が届きました。そして「私の友人に青木新門という作家がいて、帯津さんと考え方が似ている」とあり、『納棺夫日記』が同封されていたのです。当然ですが映画「おくりびと」で有名になる前のこと。「納棺夫」という言葉も知りません。ところがこれを一気に読み、青木さんに会いたいと思ったのです。死を介して人の生というものを見事にとらえた本でした。私は、ガン専門医として働いてきましたが、医療の現場では死から目を背けず、視野の中に死を入れておくことが大事だと思うようになっていた頃でした。そこにこの本が送られてきたのです。
この本に刺激を受け、それから数年間かかって初めて自分で死の話をまとめてみようと思ったのが、今回の『めでたくポンと逝く』の元となった単行本(『いのちの勉強』)です。青木さんには、今回の文庫の解説を執筆していただきました。
──本書で特に印象に残ったのは、帯津先生が感銘を受けたという、死と向き合う態度が素晴らしかった患者たちの姿です。
帯津 患者さんから学ぶことは多いですね。私の太極拳の師匠だった楊名時先生など、入院するや「私は死んでも本望ですから。今死んでもいいんですよ。あまり心配しないで下さい」という。これには驚きました。体調が悪くなれば愚痴のひとつも出るものですが、楊先生はその後も一切言わない。いつでも死ねる生き方をしてきたのです。最期まで、あるがままを通して二〇〇五年に亡くなりました。
楊先生は、まさに「生と死」を統合させたケースだと思います。生と死を切り離さなかった。生きながら死を考えることで、自分はどんな人生を送り、終えたいかが見えていた。この「生と死」の統合は、私の取り組んでいるホリスティック医学(心、体、生命の三つを一体として治療する医学)の究極だと思っています。 「生と死」が統合できていれば、死の恐怖なんて全くない楽な状態になる。ただ、それは実際には難しいことです。無理にこの世で果たそうと、悲壮な決意で毎日過ごしていたのでは元も子もありません(笑)。ですから、私などは「生きているうちが無理なら、まあ死んでからでもいいか」というくらいの気持ちでいます。