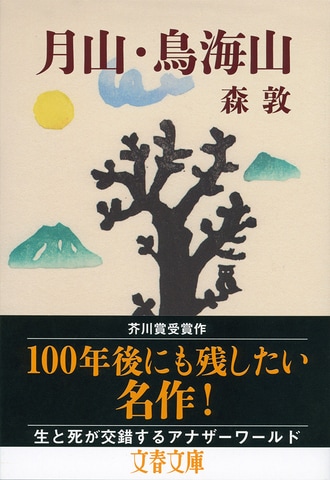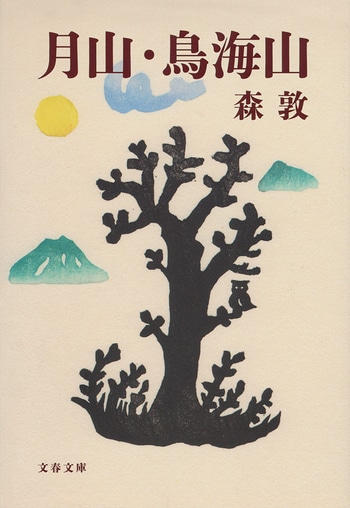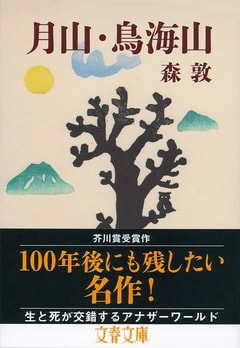大山町は私は知らないが、吹浦や酒田は何度か作者を訪ねて出かけたことがあり「かての花」の弥彦でも作者に会い、鳥海山の中腹まで登ったように弥彦山にも登り、山頂から冬の佐渡を見た。そこに石原があったことは一向に記憶にないが、今から十年前上京した作者が居を構えたのは、たしか調布の下石原というところであった。多摩川べりで、近くに京王閣があり、そこは東府中の近くでしばらく行くと大国魂神社があった。「かての花」を読み、グリ石の話が出てくると、(ここでも「わたし」がそのふもとに住みつくようになる弥彦山の話から語られはじめる)私は下“石原”のことを思い出す。そうして次にふれる「鴎」の中に出てくる砂丘のミコトとかヒメと書いた墓石を思い出す。それはやがてもっとあとにふれる「天上の眺め」のグリ石ともつながる。グリ石を通じて読者の私は戦争中そこを通り過ぎただけの京城にも思いはのびる。これらの作品の中で特に作者の気に入られている石は、ひょっとしたら同音の「意志」とも通じるかもしれない。いや、きっと通じるのであろう。あからさまにそうはいっていないが、自らの意志をもって黙々と存在し、川を登りさえし、屋根にまで登り置石として姿を見せてしたり顔をしているグリ石どもは、これすなわち意志でなくて何であろう。そうしてその意志は外貌は丸やかで機能的でしかも墓にもなる。生あるが如く、表は乾けども底は濡れる。作者は下石原という地名をもった場所を選んだのではなくて、至るところ、しかるべきところにしかるべき名称をもった場所があり、世界中といわぬまでも日本中、同じ仕組みになっている。見るものが見れば同じイメージを抱いて人々が住みこんできているのだ。それを思うとき作者は如何ばかり喜びにふるえたであろうかと想像せざるを得ない。「かての花」では石は雪がとけるとせせらぎの音と共に生々しい姿を現わし、やがて草の下にかくれる。薪を拾いにきた老婆は(ここでも“ばさま”が登場する。なぜだろうか)長太郎どんが石を車で運んで行ったという。つまり生活の糧となったわけだ。それならこの“ばさま”はどうだ。やがて姿を見せなくなった彼女も別の男の話ではこの世を去ったが、実は鋸で木を伐っていたのだという。薪の話は大台ガ原の山の中で、天の賜と称して洪水のさいに上流から流れてくる木を拾う話と呼応する。山を登るグリ石のいた山の中のことと呼応する。これはやがて「天上の眺め」では忽ち時空をこえる。そうして、前にもいったように弥彦にいることは、弥彦にいることではなくて大台ガ原の山中にいることでもあり、やがて未来に向って別の場所にいることでもある。
《シンシンと降る雪に埋もれて、いまは遠い当時のことをひとり懐かしんでいると、ふしぎにもわたしには、石という石を拾い尽くして、どこへともなく行ってしまったという長太郎どんが、あの連中のような気がして来るばかりでない。わたしはまさに遠くに行き、こうしてここに来ながら、かえってここにこうしていることが、遠くで夢みた夢の中にいるように思えるのである。》
深夜の荒海に横たえている佐渡を思いながら暮しているが、弥彦では薪と石とが存在の秘密をあかす役割を果す。糧にもならず、それなら伐っても文句の出ぬ「かての花」(この名に何と作者はいくつもの意味をもたせていることであろう)それは「鴎」の中で天の賜である松笠や海辺に流れよせる木片を拾う生活と結びつくと、容易ならぬ、(といって決して深刻な意味というわけではないが)ひびきを放ってくるようである。春、弥彦山の向う側へ降りると、思いがけず桃源郷のような部落があり、かての花が咲き、そこにまた刻まれた文字もうすれ、ただの石になろうとする墓石がある。盗むべきものもないが、その代り既に時間は失われている。時間のあるところ、私たちはダマシ、モドキであらざるを得ない。願わくは、姿うつくしく意志的であれ! いや、全き姿でもって我の前に現われよ。我に十全と思わせよ! 小癪にもグリ石の如く、“ばさま”の如く、馬主であって騎手であって、自転車の運び屋になりさがる弥彦の競輪選手のように、全一の姿であらわれよ! そのとき「わたし」は親しみをおぼえ笑ってやるであろう。なぜ笑うか、なぜ小癪だと思うのか。なぜか。「わたし」は、天の近くにはいのぼろうとしているからである。石の如く意志だからである。
私はここで飛躍するが、最近作者が新聞などに書いているエッセイのことを思い出してもらうと面白いと思う。時々作者はその中で大笑するが、とくにゼロックスの宣伝広告文として書いた「夫子の笑い」という戦闘的気配にみちみちた一種危険さをはらんだユーモラスな名文は、自転車の運び屋でありながら騎手であり、そして馬主でもあるという順序で登りつめるという方向をもっている。「かての花」で作者が眺めて「みょうに笑いたくなった」というような言葉で語られているときとは一見逆に見える。何かしら爆発的なものがあり、暴力的でさえもある。そこでは我天に近しという気概もあるが、天に近しとは死に近しという意味をふくめてのことである。夫子は孔子であり、夫子とは「我」という意味である。もともとその両意をもったのが「夫子」なのである。我は孔子であり芭蕉であり、グリ石であり、熊野の木立である。と同時に孔子は我であり、芭蕉は我であり、グリ石は我である。同じイコールでつながれていても、そこに盛りあがってくるイメージはまったく違う。私はもともとこういうことを考えるのが得意ではない。だが今いったところの、この盛りあがってくるイメージのことを考えると、やはり認識の基本であるばかりか、ひょっとしたら作者が「月山」のエピグラフにつかい、「夫子の笑い」の中で扱っている「論語」は正にこの認識そのもので貫かれているように思えぬでもない。そうして「論語」のことはしばらくおくとしても、小説における表現の問題も、尽きるところ、イコールであるが、左に置くのと右に置くのとでは大いなる違いがあり、位置がひっくりかえるときに、実は孫悟空の如く宇宙をいっきょにかけめぐり、風に乗ると見えて風をひき起し、巨大なエネルギーが造成されるように思われる。こんなことは、道元の「有は無、無は有」という言葉のいわんとすることと同じであるといってしまえばそれまでである。認識の初歩だといってしまえばそれまでである。そのときこの認識の意味から離れるのだ、とこういうと、これはこれで修行や悟りの問題になってしまう。ところが実はそうでない。悟りの問題ではない。易しくいえばそうともいえるが、やはり悟りではなくて、イメージの問題であって、と作者はいいたいのだと想像する。そして今いったようなイメージの逆転に堪えることは、一つの倫理でもある。といっていわゆる深いとか浅いとかいうこととも違う。深さの問題でもないのだ、と作者はいいたいように見える。
あまり立ち入ることや、くわしく考え過ぎることは、私は望まない。けっきょくせいぜいヒントを出しておくことが読者に対しても私自身にとってもよいことであり、また作者に対してもよいことと思われる。ところで「夫子の笑い」は神の笑いの感じがあり、自他ともに幸福感にひたらせもする文章であるが、危険さがある。その危険さこそ笑いを誘いもするし、この文章の劃期的なものである所以の一つだが、一種の裸形の雰囲気がある。エッセイであるから当然だ。だが果してそれだけか。
私はこう書きながら、さっきからアイマイにしかいえぬ自分の文章を恥かしく思いながら、何か今までよくつかめずにいたことでようやく今になって少し分ってきたように感じる。またもや、ひょっとしたらだが、作者が「荒涼」を求めたり、「壮麗なるもの」をひそかに求めて新潟や東北の山のあたりに、それから大台ガ原山に入ったりするのは、それなくしては、十全な感じをもつことが出来ないとかいうようなことだけではなくて、爆発的ともいえる荒ぶる精神をなだめるにはそういうところでしかない、ということなのかもしれない。そして、作品の登場人物はそれにふさわしい老婆であったり行商人であったり、工事人夫である「渡り鳥」(渡りをつける意にもつかわれている)であったり、莫大な負債を負う、都会からの訪問客であったりするのも一つにはそのためかもしれない。山にある神社は祀られる霊をしずめるものであるというのは、しずめねばならぬものを蔵しているということだし、そこに近づくものもしずめられるのだろう。そうであるなら、先ず山のことから書きはじめられるのは、地理的位置を案内したり、世界構築への案内の手順であるだけではないということにもなる。あらためて先ず作者自身の心をしずめる手順であるし、それがあってくれるのなら、安心ということなのであろうか。誰しも安心立命などたやすくあり得るわけはない。