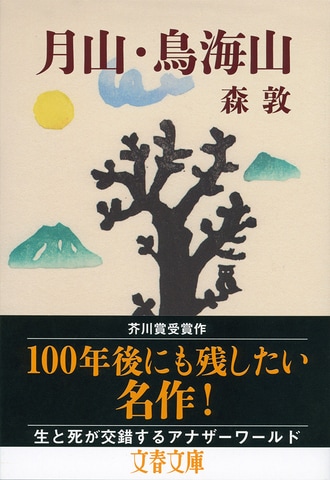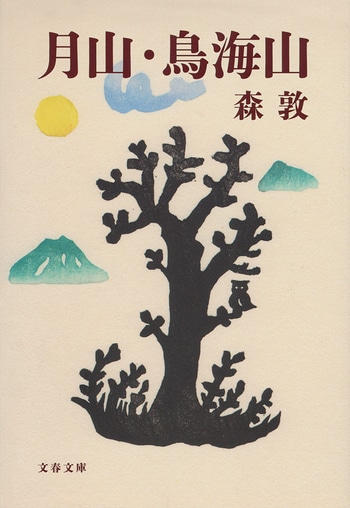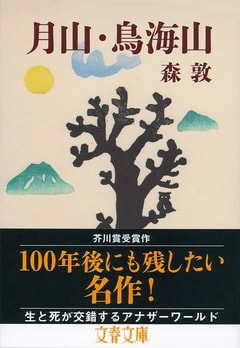二 「鳥海山」──「月山」への道(解説:初出「文藝」昭和四十九年六月号)
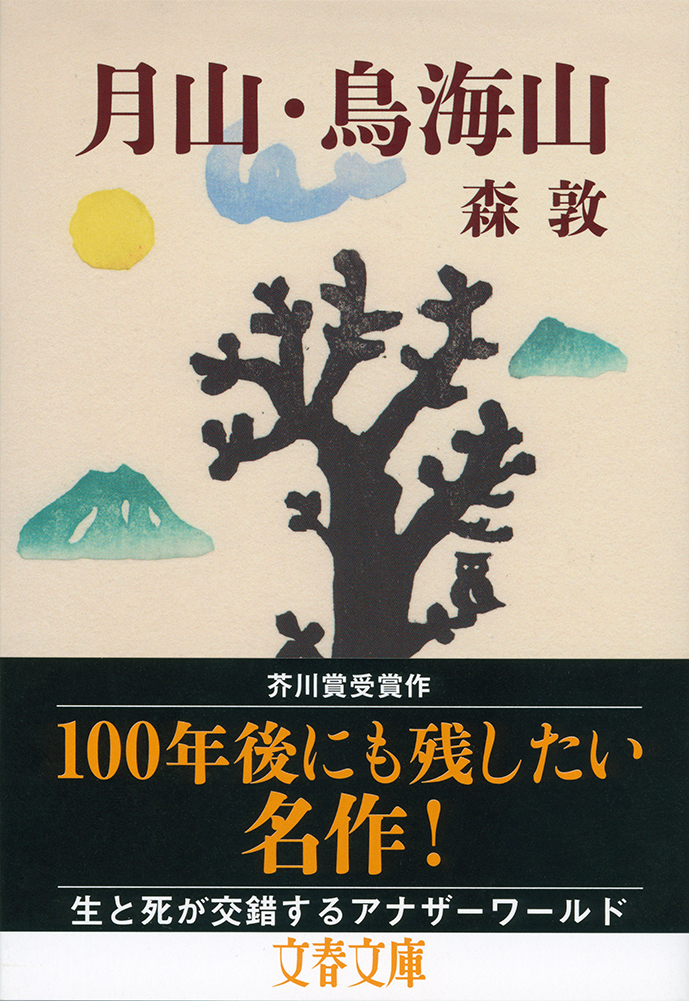
「月山」以前に同人誌に書かれこんど改稿された森敦氏の諸作品を読みなおし、その長い交友の記念に書かせて貰おうと思った。屋上屋を架するきらいもなきにしもあらずだが、邪魔にもなるまい。この解説を書くにあたって、またもう一度読みなおしたさい、たまたま「光陰」が最後になったので、これから語ることにしよう。庄内の大山町の下宿さきの“ばあさん”は大夫(たゆう)と呼ばれる神主に代筆を頼んでいる。大阪に働きに行っている娘を、傷ものにならぬうちに妾にやるべく呼びよせようというのだが、娘の方には、既に帰れぬ事情が出来ている。代筆者はそのことを娘の手紙から知っていて、帰らなくとも宜しいというふうの意味の手紙を書いている。
「わたし」は代筆の文面の偽わりや、それに安堵している婆さんを腹だたしく思う。娘も妾になることもいやではないが、帰れぬことを嘆いている。その手紙などを読むと自からも偽わらねばならない立場になる。そういう婆さんとのやりとりが優しい穏やかな文章で、時間の進むにつれて物事があらわれ物事が解けるように書かれる。まるでその優しさは時間とのつきあいのよさ(十分に意図された)の別名でもある。そして月影は蚊帳の中へやさしくさしこむ。頭が冴えて眠れぬのだが、それがもう夢路にあったのかもしれない、という。「わたし」の願いを知ってか知らずか、時間は月の光のかたちをかりてなだめてくれる。そうとは書いてはないが、その月影は、廊下一つへだてた婆さんの三畳間をてらし、異郷の娘の上をも照らしているに違いない。
いったいこの小説は、月山と鳥海山とが左右に見られる位置にある大山公園近くの話である。庄内の者は東北ではないと誇りをもつという。公園は妾を何人ももっていた嘉八郎がその銅像ぐるみ寄附したものである。その妾さまのことを語る婆さんはこの土地のものではないのに、土地の者の如き話し方をする。「わたし」を自分と同じ北海道ものか、ときいたりする。人間がある場所で、ある言葉をつかったり、それをきいたりするということは、要するにそうしたことである。それはやがて娘が大阪にいる、ということや、その娘のことを距離をこえて考え続けているということと似たようなことなのである。距離とか場所とかいうものはそういうことだ。
おしつめれば、公園からよく見える月山や鳥海山がそこにあるということは、人間、万物のありようを見せていることなのだ。嘉八郎は知るや知らずやそこに立っている。知らないといっても、二つの山を臨む場所ということはほとんどのことを心得ているともいえる。山は蓄財も蓄妾も、お見通しであるばかりか、内ふところの深い一種のボスの如く備え隠している。
湿気は山をけぶらせる。蚊もその湿気から湧いてくる。その蚊が嘉八郎をせめてさぞかしかゆかろうという“ばあさん”は、やがてその妾のことを口にする。ということは既に自分の娘のことを考えていることが分る。このようにして語り手の如き装いをしながら作者は、天地の構造をあかそうとする。そして、天地は宿屋であって万物が人間も蚊もそこに住むとはいえ、光陰こそ百代にわたって過ぎゆく旅人であるとなると、人間に対して優しからざるを得ない。このようなことは、この作品を少し仔細に読めば誰しも味わえることである。またその奥に流れる「ダマシ」というものも、至るところに飛石のように散りばめられ、相呼応するようになっている。物いわぬ銅像も、婆さまをねらったり、蚊帳の中の「わたし」が追いかける蚊にもダマシはある。異郷の娘にも、そのささやきがきこえてくる。「浮世」が浮世であり、うつせみの世である以上すでにもっているダマシというものを森羅万象がもっている。そういうことを「わたし」が感じるのではない。また「わたし」が大山町の下宿にあっての話を語りながら、おのずから天地の理法を感じるというのでもない。そうではなくて、最初にもいった通り「わたし」が語ってきかせるというふうになっている。このように語ってきかせる「わたし」とは何ものなのか、という疑問を起す人があるかもしれない。それならば、「わたし」は作者に等身大であるばかりか、このような天地の理法を語る用意をもった人、そしてそれにふさわしい生活をしている人というふうに考えてもいい。作者はわざとそのような意味では素朴な「わたし」を出し、「わたし」を書くのでも、「わたし」について語るのでもなくて、「わたし」の話す話をきかせている。
何もこのような「わたし」の扱いが小説というものの唯一の方法であると思っているどころか、その反対であるが、作者は自分としては、これがふさわしいものだと腹をきめたというのであろう。その代り、そのうえで、地名も物やことがらの名称も、それから動詞も作者の秘めたイメージを通して相呼応し、ひびき合い、その表現法でもって天地の構造が描き出されるというのが、作者の意図なのであろう。
蚊帳にさす月の光は、月の光というものについて、祖先によって蓄積されたイメージを少しでも呼び起すとき、作品は動きはじめる。妾、という言葉についてもそうである。気がつくと動きはじめるとは、一種のアソビであるが、そのアソビなくては天地に参加はできない。……
「初真桑」は鳥海山麓にある吹浦や、それから酒田の話になり、その昔芭蕉が泊った鐙屋に自分も泊るというふうに述べられる。
《この真桑瓜の句にしても、人のいうようにこれが軽みでないとは思わぬが、芭蕉もあすはこの江商──おそらくは、この鐙屋も近江屋を意味する「あふみや」からきているのであろう──からいくばくの路銀を得なければならなかったのだと思うと、こういう句まで趣を変えてくるような気がするのである。しかし、これも風流と解して深く問わぬことであろう。》
芭蕉がそれを御馳走になりつつ、よい句を作った初真桑は、時がとまったように長い間待たされた同行の“ばさま”の荷物の中からも匂ってくる。この作品では、草の木の名でもあるという「ダマシ」「モドキ」(モドキとは作者はわざと語らないが、思うに神おろしの意もこめられている)が天地にかくれそして隙を見てこだましているように書かれている。あまりにくどいではないか、と文句をいってもはじまらないようなものが全体にある。天地を構築するのに、ひびかせ方のうまい下手があり、手際のよさわるさが、どこかにあるとしても、それは二の次のことである、という態度がここにある。「わたし」はここでもうけこたえするだけで、深く立ち入らず、考察者の色を濃くしているが、“ばさま”が死んだ“じさま”を生きているかのように客に話しているところは、普通の小説のように面白い。しかしその面白さは、そこにそのような“ばさま”がそのようにしゃべり、そうと気づかず、ふりをしているということが濃厚に分り、そのまま(“そのまま”ということなどあるものか、というふうにもいえる)存在を主張しているわけであるが、作者はそれであき足りるものではない。忽ち“ばさま”も「わたし」の考察にくりこまれ、時間をこえて芭蕉につらなり、そのことによって、自分ともつながり、空間的となる。その態度は強力で意志的で、やさしい応対にも拘らず、テコでも動かぬ立ち姿をそなえている。