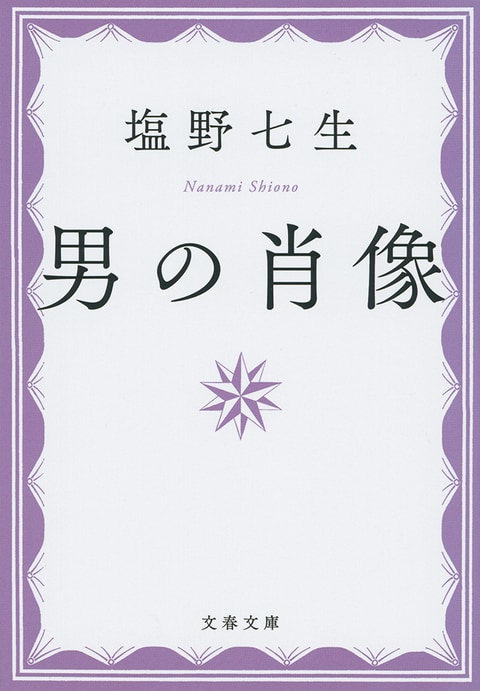
ペリクレス、アレクサンダー大王から織田信長を経てチャーチルまで、古今東西の14人の男の肖像。順に読み進めていくと、最後に15人目の肖像が浮かび上がってくる。それは「女の肖像」、塩野七生その人である。
僕は歴史家でも作家でも文芸評論家でもない。競争戦略論という分野で商売と経営について考えるという仕事をしている。競争があるなかで、なぜ商売は儲かったり儲からなかったりするのか、その背後にある論理を考えるという、やたらに世俗的な学問である。
競争の戦略とは何か。一言でいえば、他者との「違い」をつくるということになる。ただし、違いをつくるには2つの異なるアプローチがある。この区別が競争戦略の思考のカギとなる。
ひとつは他者よりも「ベター」であるという違い、つまり特定の物差しを当てたときに認識される違いである。人間でいえば足の速さとか視力とか身長のように、ある尺度で比較したときに現れる程度問題としての差である。
この種の違いは本質的な差別化にはなりえない。競争の中で大勢がベターになろうとする。ベストを目指してしのぎを削る。一時的にベターになれたとしても、いたちごっこになってしまう。違いの賞味期限が短くなる。顧客もはっきりと違いを認識しにくい。
ベターではなく「ディファレント」、ここに戦略の本質がある。人間で言えば、男と女。両者の違いは程度問題ではない。「私はあなたよりも70%より男性です」、普通はこういうことはない(たまにはあるかもしれないが)。ディファレントであってこそ、競争の中で独自のポジション(立ち位置)をとることができる。
塩野七生はまことにもってディファレントな作家である。
出版業界の中でも歴史小説はもっとも多くの読者を抱えるジャンルのひとつだろう。需要があるところに供給があるのが世の常。次々に歴史小説の書き手が現れる。それだけ競争も熾烈になる。そうした中にあって、塩野七生という作家は多くの愛読者を惹きつけて離さない。僕もその一人である。なぜか。彼女が単にベターな作家だからではない。はっきりとディファレントであり、余人をもって代えがたいポジションを確立しているからである。
僕は最初の10ページを読んで面白くなければ、そこで読むのをやめてしまう。本という商品は時間の流れから逃れられない。顧客である読者は最初から最後へと読み進める。よっぽどの変人は別にして、どんな作家もなるべく多くの人に自分の作品を読んでもらいたいと思うだろう。読者を惹きつけるため、最初の部分に全力を傾注するはずだ。そこが面白くなければ、後を読んでも面白いわけがない。
その点、本書の劈頭を飾るペリクレスの章は最高の見本といってもよい。のっけから著者の独自性が色濃く現れており、それが読者を楽しませてくれる
ペリクレスの顔をはじめて見たのは、高校の西洋史の教科書でだった。それは、胸像をななめ右前方からとらえた写真で、高校の教科書だから、その胸像がどこにあるかまでは書かれていない。ただ、この写真が十六歳の少女に与えた印象は鮮烈だった。
なんと端正な美貌(びぼう)であろう、と思ったのだ。そして、そのページに書かれている説明、それはペリクレスについてというよりもアテネの民主政治についての説明だったが、それも端正な美貌をかたわらにして読むと、実に「端正」に思えたのであった。ペリクレスの顔は、民主主義の広告としては大いなる貢献をしているのではないかと、今でも思う。
歴史小説や本書のような歴史的人物についての随筆は研究書とは異なる。正確なファクトを記述するだけでは作品になりえない。ファクトに作家の解釈やイマジネーションを加えてはじめて小説や随筆になる。客観的なファクトか主観的なイマジネーションか、どちらに軸足を置くかで歴史小説の書き手は特徴づけられる。
塩野七生ははっきりとイマジネーション志向の作家である。16歳のとき、たまたま歴史の教科書でペリクレスの胸像の写真を眼にする。その端正な美貌に瞠目し、政治家としての「端正さ」を直覚する。そこからアテネの民主政治の輪郭を描き、その黄金期をリードした指導者の器量を論じる。
こうしたスタイルは、例えば、同じように多くの読者を獲得した人気歴史小説家、吉村昭の対極にある。史実と証言の徹底的な取材と検証にこだわり、ファクトの記述を淡々と貫くことによって、吉村は「戦記文学」というジャンルを確立した。
もちろん著者にしても広範にして膨大なファクトに目を通した上で書いているに違いない。しかし、それにしても作品に表れる記述は主観的で感覚的である。情緒的といってもいい。どちらが良いという話ではない。はっきりと違うのである。
先に引用したように、著者が歴史教科書で見たペリクレスの胸像の写真は「ななめ右前方から」のものだった。当時の教科書が手元に残っていたわけではあるまい。彼女は何十年も前に見た写真をありありと記憶しているのである。いかに感覚が鋭敏で、対象に入れ込んでいるかを物語るエピソードだ。












