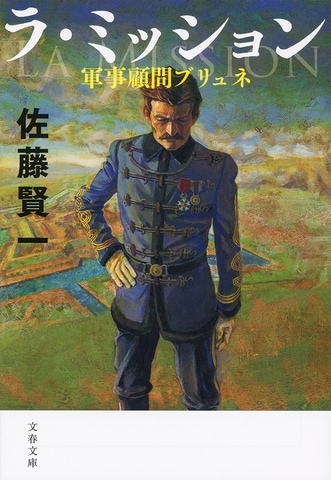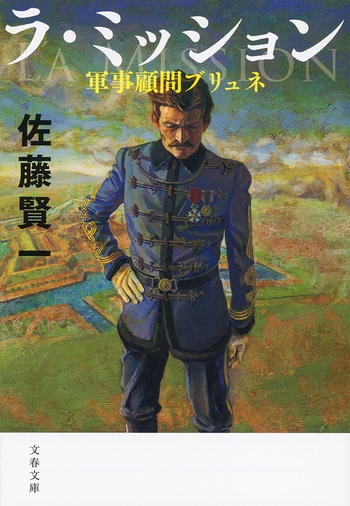2.歴史学と小説と
歴史小説を書く作家たちは、過去の表層を学ぶ(確かにそれは、たいへんに困難な作業であるが)のに忙しく、時代の構造・骨組みには注意を払わない。だから日本史の中世社会も、戦国時代の動乱・幕末の混迷も、中国やヨーロッパの歴史であっても、みな等しく、現代人の観点・視点をもとに語られてしまいがちである。その時代・その地域に特有な「価値や理念や感覚」に即しての物語作りは、残念ながら滅多に見ることができない。
これに対してごく少数ではあるが、舞台となる時代や社会の本質を十分に理解し、ストーリーを構築していくことのできる人がいる。ヨーロッパ中世史における、日本の幕末史における佐藤賢一は、まさにその代表である。彼が紡ぎ出す物語は、真に迫る説得力があって、豊かである。これこそが歴史である。彼はまさに、単なる歴史学者とか歴史作家というようなカテゴライズを易々と乗り越えた、真の歴史の語り部なのだ。
昭和三十(一九五五)年、マルクス主義歴史学者の遠山茂樹らが書いた『昭和史』(岩波新書)が大ベストセラーになった。ところがそれに対し、文芸評論家である亀井勝一郎は、この本には人間が書かれていない。著者はもっと実証的であってほしい、と鋭い批判を投げかけた。以降、亀井の言説を受けて、『昭和史』賛成派と反対派が次々と登場し、世にいう「昭和史論争」が巻き起こっていく。
『「元号」と戦後日本』(青土社)で「昭和史論争」に注目した鈴木洋仁によると、著者の遠山らは自らの叙述姿勢が「科学的」であると誇りながら、その実マルクス主義が導き出した「昭和=戦前=悪、戦後=善」という視点に引きずられている。すなわち、マルクス主義の産物である「結論まずありき」の考察に終始している。それゆえに、実証的でない、との亀井の批判は相当に効果的で、正鵠を射ているという。
とりあえず「科学的な」歴史学者を標榜しているぼくは、亀井の批判に接して衝撃を受けた。史料編纂所に勤務するぼくが根拠とするものは、「歴史資料」である。「歴史資料」の信頼性を吟味し、歴史事実を解き明かす。この手続きは、学問的な訓練を受けた人のあいだで妥当性を共有できるという意味で「科学的」であり、かつ「実証的」であると理解して疑わなかった。だが、もし遠山の姿勢が――彼も『昭和史』執筆時に史料編纂所の所員であり、歴史資料に依拠することを信条としていたと認められる――亀井のような達人にかかると「より実証的であれ」「もっと人間を学べ。人間を叙述せよ」と批判されてしまうのであるならば、ぼくの「科学的な」姿勢ごときは、木っ端微塵にならざるを得ない。
実はぼくは、そうした反省と困惑のさなかに『ラ・ミッション』を読み直した。ああ、そうか。目から鱗が落ちる思いがした。歴史資料にただ単純にすがるだけではない、亀井の言う「その先にある実証性」とは、まさにこのことか。
佐藤は、列強の利害がダイレクトに作用する世界史の一コマとして、戊辰戦争を捉え直す。その中で、まさに列強の尖兵として来日したブリュネは、オオトリ(大鳥圭介)やイジカタ(土方歳三)ら敗残の幕府兵の士道に共感し、煩悶する。私はいかに生きるべきか。私の「使命」とは何だ。苦悶の末に彼の出した結論は、軍籍を捨て、旧幕府軍の一員として戦い抜くことであった。日本の士道とフランスのエスプリ。男のゆるぎない覚悟が、本書の叙述をすみずみまで支えている。この意味で、この本こそは、まさに「人間を生き生きと描いている」といえる。ああ、佐藤賢一はやはり、卓越した歴史家であった。