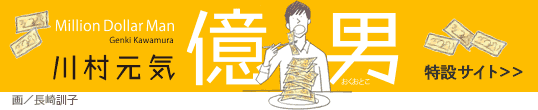一男の世界
野口英世も樋口一葉も貧乏だったらしい。
貧しい家に生まれながら医学者として成功を収めた美談を持つ野口英世も、のちに散財を繰り返した。樋口一葉は『たけくらべ』を書いて一流作家になってからも借金に苦しみ、二十四歳で亡くなるその瞬間まで貧しかった。お金で苦しんでいた人が、死後に紙幣になるなんて、当の本人はどう思っているのだろうか。
「きっと貧乏には楽しいことがたくさんあるに違いない。そうじゃなければ、こんなにたくさんの人が貧乏でいるはずがない」
昔読んだ本で、見つけた言葉。それが教えてくれたのは、貧乏を楽しむ方法ではなく、この世界はお金の皮肉であふれているということだった。
一男が三億円を手にすることになったのも、そんな皮肉めいたある一日の出来事がきっかけだった。
ちょうど三週間前の金曜日。一男は図書館のカウンターのなかでひとり、返却された本の整理をしていた。毎朝八時半に出勤し、館内の電気をつけ、エアコンを入れる。カウンターの中でパソコンを立ち上げ、開館準備をする。九時に図書館が開いたあとは、来館者の貸し出し手続きと新着本の整理をしながら、返却された本を書棚に戻していると一日が終わる。幹線道路から少し奥まったところにある図書館の中はほとんど音もなく、どこか浮世離れした静けさに包まれている。
「ちょっと……すんません」
掠れた声に呼ばれ、一男は振り向く。ぼさぼさの髪に無精髭。ずいぶんと痩せた青年が頬を掻きながら立っていた。着ているトレーナーの首がだらしなく伸びている。浪人生かフリーターか。青年はあくびを噛み殺しながら訊ねる。
「金持ちになれる……みたいな本って、どこすかね?」
あまりにも大雑把な問い合わせだが、この手の質問は少なくない。多くの人が“何かの答え”を求めて図書館にやってくる。
「それは……金持ちになるための実用書ということですか?」
一男は、痩せた青年の足元に目をやる。白いキャンバス地のスニーカーはずいぶんと汚れており、その踵は踏みつぶされている。
「そう。それ的なやつ」