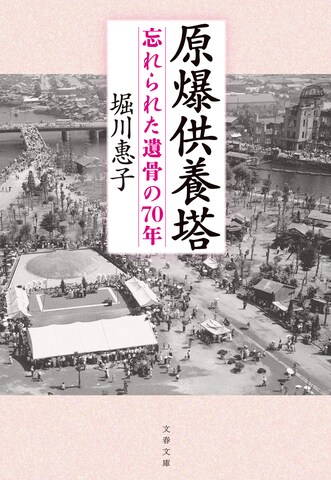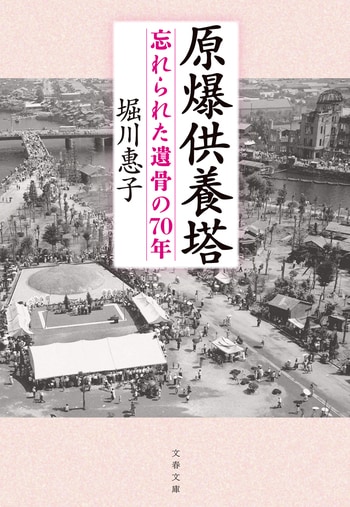その日は抜けるような青空の広がる五月晴れで、ひと足先の初夏を思わせた。「原爆ドーム前」で路面電車を降り、平和記念公園内の北側を目指す。連休のまっただなか、地元の家族連れや観光客の姿でにぎわっており、ライブ演奏があたりに響くなごやかな昼下がりである。しかし、いま自分が歩いている足の下にはかつて市内有数の繁華街が広がっていたのだと思うと、複雑な感情に捕まって混乱してくる。
原爆投下の照準とされた相生橋、連絡橋南詰近く。原爆の子の像が建ち、被爆した墓石が当時の地形のまま安置されている。そこからほど近く、緑の芝生に覆われた土盛りの小山が目に入ってくる。
原爆供養塔である。鬱蒼と生い茂る木々に護られ、ふっくらと盛り上がる塚の頂に石塔が立つ。伏せたお椀に似た塚に向かい合うと、静寂がひたひたと押し寄せてきた。公園内の喧噪が、すうっと遠のく。この広島の墓を、佐伯敏子さんは身を削って生涯守り続けてきたのだ。そして一九九三年、著者が佐伯さんに出会ったのもこの場所なのだった。
死者を葬り去ってはならない。死者を忘れてはならない。死者を歳月のなかに埋もれさせてはならない。なぜなら、原爆供養塔におさめられているのは、無差別殺戮によってもたらされた無念の死であるから。本書が問いかけてくるのは、死者の想いとともに私たちが生きることの意味である。
昭和二十年八月六日午前八時十五分、爆心地は瓦礫の海と化す。その中央に位置した慈仙寺や広島市役所に行き場のない遺骨が次々運び込まれた。人肉の焼かれる匂いと煙を浴び、野宿同然のまま遺骨を拾って歩く僧侶。市長室に畳一枚を持ちこんで遺骨を守り、供養する二十代の若い女子職員。または昭和二十九年、供養塔再建に向けて行政を動かした建設局長や、舞台裏で財源を死守した漁協のボス。彼は、原爆によって愛娘をふたり奪われた父親だった。
私たち生きる者は、これまで死者と正面から向き合い、寄り添い、ひとりひとりの人生が語りかけてくる言葉に耳を澄ましてきただろうか。著者の視線は、日本の戦後そのものにも注がれている。
本書でつまびらかにされる佐伯敏子さんの修羅の人生。戦後七十年の歳月から丁寧に掬い上げられてゆく知られざる事実の数々。この原爆供養塔にも、存続の背景には人々の辛苦が秘められていた。縷々語られる事実は、打ちのめされるほかない凄まじさである。いっぽう、目をそらさず、こうして読む行為そのものが死者に向き合い、寄り添い、考えることでもあるという思いがしだいに湧き上がってくる。なぜか。それは、一言一句が著者が自身に課した覚悟と厳しさによって貫かれているからだ。
掘り起こされる事実のあらゆる細部に、堀川惠子そのひとが遍在している。ジャーナリストの執念や誠実を超えた、人間としての生き方が事実の毛細血管のすみずみに血を通わせているのである。だから、読む者を突き動かす。ノンフィクション作品に真に胸を打たれるのは、記された事実や記録の凄みによってだけではなく、それらを通じて書き手の人格の深部に触れるときだ。
著者が佐伯さんの行方を探したのは二〇一三年が明けた頃、とある。九年前、著者は広島のテレビ局の報道部デスクとして、似島で行われた遺骨発掘作業の取材を最後の現場にしようと考え、しかし割り切れない思いを抱きつつ広島を去った。その心の揺れを、著者は、病に倒れたのち老人保健施設で暮らす佐伯さんに打ち明ける。いまなお似島で目にした遺骨が気にかかるのは、これまで自分が死者の存在について深く考えていなかったからではないか、と。告白を受けた佐伯さんは、示唆をあたえる。
「あなたが似島で見たのは、供養塔の地下と同じ、あの日のまんまの広島よ。死者の本当の気持ちにふれてしもうたんじゃ。じゃから、自分がこれからどうするか、自分の頭で考えんといけんよね」
本書は、佐伯さんの発問にたいする全身全霊の返答でもある。毎年七月、広島市が公表する「原爆供養塔納骨名簿」は、佐伯さんが原爆供養塔の地下室にこもり、懐中電灯で照らしながら写し取った記録を下敷きにしている。その名簿を手がかりに、船に乗り、新幹線や鉄道を乗り継ぎ、レンタル自転車を漕いで遺族探しをはじめる著者の姿は、まるで佐伯さんが乗り移ったかのようだ。そして、推理小説を地でゆく困難な作業を続けるうち、疑念が湧きはじめる。納骨名簿に記されている情報は、いったいどこまで正しいのか?
半年後の七月、取材の経緯を報告するため、著者はふたたび佐伯さんのもとを訪ねている。疑念を率直に打ち明けると、「おうとるほうが、不思議よね」。虚を突かれ、あわててテープレコーダーの録音ボタンを押した。では、間違っているかもしれないのに、なぜ佐伯さんはあれほど根気よく遺族を探し続けたのか。
堰を切ったように語られる、九十三歳の語り。
「――じゃから、遺族が分かるということのほうが奇跡なんよね……。でもそれもまた、本当は違うとるかもしれん、だけど、もし何か手がかりが見つかったら、それは伝えんといけん。いらんと言われても、伝えるだけは伝えんといけん。それは知った者の務めよね」
固唾をのむ著者の気配が伝わってくる。
では、生きる者は何を伝えるべきか、何をなすべきなのか。
「現実は厳しいからね。二〇〇〇柱、名前の分かっとる遺骨があって、その中のたった一〇人とか二〇人くらいしか、本当の真実はないかもしれん。だからといって、それを捨てることはできんのよ。死者を見捨てることは、できんのよ。名前や住所が違うとるのは、生きている者のしわざじゃから。あそこに眠る死者たちはみんな、息をひきとる前に家族のもとに帰りたいと思いながら、自分の名前や住所を伝えていかれたんじゃから。その気持ちを考えるとね、知ってしまった人間として知らんふりはできんのよ」
著者を、佐伯さんは質したのである。終生いかなる政治組織や団体にも属さず、一市民として原爆供養塔の守り人であり続け、志半ばで病に倒れた悔しさもにじむ。くわえて、おたがい真実に近づこうとする者同士としての、連帯の表明でもあったろう。正義感や使命感だけではない、「知らんふりはできない」とは、つまり生き方に関わる問題なのだ。
自身の葛藤や孤軍奮闘ぶりについて、著者はみずからを律して多くを語ろうとはしない。しかし、事実に即して忠実に語られる言葉は、緻密な取材によって集められた証言、丹念な資料収集、煩雑な裏付けを厭わぬ精査のたまものである。その結果、私たちに手渡される事実の数々は、日本の戦後史の発掘に繋がってゆく。全国の農漁村から軍事拠点広島に動員された少年特攻兵たちの存在。朝鮮半島出身者たちの身の上と、理不尽に抹殺された人生。納骨名簿に記載されながら、じつは生存していた従軍看護婦。半世紀以上の歳月を乗り越えて弟の遺骨を手にした、かつての原爆孤児の半生。沖縄出身の被爆者は、戦後のアメリカ統治下、社会的に放置されたままだった……納骨名簿の名前ひとつひとつに、家族にまつわるおびただしい物語があった。ようやく連絡がついても、遺骨はすでに戻っていると言われ、受け取りを拒まれることさえあったという。読みながら、遺族の方々が抱えてきた煩悶の深さを、想像したことさえなかった自分の無知が恥ずかしく、歯がゆい。佐伯さんが洩らした言葉「おうとるほうが、不思議よね」のリアリティが、ひたひたと黒い雲のように迫ってくる。
著者を奮い立たせた存在は、ほかにもあった。佐伯敏子を十数年にわたって取材しながら、二〇〇八年に急逝したジャーナリスト、中島竜美。遺族から著者のもとに託された取材ノートが、執筆を励ます伴走役となったことも、ここに書き留めておかなければならないだろう。死者たちへの鎮魂の祈り、知らんふりのできない生き方、このふたつが本書を支える両輪の轍である。
原爆供養塔に眠るおよそ七万人、納骨名簿に記載される遺骨八一五柱。死者がひと括りの数字で語られることへの違和感、怖さを思う。数字のなかにひとりひとりの生を埋没させてはならない。二〇一七年、遺骨八一五柱のうち一柱の身元が判明、七十二年ぶりに遺族のもとに戻った。死者の語りに、私たちは耳を澄まし続ける必要がある。それが生きる者の義務であり、務めである。同年十月三日、佐伯敏子さんは九十七歳の生涯を閉じられた。
五月に萌える新緑が、原爆供養塔を取り囲むようにしてさわさわと揺れている。初めて私が原爆ドームの前に立ったのは、小学生のときだった。平和記念資料館で受けた衝撃は今日まで色褪せることはないが、近年その展示内容が原爆の凄惨さを減じる傾向にあることが、どうにも引っかかる。さまざまな思いが湧き上がるなか、それでもあたりの静寂に導かれて心の波立ちを鎮め、手を合わせた。佐伯さんがこの世にいなくとも、佐伯さんそのひとの魂はきっとここにある。死者を葬り去ってはならない。忘れてはならない。歳月のなかに埋もれさせてはならない。しばらくひとり佇みながら、この原爆供養塔の前で出逢った佐伯敏子さんと著者の姿に思いを馳せた。そして、本書『原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年』によってもたらされた〈読む〉という行為の強度を思い、あらためて畏敬の念を抱いた。