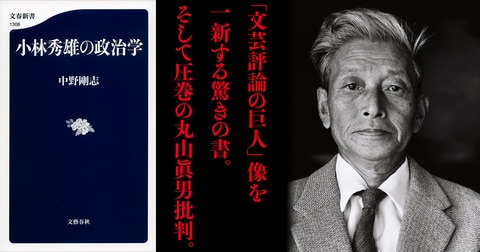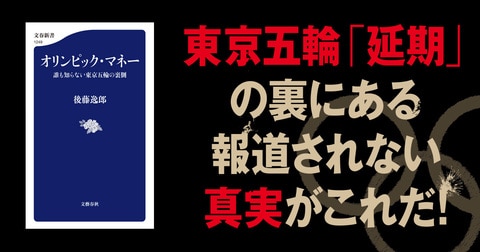「世界遺産」という言葉は、知らぬ者がいないほどの馴染み深い存在となったと言えよう。もちろん、世界遺産に言及した書物も数多く出版され、興味深い本が書店に並んでいる。
しかし、その主力はパンフレットのように世界遺産を紹介したものであり、一冊を貫く確固たる価値概念に欠けたものが多いのもまた事実である。きれいなカラーの写真に彩られたムック本は、読み手の心をくすぐるが、カタログ雑誌における“消費の刺激”のような影響しか与えないのかもしれない。
一方、専門家による硬質な良書もたくさんある。例えばユネスコ事務局長を務めた松浦晃一郎氏の論考『世界遺産 ユネスコ事務局長は訴える』(講談社)は、筆者にも大きな感銘を与え、本書の執筆にあたっても参考にさせていただいている。その他、歴史学や考古学、また生物学などを専門とする方々による著作は、世界遺産という制度が学術研究と密接に関係していることに改めて気づかせてくれる。
これらの書物はなるほど確かに素晴らしいのだが、世界遺産という制度や遺産そのものの価値を説明したものが多く、訪問客が如何に世界遺産と対峙すべきかという利用者側からの視点に乏しい。旅人が世界遺産という、「人類普遍の価値」に出会ったとき、何を考え、どのような態度を取れば良いのかという観点から書かれた書物はほとんどないのではないだろうか。
そこで本書では、数多く存在する世界遺産を観る視点として、「ダークツーリズム」という眼差しを設定してみたい。
ダークツーリズムとは平たく言えば、「戦争や災害などの悲劇の記憶を巡る旅」ということになり、世界遺産にも登録されているアウシュビッツ強制収容所や広島の原爆ドームなどがその対象となっている。実は、世界遺産登録物件の相当数が、こうした悲劇の記憶を持つ文化財であり、自然遺産についても環境問題と関係するケースがある。
日本人は通常、世界遺産と言えば、輝かしい文化文物ばかりを思い浮かべがちだが、世界遺産制度の趣旨は人類にとっての「顕著な普遍的価値」を次世代に受け継ぐことであるから、当然のことながら悲劇の記憶もその対象となる。本文で詳しく述べている通り、ユネスコ自身は特に「負の遺産」という概念を用いず、世界遺産については光の記憶も影の記憶も後世に受け継ぐようになっている。本書では、旅人が影の記憶を持つ世界遺産をどのように見ていくのかという点について、対象を固定的に観るのではなく、比較文明論的な視点から相対化して解釈するように心がけた。