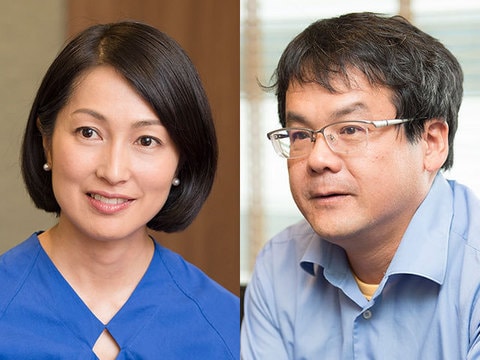その日、キューバ音楽史に関するレクチャーを終えたところで、一人の男性が近寄ってきて、声をかけられた。
それが、当時、このシリーズの執筆のために、キューバをはじめとするラテンアメリカに関する資料を渉猟しておられた海堂尊氏と私との出会いだった。奇しくも、そのまさに同時刻、巨星フィデル・カストロの訃報が世界を駆け巡っていた。
ラテンアメリカを一言で表現すると、陽気。サッカーや音楽や踊りが盛んという印象が強い一方、政情不安定で、やたらに政変が起こっているというイメージがある。
そのどちらも、あながち嘘ではない。
特に、後者のイメージが決定的に形作られたのは、二〇世紀前半から中盤の南米だった。
長年のスペイン王国の植民地支配から、ようやく、次々に一九世紀に独立を達成したものの、些細な利害の対立から国々は細かく割れ、さらに、それらの国々でクーデターや革命が次々に起こって、目まぐるしく政権が交代した。しかも、巨大帝国として新たに出現したアメリカ合衆国の利権に加えて、ソ連や中国といった共産主義国家の台頭という巨大な波に揺られ、二〇世紀のラテンアメリカの国々は、右も左も魑魅魍魎が徘徊する百鬼夜行の舞台となる。
本書は、世界で最も有名な革命家であるエルネスト・チェ・ゲバラ青年の、キューバ革命に至る前の旅を描いた小説だ。
実のところ、キューバ革命というのは、まさに、前述したような時代背景の中での試行錯誤であったわけで、その革命前史の時代を、この作品の中で、ゲバラ青年は全力疾走する。そしてその体験が、後の『革命家の中の革命家』としての彼を形作っていくことになる。
実際、アルゼンチン出身の医学生だったゲバラが、故国を遠く離れたカリブ海に浮かぶキューバでの革命に参加するまでには、長い道のりがあった。その、ごく若い頃の、盟友とのオートバイでの南米旅行は、彼自身が詳細に日記に記しており、二〇〇四年にロバート・レッドフォードの製作、《ラテンのブラピ》ことガエル・ガルシア=ベルナルの主演で、『モーターサイクル・ダイアリーズ』というタイトルで映画化もされている。本シリーズ第1巻『ゲバラ覚醒』に描かれているのは、それに対応する冒険談だ。
その『モーターサイクル・ダイアリーズ』時代の続き、すなわち、そこからメキシコに至るまでの空白を埋める形になるのが、本書『ゲバラ漂流』というわけだ。
とはいえ、これは、あくまでも小説である。
ゲバラ青年が、中南米各地を旅した末に、メキシコに辿り着き、そこで、フィデルとラウルのカストロ兄弟と運命的に出会ってキューバ革命に参加したのは史実なのだが、ことは、そう単純な英雄譚ではない。
なぜ、あの革命が起こったのか。なぜ、キューバ革命がキューバ革命たりえたか。なぜ、九〇年代にソ連東欧圏が崩壊しても、キューバは生き残り、それどころか、中南米ではその後も左派政権が生まれてきたのか。
そういったことを理解するためには、その土壌を深く掘り下げなければ、けっして見えてこないものがある。
外科医が患者の病態を理解するためにさまざまな検査をおこない、精緻に分析・検討した上で、はじめてメスを手に取るように、キューバ革命を生きた革命家の姿を描くためには、革命の足下にある歴史的・時代的背景を知悉しておかなければならない。
それは、医師でもある海堂氏には当然のことだったのかもしれないが、一方で、この時代は、ラテンアメリカ史の専門家であってさえもなかなか把握しきれない、もつれた組紐のような様相を持つ。
海堂氏自身、このシリーズを執筆するにあたり、一千冊を超える書籍を集め、ラテンアメリカ各地にも何度も取材旅行を敢行したというだけあって、本書の情報量は膨大だ。
だからこそ、なのだろう。
この、日本人には馴染みが薄く、しかも魑魅魍魎が跳梁跋扈する複雑怪奇な時代背景を鮮やかに浮かび上がらせるために、海堂氏はいくつもの華麗にして壮大なトリックを仕掛けている。
たとえば、当時の中南米の輪郭を描くために、前書ならびに本書では、いくつもの魅力的な《嘘》が語られる。
たとえば、本書の前編『ゲバラ覚醒』で描かれているように、エルネスト・ゲバラ青年が、日本ではミュージカルで有名になったアルゼンチン大統領夫人エビータ・ペロン(小説内では、ジャスミン)と親しかったという史実はない。
また、『モーターサイクル・ダイアリーズ』で一緒に旅をしたアルベルト・グラナード(小説内では、ピョートル・コルダ)は、ゲバラ本人よりはるかに長生きして、革命後のキューバに渡って医学校を創設し、本を書き、くだんの二〇〇四年の映画にも、しっかりゲスト出演していたりする。
若き日のゲバラは、確かにボリビアに滞在はしていたが、本書の中のエピソードのように、どさくさまぎれにボリビア革命に参加して前線で銃を握ったりなどしていないし、ペルーの大政治家アヤ=デラトーレ(殿下)に、極秘に会見し、政治についての激論を交わしたというのも、もちろん、史実ではない。
ましてや、豪華客船に乗ったり、パナマの〈エスクエラ・デ・ラス・アメリカス〉米州学校ことSOAで、特殊訓練を受けたりもしていない。
ちなみに、米国の大量の外交機密文書を暴露したウィキリークスの創設者、ジュリアン・アサンジは、訴追を逃れて、二〇一二年からロンドンのエクアドル大使館内に匿われているが、実は、その先例となったのが、このアヤ=デラトーレだった。彼もまた、軍事反乱罪で訴追されたことで、コロンビア大使館に逃げ込み、一九四九年から五年にわたって保護されていた。
物語では、そこをなにも知らずに訪ねていったのが、ゲバラ青年ということになっている。
つまり、本書で描かれるラテンアメリカの姿の大半は史実に沿っているのだが、ゲバラ青年が、ラテンアメリカ史に名を残す著名人と、行く先々で遭遇するという部分の多くは創作というわけだ。とはいえ、こうした嘘が効果的に鏤(ちりば)められることで、読者は、当時のラテンアメリカ史の百鬼夜行の現場に立ち会うことができる。それと同時に、これらの、日本ではほとんど知られていないラテンアメリカの歴史的有名人たちの登場自体が、ゆくゆくは、キューバ革命からゲバラの死までを描いていくであろう、この壮大な叙事詩の、後の展開の重要な伏線ともなっていくのではないか。
そんなことを考えながら、中南米史の勉強も兼ねて、どこが事実でどこが創作なのかを考えてみるのも、また一興かもしれない。
それにしても、海堂氏の流麗な筆で描かれた、それぞれの著名人たちのキャラの立ちっぷりときたら!
本文中で、ゲバラ青年が、ある重要な登場人物について「見てきたような嘘をつく」だの「息をするように嘘をつく」と評するシーンがあるが、誰よりも、息をするように見てきたような嘘をついているのは、作者の方だというべきだろう。
とはいえ、それが小説の小説たる所以。素晴らしい作家とは、天才的な嘘つきでなければならない。
そして、その巧みで鮮やかな嘘ゆえに、かえって、私たちは、ラテンアメリカ史の、キューバ革命史の深淵を覗き、バイブレーションを感じる愉悦に浸ることができるのだ。