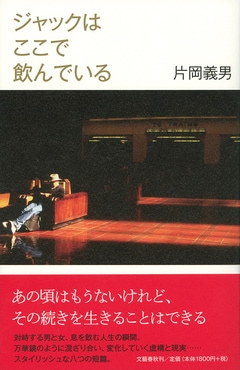「瀬戸内寂聴さんや山崎豊子さんらの作品が好きで、いつか女性の一代記を書けたらと思っていました。それも時代は昭和だけに限定せず、比較的長い歴史のスパンで追う女性の物語を書きたかったんです」
窪美澄さんの新作は五十年前、出版社で出会った三人の女性が主人公。それぞれの半生を丁寧に描いていく。
「まず着想を得たのは、六〇年代に活躍された女性ライターの方です。今もある女性誌の文体は彼女が作ったといってもいいくらいなのに、功績があまり知られていないのは残念だという話を聞き、一人目の登紀子の設定が決まりました。次にイラストレーターの妙子、最後に専業主婦の鈴子という設定を考えましたが、主婦の視点は絶対に入れたかったんです。ひとりの女性の一人称で書くと、ひとつの視点でしかその時代を描けないけれど、三人の女性がいることで三台のカメラを使うことができました」
新雑誌が創刊された当時の出版社は完全に男性優位、編集部は雑然としながらも活気にれていた。そこで母娘三代物書きとしての才能を発揮する登紀子、表紙を任されて時代の寵児となる妙子、結婚して家庭に入ることが望みの鈴子――生まれも育ちも異なる彼女たちは、一九六八年の国際反戦デーで、奇跡的な夜を過ごすことになる。
鈴子が機動隊へ向けて投石すると、
「馬鹿な男どもの下で働くなんてもううんざり!」
登紀子がそう叫び、妙子もこれに続くシーンは実に鮮やかで印象的だ。
「連載時には直接デモに関わる場面はなかったんですけど、編集の方からあの場面を『女たちの祝祭の夜にしてください』と言われ、単行本化にあたって能動的に叫ぶ、石まで投げてしまうというように書き換えました」
仕事、男、結婚、子供……かけがえのないものを求めて彼女たちは悩み、戦い、戸惑いながら年齢を重ねていく。そして、妙子の死がきっかけで、鈴子の孫・奈帆は、往時の話を聞くため登紀子のもとを訪れるようになる。
「働く女性の生き辛さは、今でもあまり変わらないかもしれません。でも少しでも良くなっていたとしたら、前の世代の女性が頑張ってくれた証だと思います。現在の奈帆の状況が辛かったとしても、何かに挑み続けようとすることで、未来を変えられるかもしれない。それは作品を通じて伝えたかったことのひとつです」
この長編の執筆を通じ、「歴史小説が書ける」手応えもつかんだという。
「でも今、真っ先にほしいのは健康、貯金、仕事、体力ですね(笑)」
くぼみすみ 一九六五年東京都生まれ。二〇〇九年女による女のためのR-18文学賞大賞。一一年『ふがいない僕は空を見た』で山本周五郎賞、一二年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞。