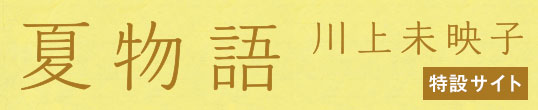前代未聞の小説である。女性が女性である「あたりまえ」にもたれかからずに、どこまで女性性を肯定的に描けるか。本作はこの難題に正面からいどみ、一つの答えに到達している。その意味で本作は、川上未映子の集大成と呼ばれるべきだろう。
前半は、芥川賞受賞作『乳と卵』の「リブート」としてはじまる。主人公の夏目夏子は売れない小説家だ。DVを振るう父親が失踪してから、母親と祖母のコミばあ、姉の巻子とともに大阪で暮らしていた。祖母と母親を癌で亡くしてから、巻子は水商売で二人の生活を支え、夏子は二〇歳で上京して小説家になった。真夏のある日、彼女のつつましいアパートを巻子と姪の緑子が訪ねてくるが、緑子はいっさい口を利かず筆談で話す。巻子の豊胸手術への執着がきっかけらしいが、真相はわからない。
夏子と巻子、緑子との、哀しくも愛おしい絆は本書の通奏低音だ。あの「葡萄狩り」のエピソードは涙なくしては読めないし、読む側までも包みこむような大阪弁の響きに、ずっとひたっていたくなる。
夏子は心理的な理由で性行為ができず、パートナーもいない。小説の執筆も停滞気味だ。そんな夏子が、巻子にとっての豊胸にも似た奇妙な情熱によって、AID(非配偶者間人工授精)に取り憑かれてしまう。
本書のテーマの一つが「反出生主義」だ。一定の確率で苦痛に満ちた生をもたらす可能性があるのに、あえて子供を作るのは親のエゴではないか。この問いに対する回答は、たとえばこうなる。生まれてしまったという事後性のもと、あらゆる価値観の基盤は出生の事実なのだから、基盤そのものは価値判断の対象たりえない……これは一つの正解かもしれないが、しょせんは男の理屈だろう。
その問いに答えるかのように、四人の女性が登場する。夫婦や親子関係に違和感を感じつつもそれを捨てられない主婦、紺野りえ。男女は決してわかりあえず男は不要と主張するシングルマザーの作家、遊佐リカ。子供なんかよりも小説を書けと挑発する独身の編集者、仙川涼子。AID当事者で、父親から性的虐待を受け、反出生主義を主張する善百合子。夏子は彼女たちの生き方に共感したり違和感を覚えたりしつつも、決して誰のことをも否定しない。そのうえで夏子が出した答えは、AID当事者の男性医師、逢沢潤の助けを借りてみずからAIDをおこなうことだった。
ラストシーンは圧倒的な光に満ちているが、複雑な陰影を帯びてもいる。それは「産む性」への讃歌だろうか? そんなはずはない。その空間には、調和も融合もすることなしに、女たちのいろいろな言葉がポリフォニックに残響している。その余白に夏子は「(自分の子に)会いたい」という主体性を見出した。そう、私たちが立ち会うのは、“母性とは別のしかたで”、夏子の主体が回復される眩しいシーンなのだ。
かわかみみえこ/1976年、大阪府生まれ。2007年『わたくし率 イン 歯ー、または世界』『そら頭はでかいです、世界がすこんと入ります』で早稲田大学坪内逍遥大賞奨励賞、08年『乳と卵』で芥川賞を受賞。17年には「早稲田文学増刊 女性号」で責任編集を務めた。
さいとうたまき/1961年、岩手県生まれ。医学博士。現在、筑波大学社会精神保健学教授。専門は思春期精神医学、病跡学。