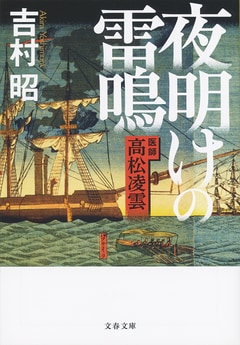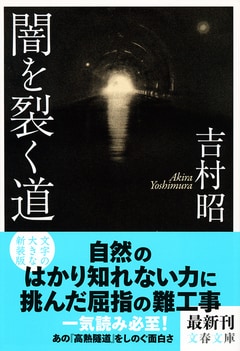最後のページを読み終えて、深く息をつく。手にここちよい重さを感じながら本を閉じた。
読む前よりも読み終えたあとのほうが、なぜか重く感じる本がまれにある。本書で私はそういう経験をした。おそらくそれは、一冊の中に流れている時間の厚みのためだろう。
一組の男女が出会い、夫婦となってともに暮らし、死別するまでの歳月が、夫から妻への手紙を軸に回想される。夫は吉村昭、妻は津村節子。書かれた時代が下るにつれて、文学仲間から恋人へ、そして夫婦へと二人の関係は移っていくが、吉村氏はどの時期の手紙でも、実に率直な言葉で愛情を綴っている。
生涯というものをお前は考えたことがあるか? 愛する女を妻としている男の幸福を考えたことがあるか? それは生命に代えてもよいような幸せなのだ。(一二二ページ)
貴女は人間的に素晴しい。女としても、僕には分に過ぎたひとです。
貴女と共に過すことができたことは、僕の最大の幸福です。生きてきた甲斐があった、生れてきた甲斐があったと思います。(一九五ページ)
吉村文学はいくつかのジャンルに分けられるが、ノンフィクションを仕事とする私がいまも繰り返し読んでいるのは、記録文学と呼ばれる作品群である。それまで見過ごされたり、誤って伝えられたりしてきた事実が、いくつも吉村作品によって掘り起こされてきた。
資料に書かれていることであっても、何度も現地に赴いて自分の足で歩いて確かめ、証言者を探し出して話を聞く。長崎を百七回訪れた話は有名だが、どの作品も気の遠くなるような調査を重ねて書かれている。
それは作家としての誠実さであるが、同時に非情さでもある。資料に書かれていることがすべて正しいとは思っていないから自分で確かめに行くし、証言を鵜呑みにしないから、おびただしい数の人の話を聞いてから判断するのだ。その、書き手としての非情さこそが、私が氏を尊敬してやまない理由であるし、透徹したきびしさと美しさをたたえた文体の鍵であるとも思う。
その吉村氏が、こんなにストレートな愛の言葉を伴侶に捧げていたことに、まず驚かされた。それも、恋愛時代や新婚時代だけではない。復帰前の沖縄への一か月に及ぶ滞在と、心臓移植の取材で訪れた南アフリカとニューヨークを中心とする一か月半の旅の間に書かれた手紙は本書の読みどころだが、これらは『戦艦武蔵』がベストセラーになったあと、吉村氏が四十代を迎えたころに書かれたものである。心細さや寂しさをこれ以上ないほど素直に吐露した文章(便箋半頁に「帰りたい」という言葉が書かれたものもあったという)からは、妻とともに築いた家庭が、真の意味でのよりどころになっていたことが伝わってくる。
だが本書は、夫婦の愛情の軌跡という一言ではくくれない深さと広がりをもっている。吉村氏の手紙は、そのすべてが恋文であるといっていいほど愛と慈しみにあふれているが、普通の恋文と違うのは、文学に向かう姿勢と覚悟が繰り返し語られていることだ。
本書で公開された吉村氏の、青春時代から最晩年までの手紙の数々――文学資料としての価値もすこぶる高い――には、おのれの生きる道は文学にしかないと思いさだめた青年がおり、こころざしを曲げることなく耐えた苦節の時代があり、多くの読者と名声を得てなお愚直なまでに「書くこと」に向き合う作家の姿がある。津村氏によるあとがきに「かれの生涯を書いたこの作品」とあるように、本書は、吉村昭という作家をもっとも近くで見ていた人による、すぐれた伝記としても読むことができるのである。
僕はやります。
文学はつきつめた戦ひです。孤独に徹した仕事です。
机の前で万年筆を少しづつ動かしてゐる時間が僕の時間なのです。あゝ、よく生きてやがる! と思ふのもこの時間です。
人間によくも文学と云ふ仕事を与へてくれたものです。(一六ページ)
結婚前、まだ二人とも学生だったころの手紙の一部だが、すでに吉村氏は、文学を一生の仕事にすると宣言している。はりつめた文章から強い意志が伝わってくるが、心に決めた女性へこのように語ることで、自分を鼓舞していたのかもしれないとも思う。人は、大切な相手に向けて真情を語るとき、自分自身がその言葉にはげまされることがある。さらに、あのときあの人にこう語ったという記憶を、前を向いて歩くための支えとすることもできるのだ。
この手紙の前半には、尾崎放哉のことが書かれている。孤独な漂泊の暮らしの中ですぐれた句を生み、最後にたどりついた小豆島で肺を病んで亡くなった俳人で、のちに吉村氏は放哉を主人公にした作品を書いている。
吉村氏は昭和十九年、十七歳のときに肺浸潤の診断を受けている。この年、癌で母が死去し、翌二十年には父もまた癌でこの世を去った。戦後、旧制学習院高等科文科甲類に入学したが結核を病み、左の肋骨五本を切除する胸郭成形術を受けた。
結核は当時、多くの若者の命を奪った病気だった。私は明治から昭和期にかけての作家たちの短い評伝を連作として書いたことがあるが、そのとき、この病で命を落とした人や、恋人・配偶者を失った人の多さに茫然とした。
本書の中に、結婚して二十数年後、かつての胸郭成形術で執刀した医師から「同じ手術を受けて今生きているのは吉村さんだけです」と言われた話が出てくるが、これは本当に危険な治療で、作家の三浦綾子の恋人は、同じ手術を受けて亡くなっている。
戦争と療養のため進学が遅れた吉村氏が学習院大学に入学したのは二十四歳のときだったという。不安の残る身体で、命をふりしぼって文学に賭けようとしていたのだ。そうした背景を津村氏による地の文から知り、「あゝ、よく生きてやがる!」という言葉の切実さに涙が出た。
同時期に津村氏が吉村氏にあてて書いた手紙も収録されている。そこにはこんな一節がある。
女は家庭にはいつて良い子を育てて、やがて孫を抱き、静かに死ぬのがしあはせなのかもしれませんが、女だてらにいのちをかける仕事、情熱を注げる仕事がほしくて、ほかのものはみんな捨てて了ひました。(一八ページ)
若い津村氏もまた、書くことに命をかける覚悟をしていた。一生独身で小説を書いていきたいという彼女を口説いて結婚した吉村氏は、自分がまだ専業作家として立つことができず会社勤めをしているときから、妻には台所に立つ時間があったら小説を書けと言い、手伝いの人をつけてくれたという。
妥協のない作品を書き続けた一方で、地道な生活者であったこと。妻の才能を犠牲にせず、その作家的成功を自分の喜びとしたこと。作家・吉村昭がそういう人物であったことを本書を通して知ることができたのは、愛読者の一人として大きな喜びだ。
吉村氏の手紙はどれも、息遣いが聞こえるような、ある種の熱を帯びているが、それらが書かれた背景を説明し、夫婦の歴史を振り返る津村氏の文章は淡々として静かである。その対比が吉村氏の生の軌跡をくっきりと浮かび上がらせていることに、何度か読み返すうちに気がついた。
津村氏がこの本のために夫からの手紙を原稿用紙に書き写した、その時間を思う。亡き人の言葉をなぞることは、ともに過ごした歳月を、もういちど自分の中によみがえらせることである。その時間が加わったことで、本書は、読み手の心にあたたかな重さを残す一冊となった。